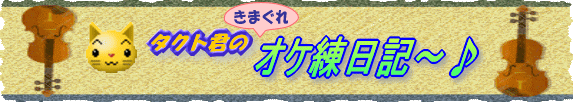
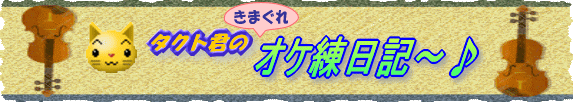
| �@�Q�O�O�X�N�V���P�Q���i���j �@  �@�s���Ă̑�� �Q�O�O�X �{�ԁI�@ �@�s���Ă̑�� �Q�O�O�X �{�ԁI�@�@�@�@�@�@�@�}�G�X�g���̐��X���d�|���́H �@�@�@�@�@�@�����āA����p�[�g���_�l�~�ՁI�H �@�@�@�@�@�@�@ �@���悢��{�ԓ����B �@�ߑO���ɁA�Ō�̍��킹���K�B�����Ă����Ă����ꂪ�I�������A�{�Ԃ��B �@��ʂ���K�͏I��������̂́A�S�y�̖͂`���̃��Y�����C�}�C�`����Ȃ��܂܁A�ꖕ�̕s���E�E�E�B �@ �@�P�x���A���ӂ̃A�i�E���X�A�Q�x���E�E�E�I�P����B�����A�R���T�[�g�̎n�܂�I �@���͂قږ����B�����c�̐l�����炵�Ē������ł����������Ȃ��̂����ǁE�E�E�ł��A�X�����Ȃ����܂��Ă���̂��݂�Ƃ���ς���C���݂Ȃ����ˁB �@�`���[�j���O���ςނƁA�}�G�X�g�����D�u�Ɠ���B �@�u�C�[�S�����v���t�J�n�B�@�`���̃z�����B�@�����H�@�o�����E�����Ƃ��s�b�^���I�@���K�ł͉��x����Ă��_���������̂ɁB�A�}�E�I�P�̖{�Ԃł́A����������ՁH�݂����Ȃ��Ƃ����\�N�����ˁB �@���ԕ��̃z�����̑�\���B�ŏ��̉������k�������������̂́A�قڃm�[�~�X�̏o���B�I�M�h���A�������I �@�N���̃t�@�C���v���[�̓I�P�S�̂����C�Â���B���������őO�v���A�����I���B �@�P�T���x�e�̌�A���悢��u���v�B �@����́u���v�ɂ́A�}�G�X�g���ɂ�鐔�X�̎d�|�����{����Ă���B���āA���̎d�|���A��ł��C�t���l�͂��邩�ȁH�i�����A�C�t�����l��������A�Ǘ��l�Ƀ��[�����Ă݂ĉ������B�������Ƃ����邩���H�j �@��P�y�́A��������`���̃z�����A�s�b�^���Ƃ��������Ńn�}��B���������A�����̃z�����̓��`���N�`��������������Ȃ����I�@���̌���悢�ْ����Y���Ă���B���̂܂܍Ō�܂ł����E�E�E�悵�I�@�Ǝv�����u�ԁA��ꂩ�甏�肪�I�@�s���̒��O�̖��m����p����ׂ����A����Ƃ��M���䂦�̔������E�E�E�܂��A�ǂ���ł��������B �@���肪���܂�̂�҂��āA��Q�y�́B�o�����̌��y��͂P�y�͂̍Ō�̋����𐁂�����悤�Ȃ����Œe���悤�ɂƂ̃}�G�X�g���̎w���ʂ�A�݂�ȟӐg�̗͂����߂Ēe���B�������A�������I�@�Q�y�͂��I���Ƃ܂����┏��B�����ǂ��ɂł����Ă���`�B �@�����c�E�\���X�g�����ꂵ�A��R�y�́B�u�������A�������E�E�E�v�@�}�G�X�g�������O�̗��K�ł������Ă������t�����̒����삯����B���ԕ��A�܂�����I�M�h���̃\���B���܂����`�I�@�����̃z�����́A�����������ƂȂ����ˁI �@�������R�y�͂̌�́A�������ɔ���͂Ȃ������B�ق��I�@�����āA��S�y�́B�`���̃��Y���A�������H �@�M���M���Z�[�t�B�͂��`�A�悩�����B �@���ň�Ԏn�߂ɉ̂��̂̓o�X�̃\���X�g����B�����A�ْ�����炵���B�u���̕����͉��x����Ă��|���ē����o�������Ȃ�܂����A�����̓I�P�̔M���ɗ͂����炢�܂����B�v�Ƒŏグ�ł���������Ă����B �@�m���ɁA���̓��I�P���������M���������B�䂦�ɁA�g���R�}�[�`�̑O�̃I�P�E�������Ƀ{���e�[�W���������������Ŕ��肪�N���N�����Ă��܂����B����A���́A�܂������������ł����ǁE�E�E�B�}�G�X�g��������ł��傢���傢�Ƌq�Ȃ�Â߁A�g���R�}�[�`�ցB����`�A����Ȃ��Ƃ�����Ȃ�ĂˁB�i��j �@�ŏグ�̐ȂŃ}�G�X�g�����u���ɂ��Ďv���ƁA�������Ŕ���������Ɛ���グ�ďI��ɂ�������Ă��悩���������ˁ`�B���t��A�����I��邵���B���s�����Ȃ��B�v�Ȃ�ăW���[�N�������Ă��܂����B�����ځ� �@�Ō�́A�������Ղ��Ԃł��̂������������̃v���X�g�A�v���X�e�B�V���ő��I���I �@�u�u���{�[�I�v�̐�����ԁB����`�A�y�F�I�P�̗��j�Ɏc�閼���ɂȂ�����Ȃ��H �@�A���R�[���͑S�R�l���Ă��Ȃ������̂����ǁA�}�G�X�g�����@�]�𗘂����āA���̒��ł���ԃ��W���[�ȍ����������ĉ��B����オ��܂����`�B �@���Â��A���̃}�G�X�g���͉��o����肾�Ȃ��Ɗ��S���܂����B �@ �@�y�Q����ł̂Ђƌ��z �@�I�P�̃����o�[�łQ����ɍs���ƁA�}�G�X�g�����z�����̃����o�[�Ɂu�N�B�A�����A�ō��̏o���������ˁI�@����Ȏ��͂�����Ȃ�A���K�̎����炿���Əo���Ă�`�v�ƈ��肵�Ȃ���b���Ă����B�m���ɁE�E�E�B �@�Ă������A�{�l�������g���{�Ԃ̏o���ɋ����Ă����̂ŁB�B�B���m�̗́A���悢��J�Ԃ��H �@�Ƃɂ����A����́A�z�����p�[�g�ɐ_�l���~�Ղ����悤�ł����B �@�y�}�G�X�g���̍ő�̎d�|���I�H �g�B���͌Ђ��琶�܂��́H�z �@�قƂ�ǂ̃A�}�E�I�P���������Ǝv�����ǁA�{�ԂɌ����āA�X�~����X�~�܂ł���ł����Ƃ������炢�A�������荇�킹���K�������ˁH�@�s���ł��������������������X�^�C���B�ł��A���̃}�G�X�g���l�́A�킴�Ə����B���ȕ������c���Ă����炵���B���ꂪ�{�Ԃł悢�ْ����ĂԂ̂��ƁE�E�E�{������H �@�ł��A�m���ɁA����͂��̂������ł݂�Ȉӎ����W�������Ă����悤�Ɏv���B���[��A�[�C�C�B �@�����A�u�Ă̑��v���I���ƁA���͂X���̃A���E�t�F�X�i�g�c�}�G�X�g���o��I�j�A�P�Q���̃v�b�`�[�j�ƖZ�����Ȃ�ˁB���ߑ��߂ɕ��ǂ݂����Ă����܂��傤�I �@�݂Ȃ���A�����l�ł����B �@�@ |
| �@�Q�O�O�X�N�V���P�P���i�y�j�@�P�R�F�O�O�`�P�X�F�O�O�@�X�e�[�W�Z�b�e�B���O���Q�l�v�� �@�@���悢��Q�l�E�v�����`�`�`�I�I �@�����A���������ɃQ�l�E�v���܂ł��ǂ蒅���܂����B �@�܂��́A���݉c�B����́A�������吨�Ȃ̂ŁA�R��̑g�ݕ��ɂ͂��Ȃ�̍H�v���K�v�B�z�����̃I�M�h�������S�ƂȂ��āA�W�X�ƍ�Ƃ������B�}�G�X�g���̊�]��؊ǂP��ڂ̗v�]�����Ȃ��邽�߁A�������낢��l���Ă����݂����B�������G�ȃZ�b�e�B���O���݂�Ȃ̋��͂łR�O���قǂŏI���I�@�f�����I�I �@���̌�A���o���E�����c�̗����ʒu�m�F�Ȃǂ̌�A�}�G�X�g�����w����ɏオ��A�Q�l�����E�v���[�x�̊J�n�B �@�܂��́A�u�C�[�S�����v���ȁB�Q�T�ԂԂ�̍��킹�Ƃ������Ƃ������āA�����������Ȃ����E�E�E�B �@�ǂ����Ă��C�ɂȂ�ӏ����ق�̏��������Ԃ����K���āA�u���v�� �@�u�C�[�S�����v�����������ǁA�`���̃z�����̏o�����Ɖ������҂�����͂܂�Ȃ��B�ӁA�s�����`�B �@���̌���A��͂�ǂ��ƂȂ��������Ȃ�����킹�A�P�y�́A�Q�y�͂Ɛi�ށB�R�y�͂ɓ���O�ɁA�����c����B �@�����c�������������Ƃ���ŁA��R�y�͊J�n�B�u���x�����Ă��f�G�ȃ����f�B�[���Ȃ��v�ƃ^�N�g�͕������тɊ������Ă��܂��B�����āA��S�y�́B�\���X�g���������̂͂��̓������߂ĂŁA�I�P���ɏ����Ƃ܂ǂ�������悤���B �@��ʂ荇�킹���I������Ƃ���ŁA�x�e�B�t�[�b�B�����n���n������Ƃ��낪�����āA��ꂽ��B �@���āA�x�e��́A��S�y�͂̕Ԃ����K�B�}�G�X�g�����獇���c�Ɂu�V�g�̉H�ɏ���Ĕ��ł����悤�ɁA���̌��̕��̂��q�l�ɂ������������Ő��������ɔ���āI�v�u�����Ƃ����Ɓv�Ɛ���������B �@�����āA�Ō�Ɂu���ɒj���́A�����͂������肨����H�ׂĖ����̂��߂̗͂����Ă��ĉ������ˁI�v�����āB�i�j �@�����c�E�\���X�g����͈ꑫ��ɃQ�l�E�v���I���B �@�u�����ɂ͂����ƃI�P�͏��ɂȂ��Ă��܂�����B�v�ƃ}�G�X�g�����W���[�N�����B����H�W���[�N�ł͂Ȃ��A�{�C�H �@���āA��������̓I�P�݂̗̂��K�B�P�y�͂���B����܂ł̒��ӓ_���ē_������悤�ɁA�Q�y�́A�R�y�͂Ɛi��ŁA�Ō�Ɂu�C�[�S�����v������āA�\��ʂ�P�X��tutti�I���B �@�݂Ȃ���A�����l�ł����B�����A����܂ł̐��ʂ���������܂��悤�ɁE�E�E�B �@�y�����{�P�̃}�G�X�g���z �@�^�N�g�����肵�����ɂ��ƁA�}�G�X�g���͑O�X���I�����_����A���������肾�����炵���B�������A�A������Z�������Ă��āA�����{�P���c���Ă����悤�ŁA�Q�l�E�v���̓r���łӂƈӎ�����肵�Ă����炵���B�Ђ傦�`�A�����̂��߂ɁA�����A���ĐQ�ĉ������I �@ |
| �@�Q�O�O�X�N�U���Q�W���i���j�@�P�S�F�O�O�`�Q�P�F�R�O�@�S�� �@�@�����n��������������� �@���Ȃ范�����J�̒��A�ߌ�͐��N��قő��̂P�`�Q�y�͂̍��킹�B�@ �@��͂���������E�E�E�B�{���ɋ��ǂ��ɂ����Ăق����I�I �@ �@�Ƃ���Ȃ��Ƃɂ͂߂����A�}�G�X�g���̔M���w�����n�܂�B �@�`���̂U�A���́A�]���Łu���c�n��A�������̂E�E�E�v�Ə����ē���܂��傤�I�H �@�؊ǂ͂����傫�����Ȃ��悤�ɁB �@���̑��́A����܂Ō���ꂽ�ʂ�B �@�����āA�Q�y�́B���̏o�����̉��͉\�Ȍ���A�傫���������͂�����ƁB �@�X���ߖڂ���̂Q�������@�C�I�����͑S���������Ċm���ɒe����悤�Ɂi�S���ߊԂ����ł�������H�j �@�����āA�؊ǂ͂����Ɖ��̃����[���I �@�T�U���ߖڂ̃t���[�g�ƂP�������@�C�I�����́A�����������炢�傫���ڗ����āI �@�P�R�X���ߖڂ���̓t���[�g�ƃt�@�S�b�g������B���̐l�͉����T���āB �@�P�T�X���ߖڂ���͌����ǁA��ɋC���Ȃ��I�@�t���[�g���C�j�V�A�`�u���I �@�P�V�V���ߖڂ���̃t�@�S�b�g�͑傫�߂ɁB �@�o��������������͑������ǁA�Q�Ă������ɂȂ�Ȃ��B �@ �@�Ƃ����܂łň�U���K�I���B�㔼�͖{�ԉ��̎s���s����ّ�z�[���ɂč������킹�B �@�܂��A�E�H�[���A�b�v�����˂āA�U�T�T���ߖڂ���B�����͕t�_�Q�������œ����Ă���p�[�g���厖�B �@�A���g���e�m�[�����o�X���\�v���m�̏��ŏo�Ă��邩�炻�̏ꏊ�ɂȂ����瑼���傫���B���̑��̃p�[�g�͏����T���߂ɁB�i�\�v���m�͉��������đ�ς��낤���ǁB�j �@�V�R�O���ߖڂ͕K���̂������߂�悤�ɏ������I �@�W�T�P���ߖڂ���̍����͑O��̃}�G�X�g���̗v�]����������}�X�^�[���Ă��Ă����B�n�j�I �@�������I������X�Q�O���ߖڂ���̓I�P�̍Ō�̌������I�@��������ƂˁI�I �@�X�Q�W�`�X�R�P���ߖڂ͊ǁA�X�R�Q���ߖځ`�X�R�T���ߖڂ͌����撣��悤�ɁI �@�X�R�U���ߖڂ���̖؊ǂ̏�s�A�ł������傫���I�I �@�����ŋx�e�B �@�㔼�͂Q�R�V���ߖڂ�����K�J�n�B �@�ƍ��킹���n�߂�O�ɁA�}�G�X�g���������B �@�u�݂Ȃ���A�O�b�����P���v�Ƃ����V�g�ɂ��Ē��ׂĂ݂܂������H�v �@�Ƃ����āA�}�G�X�g���̓C���X�g���q���q���B �@�u�P���v�͑�Q�ʂ̒q�V�g�ƌ����Ă邯�ǁA�����ڂ͓V�g�Ƃ͎v���Ȃ�������ƃO���e�X�N�ȕ��e�ŁE�E�E���̓V�g���_�̑O�ŔԂ����Ă��邽�߂ɁA�_����j������y��^����ꂽ���Ă��Ȃ��Ȃ��O�i�߂Ȃ��B�����āA���߂��l�X�͂ǂ����邩�H�@�����̉��y�ɖڂ�������B�����A�₩�ƌ����Ă����g���R�ւƌ������킯�B���ꂩ��̂��̂͂��������V�[��������B�v �@�����āA���킹�J�n�B�O���x���킹�Ă���̂ŁA���͋C�͂悳�����B�I�P�̕����܂��܂����K���K�v���ȁB�i�ׂ����Ƃ���ŁB�j�@�g���R�}�[�`�̕����͂����Ƃ����Ɩ��邭�z�C�ɁI�@�i�ł��A���܂�ɂ��z�C�Ȋ����Ńe�m�[���x�搶�̃C���[�W�ƈ�����̂��A�x�搶�u�t���E�E�E�A�t���E�E�E�H�v�Ƃ����Ȃ���q�ɁI�Ȃ�V�[�����j �@ �@�������킹�́A���ƃX���[�Y�ɏI���܂����`�B �@�����c�����U������A�I�P�͍Ăї��K�B�u�C�[�S�����v����B�i����͖`�����������Ȃ������̂ŁB�j �@�o�����̃z�����͂P�Ԃ̉��ʂ��ő�ɂȂ�悤�ɂ��̑��͗}���āB �@���y��͂V���ߖڂ̂��Ɍ����Ă�������cresc����B���ɂȂ��Ă���������キ�Ȃ炸�ɉ��ʂ��ێ��B �@�����̃_�C�i�~�N�X���͂�������邱�Ƃō���̓W�J�Ɋ��҂��������A�ϋq�̎����Ђ�����B �@�`�̂Q���ڂ���̖؊ǂ̂S�������́A�W�������Q���������Ď��̂��鉹���B �@���Ƃ́A����܂Ō���ꂽ���Ƃ��e�������������邱�ƁB �@ �@�X�����܂ł݂�����Ɨ��K�ł����B�@�݂Ȃ���A�{���ɂ����l�B �@���́A���悢��Q�l�v���B����܂łɁA�l�E�p�[�g�E�Z�N�V�����ōX�Ȃ���K���I �@�y�y�����Ȏw���z �@��˓c�搶�́A���Ɋy�������Ɏw��������B �@�Ȃ̂ŁA���t���Ă��鑤�����̂܂ɂ��������܂�A�m���m���ʼn��t���Ă����肷��B �@������Ȃ��H |
| �@�Q�O�O�X�N�U���Q�V���i�y�j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�u���v�R�y�́��C�[�S���� �@�@�N�Ɖ��y���Ă���̂��H���l����B �@�����́A���Ȃ���������E�E�E�ł��A���N��ق̗�[�͂V������łȂ��Ǝg���Ȃ��B �@�������A�n�����g�������������A�����O�|���Ŏg����悤�Ȕz�������Ă��炦�Ȃ����̂��낤���H �@�w��̑����J������NJy��`�[���͏����}�V�����A�Z��X�ɖʂ��Ă��邽�ߋ��Ȃ������ɂ���}�G�X�g���ƌ��y��`�[���͊������ŗ��K�B���C�̓łł����B �@����Ȓ��A���K����l�߂ƌ����������B �@�܂��́A���̂R�y�́E�S�R���ߖڂ̂P�������@�C�I��������B�`���ɏo�Ă�����̃��@���G�[�V�����͉����ɂ����Ƃ����ƋC��z���āB�Ԃɓ����Ă���N�����l�b�g�ƃt�@�S�b�g�͐[�����ŁB�Q�������@�C�I�����ƃ`�F���̃s�`�J�[�g�̔��t�͂��݂��������ƕ��������ĉ�b����悤�ɁB �@�U�T���ߖڂ���̖؊ǂ̃����f�B�[�͓r��r��ɂȂ�Ȃ��ŏ�Ƀ��K�[�g�B �@�Ƃ�����Ƃ���ŁA�`������B �@�o�����̖؊ǂ͂Ȃ�ׂ����ʂ��������ŁB �@�Q�T���ߖڂ���̂Q�������@�C�I�����ƃ��B�I���̃����f�B�[�A�������I�@�R�R���ߖڂ���͑��̊y�킪���t�ɉ����̂ŁA�O��菭���傫�߂ɁB �@�X�V���ߖڂ���̖؊ǂƃz�����̓I���K���ɂȂ�������œ������s�b�^�������Ęa�����ɁB �@�X�X���ߖڂ���̕t�_�����́A�����L�������ɂȂ�Ȃ��悤�ɁB���ɂW����������������l�܂��������œ����̂��銴�����B �@�Ō�̌��y��̃s�`�J�[�g�͕n��ɂȂ�Ȃ��悤��������B �@�����āA�C�[�S�����B �@�����̓`���[�o�����Ă���̂ŁA�����Ȃ�A���O������B �@���ǂ͑O�̐l�̉��ʂ�������������p���ŁA��������̃��C���ɂȂ�悤�ɁB�i�o�x��Ȃ��j �@�i�^�N�g�����肵�����ɂ��ƁA�}�G�X�g���͂����ƃe���|���グ�Ă�����炵���B���njQ�͊o�債�Ă����悤�ɁI�j �@�U�O���ߖڂ���̃g�����{�[���͏d���Ȃ�Ȃ��Ő�i�ނ悤�ɁB�i�㔼�������j �@�a�̂P���ߑO�̃��@�C�I�����́A��C�ɋ삯�オ��܂��傤�I �@�Q�P�S���ߖڂ���̃��@�C�I������con anima�i�����������āj�@�̂�т肵�Ȃ��悤�ɁB �@�Q�W�T���ߖڂ���̖؊ǂ̂W�������͂Ȃ�����ɂȂ炸�ْ����������āB �@�R�R�P���ߖڂ���̖؊ǁ����B�I�����̃g�����͖��邭 �@�r����̃t�@�S�b�g�A���B�I���A�`�F���̃����f�B�[�͂����Ղ�ƁB �@���āA�����́A�ߌ�I�P���̂��ƁA�鍇�����킹�ƃn�[�h�����NJ撣��܂��傤�I �@ |
| �@�Q�O�O�X�N�U���P�S���i���j�@�X�F�R�O�`�P�T�F�S�T�@�u�C�[�S�������ȁv���u���v�R�C�S�y�� �@�@ �@�����́A�܂�����ԁi�Ƃ����Ă��X�������[�j�Ƀ`�F�����R���o�X�̓��P�B�ۑ�͂��������E�S�y�͂��B �@�}�G�X�g���ɒ��X�Ɏw������������Ȃ�āA�A�܂����悤�ȁA�R�����悤�ȁB�B�B �@���̌�A�u�C�[�S�����v�̍��킹�B����̒��ړ_�͂��ꁫ �@�E�o�����z�����̘a�����킹�� �@�E2���ߖځ@�@�`�F���̂߂��߂��̉������킹�� �@�E36����28�̂Q�������@�C�I�����̃{�[�C���O�ύX�@�A�N�Z���g�����Ȃ��悤�ɋ|�̕Ԃ����~�߂� �@�E�P�������@�C�I�����̃����f�B�͐F���ۂ��@�V���K�|�[���q��̃A�e���_���g�̂悤�ɔY�܂����H�I �@�Ƃ����ŁA�}�G�X�g�������ӁH�̗]�k�̎n�܂�n�܂�` �@�u�Y�܂����̓V���K�|�[���łȂ�������A�L���Z�C�ł͂��߂��ˁB���ł����L���Z�C�̓��[���X���C�X�̏��S�n�B�ԂłȂ��̂ɕς����ǁE�E�E�B���������Ԃ͂����ȎԂɏ���Ă��̈Ⴂ���������ׂ����ȁB�����Ԃƌy�ł͐��E���ς��B�v �@���y�����낢��ƌ��������������́E�E�E�s�� �@���������A���w���̏��̎q�ɍD���Ȓj�̎q�̂��Ǝv���Ȃ���e���Ȃ����Ƃ����ăZ�N�n�����Ƃ̖쎟���Ă܂����B(^_^;)�@ �@���āA�Ăт܂��߂ɁE�E�E �@�E122����̃g�����{�[���͉��̗����オ�肪�������B�傫���y��͂ǂ����Ă��x���Ȃ�̂ŁA�����t���C���O���邮�炢�ɐ������� �@�EL����̓z�����̃\���ɂ��킹��悤�ɔ��t���邱�ƁA���ʁA�j���A���X�Ƃ� �@�ES�̑O4���߂̃r�I���̍��݂͐���悤�ɒe�� �@�E549����̃r�I���ƃ`�F���͊��炩�ɁA16��-16��-8���̉��`��8���ɃA�N�Z���g���Ȃ��悤 �@�Ƃ܂��A����Ȋ����B�݂Ȃ���A�������胁�����܂������H �@�ߌ�́A���E�R�y�͂���B �@�u���̋Ȃ͂��A�V���̃C���[�W�����炳�B�Ƃɂ����\�Ȍ������������Nj����āI�@��ΑĐ��ʼn����o������_���I�I�v �@�o�����̖؊ǁA�P�������@�C�I�������炷�łɃ}�G�X�g���̂��C�ɏ����Ȃ��炵���B���x�����x������炵�������o��܂ŌJ��Ԃ��B�������E�������E�E�E�ߌ�̗��K�ɂ͂�����҂�h���t���[�Y�ł���B�i�����Ă���ƐS�n�悭�Ė����Ȃ����Ⴄ��ˁB�j �@�E�r���̃g�����y�b�g�͂��̓V���̐��E��ł��j�鈫���o��݂����Ȋ����ŁI �@����͂�A�g�����y�b�g�͐_�ɂȂ����舫���ɂȂ�����Z�����ˁB�i��j �@�E���ԕ��̃z�����E�\���͂����R�ɂǂ����`�B���Ă���悤�ɁA�݂�Ȃ͂��̑O�̕�����e���Ă����ĂˁB�i���̂R�A�����x���Ȃ肷���Ȃ��悤�Ɂj �@�����āA�S�y�́B������Ȃ����������𒆐S�ɍ��킹�B �@�܂��́A�o�����̕������ǂ̂��炢�̑����܂ł��邩�A�������߂��班�����e���|���グ�Ċm�F�B �@�ǂ����}�G�X�g���͉\�Ȍ��葬����肽���炵���B�݂�ȁi�Ƃ����Ă������͊NJy��݂̂��j�A�撣���Ă��Ă����Ăˁ`�B �@���̌�ɑ����`�F���E�R���o�X���͒��̓��P�̐��ʂ��o�āA�Ȃ��Ȃ��͋������������B �@�E�X�Q���ߖڂ̃`�F���E�R���o�X�Ŏn�܂銽��̎��́A�Ⴂ�Ƃ��납��ǂ�ǂ�ǂ�ǂ��Ƃ���ցA�C���������g���Ă����悤�ɁB�����āA�Ō�i�Q�O�P�`�Q�O�Q�j�͏_�炩�ȗ��ō������ŁI �@�E�R�R�P���ߖڂ���n�܂�}�[�`�́A�_�ɋ߂Â��Ȃ��Ē��߂��l���g���R�i�����̉��y�ɖ��������j�ŕ�����ĕ����Ă������A�����Ƃ����Ɗy�����ɁI �@�E�S�R�Q���ߖڂ���͓����̎n�܂�B�i�����̉��y�ɓM��Ă��Ă͂����Ȃ��H�j�@�������I�I �@�E�����ĂT�X�T���ߖڂ�����@���n�܂�B�g�����{�[���͐_�̐�������_�X�������ŁB �@�E�U�Q�V���ߖځA�U�R�P���ߖڂłT�x���������������ɐ_�ɂЂꕚ�����C�����ŁB �@�E�U�R�O���ߖځE�U�R�S���ߖځE�U�R�W���ߖڂ̂R���ڂ͂�����Ƒ҂����肷��̂ŁA�w�����悭���Ĕ�яo���Ȃ��悤�ɁB �@ �@�ق��ɂ��ׁX�����w�E�������������E�E�E�^�N�g�͏����ڂ��肵�Ă����̂ŁA�����Ƃ������͊e�p�[�g�Ńt�H���[���ĂˁB �@���Ă��āA����tutti�͂Q�T�Ԍ�B����܂łɏ����ł��}�G�X�g���̂����Ă��郔�B�W�����ɋ߂Â��邩�H �@�݂Ȃ���A�撣���ĉ������I �@ �@�y�}�G�X�g���̂��ڂ�b�z �@���g���Ă��鑍�����߉q�G���̎g���Ă����y���Ő펞���̂��̂ł��邱�ƒm�����B�Ƃ������Ƃ͂m���͂���ȍ~�C�[�S�������������t��Œe���ĂȂ��Ƃ������ƁB������������I �@���̋Ȃ̓A�}�`���A�ɍD�܂�Ă���悤���ˁB �@�����āA�������j���[�X�I�I �@���N�̃A���T���u���E�t�F�X�^���g�c�}�G�X�g�������I�H �@�Ȗڂ̓n�C�h���̌����ȑ�P�O�S�ԁu�����h���v�i�����j�Ɍ��܂�܂����`�B�@ �@�H�ȍ~���Z�������NJy���݂ł��ˁ� |
| �@�Q�O�O�X�N�U���P�R���i�y�j�@�P�W�F�O�O�`�Q�P�F�R�O�@�������킹�ق� �@�@�̎��̈Ӗ��������Ɗ��݂��߂āI�I �@�����́A���������ɂ��{�ԉ��ɂč������킹�ł��B �@�Ƃ͂����Ă��A�������ɖ{�Ԃ��Ȃ���̕���Z�b�e�B���O�͖����Ȃ̂ŁA�R��͂Ȃ��B �@����̍����c�́A�s���s�y�F������c�v���X�s���s�����A�������c�̃v���X��ʌ���̑����P�S�O���Ƃ����及�сB�������A���̂����̂W�������͏��̌��Ȃ̂������B �@�Q�O�O���ȏ�Ƃ������t�҂ׂ�}�G�X�g���́A�����Ȏ�r���v������܂��ˁE�E�E�B �@���āA�m���̒���������I���Ă���A�d�Ԃɔ�я�����Ă����}�G�X�g���́A�{�Ԍ�Ƃ͎v���Ȃ��G�l���M�b�V�����Ŏw���I�@�Ђ傦���`�A�������X�^�~�i�I�I �@�S�y�͂̍����c�������E���o���āA�܂��͈�ʂ荇�킹�B �@�����āA�Ō�̕�����Ԃ����K�J�n�B�����c�݂̂Ȃ���ɁA�u�g�I�h���������t�͓��ɋ����������P�ꂾ����͂�����傫���I�v�Ƃ��u�����́A�����ƃ\�t�g�ɉ\�Ȍ��菬�����v�Ȃǂ̎w��������B �@�}�G�X�g���͌��t�̈��Ɍ��\������肪����悤�ŁA���x�����x���[���������܂œ����Ƃ�����J��Ԃ��B�i���̂ւ�͋g�c�}�G�X�g���Ƌ߂��ł��ˁB�j�Ȃ̂ŁA���K�͂��܂�i�܂��A�����Ƃ����Ԃɍ������킹�̎��Ԃ��I����Ă��܂����B �@�Ō�ɁA�}�G�X�g�����獇���c�݂̂Ȃ���� �@�u�y���Ȃ�Ă̂͂����̃��������ɂ����Ȃ��B��������A�l��͂����̉��ł͂Ȃ��A���y��a���o���Ȃ���I�@���ɉ̂́A�̎����������Ӗ���͂ݎ��₷���͂��B�@����܂łɉ̂̈Ӗ�����������c�����ė��ĉ������B�v �@�Ƃ̒����B�m���ɁA�Ӗ���m�炸���ĉ̂Ȃ�ĉ̂��Ȃ���ˁB �@���������U������A�I�P�͂܂��܂����K�B�P�y�́E�Q�y�͂̍��킹�B �@����܂Ō����Ă������ƁA�A�A���`��A�o���ĂȂ��H �@������x�y���̃������������Ċe�����K���K�B �@�y�}�G�X�g���̂��ڂ�b�z �@����������ł̂��ƁB�@�����ȃh�C�c�l�w���҂���S�y�͂ō����c���̂��n�߂�ƁA�O�ɂ���h�C�c��x���x���̃��B�I���t�҂ɉ���炵����ɘb�������Ă���B�����낤�H�H�H�@�ƌ�ŕ����Ă݂�ƁE�E�E �@�u�ނ�͈�̉���ʼn̂��Ă���́H�v �@�Ǝ��₳�ꂽ�Ƃ��B �@���ɏ��Ȃ����b�ł����B�`�����`������ |
| �@�Q�O�O�X�N�T���R�O���i�y�j�`�R�P���i���j�@���h�F���C�݂��Ƃ��q�x�n�ɂ� �@�@�����f�B�[�S���́A���ɂ������ӔC���������āI �@���N�����C�݂ɂč��h�ł��I �@�X�P�W���[��������ƁA�A�A�P�R������tutti�J�n�A�[�H��Q�P���R�O���܂�tutti�ƈ���ڂ��猋�\�n�[�h�E�E�E�B �@�ł��A�݂�ȏW�܂�܂����˂��B�S�O���߂����Q�����Ă̑升�h�ƂȂ�܂����B �@���������X������P�T�����܂ł݂�������K�B �@���̓���ԂŁu�C�[�S�����v�u���v�Ƃ������`�ɂȂ��Ă��������B �@��ې[���͍̂��h�Q���ڂ̌ߑO�̗��K�B��˓c�搶�͑O���i�Ƃ����������̑����܂ŁH�j�̍��e��̂������c���Ă���̂��A�����ɂ��������`��B���E�I�Ȏw���҂���̗��b�Ȃǖʔ����̂Ȃ�̂��ā`�B �@���̒��ŁA�u�����f�B�[��S������l�͈��̉��������Ƒ�ɁI�@���̊�����Ȃ������o���Ă͂����Ȃ��B�������ƂȂ������o���Ȃ�Ă����Ă̂ق��I�I�@�����f�B�[��e���Ƃ������Ƃɂ����ƐӔC�������āI�v�ƔM������Ă����B �@������Ă��āA���ƂȂ������ǁE�E�E����͂قƂ�ǂ������y�̓y���S���Ă���R���g���o�X�t�҂���̐S�̋��тƂ������肢�̂悤�Ɏv���Ă��܂����B �@���ǁA�u���E�R�y�́v�̖`���̂P�����o�C�I��������A���̌�̂Q�����o�C�I���������B�I������̃����f�B�[�͂܂��܂��搶�̖]�ނ悤�ȉ��y�ɂ͉����y���B�B�B�S�����߂Ēe���E�E�E�ȒP�Ȃ悤�ň�ԓ�����ƂȂ̂�������Ȃ��B �@�u�C�[�S�����v�́A�NJy��̘A�W�v���[�������ƃX���[�Y�ɂȂ�Ȃ��Ɖ��y�̗��ꂪ�~�܂��Ă��܂��̂ŁA�����ĂЂ�܂��ɁI�@ �@���̑��A�u�x�[�g�[���F���̋Ȃ̓e�B���p�j���ƂĂ��d�v�I�v�Ƃ̂��ƁB �@�e�B���p�j�S���̂f����A�撣���Ăˁ[�� �@��˓c�搶�E�E�E�N�[���ȕ����Ə���Ɏv���Ă������ǁA�^�N�g�����Ǝ��͂��̂�������M�n�ł����I�@ �@�S�y�͂̍Ō�ȂW�����v���Ă��悤�ȁE�E�E�B �@����͂Q�T�Ԍ�ɂ��悢�捇�����킹�B�ǂ�Ȋ����ɂȂ�̂��h�L�h�L���N���N�B �@�����c�̕��X��S�z�����Ȃ��悤�ɁA�e���E�e�p�[�g�ł������蕜�K���K�����Ă����ĂˁB �@�y���������E�肫�H�H�H�z �@��˓c�搶�̂��b�̒��ɂ��т��ѓo�ꂷ��u���������E�肫�v�E�E�E�N�H �@�@�g���������̂��`��h�Ɖ̂��Ă���炵���B�������A���̉́i���H�j�ɂ͓Ɠ��̃��[�h������A���ꂪ�搶�̐S�̋Ր��ɐG��Ă�����悤�B �@�����o�[�݂̂�Ȃ́A�u���������E�肫�v��m���Ă܂������H�H |
| �@�Q�O�O�X�N�R���Q�W���i�y�j�@�P�W�F�S�T�`�Q�O�F�S�T�@�u�C�[�S�������ȁv���u���v �P�y�� �@�@�؊NJy��̒��łނ��������̂́E�E�E�H �@�R�T�ԑ����Ă�tutti�ł��B�C����������܂��ˁ`�B�o�ȗ������Ȃ肢���ł��B�g�����y�b�g�����ȂȂ̂��c�O�ł����E�E�E�B �@���Ă��āA�����̓C�[�S�����̍��킹����B �@�E�`���̃z�����ƃ`���[�o�͌����Đ��X�������ɂȂ�Ȃ��悤�ɁB�e�B���p�j�̉e�ɂ����ƉB��銴���ŁB �@�E�Q���ߖڂ���̃`�F���E�R���o�X�͉��������킹��悤�ɁB�i�p�[�g���Ŋm�F���Ă����Ăˁj �@�E�`����̖؊ǂ̃����f�B�[�́A�����̂S�������̗���ɂȂ�Ȃ��悤�ɁB�S�ڂ̃X���[�͂������������B �@�E�W�O���ߖڂ���̂u���́u�������܂��A�������܂��E�E�E�v�Œe���āB �@�@�b���͉��̗����オ�肪�x��Ȃ��悤�ɁB �@�E�`���������������O��2nd Vn.�̔����̓����́A�������n�܂�\�������߂āB �@�E�`����������������̂s���̂��������́A�͂�����ƁB�����𐳂����B �@�E�b����S���߂����ď���rit.�i���ɑ����b���̃����f�B�[���Q�Ă������ɂȂ�Ȃ��e���|�Ɏ����Ă����j �@�E�b����̂b���̃����f�B�[�͂P�U�������ŋ}���Ȃ��B �@�E�P�P�V���ߖڂ����肩�班������accel.���A�c�ł`�������������̃e���|�� �@�E�Q�P�O���ߖڂ���̂e���Ƃu���͂Q���ߊԂł�������cresc.���ĂQ�P�Q���ߖڂ���͍��Ȋ����i�H�j�� �@�E�Q�P�S���ߖڂ���̂u���̃����f�B�[�͂����Ղ聕�������肵�����ŁB �@�E�f�̂Q���ߖڂ���e���|�������� �@�E�Q�U�P���ߖڂ���̖؊ǁ��u���A�u���͂W���߂��P�t���[�Y�ƂȂ�悤�ɁB �@�E�g����̒ጷ����A�N�������Ă���܂���B����������K���I �@�E�h���班��accel. �@�E�h����̒ጷ�i�Ə����x��Ăe���j�A�����炶�킶���cresc. �@�E�k�̂Q���߂߂͕K�����ɗ����B���̌�S���߂�����cresc.�������̌J��Ԃ���Y��Ȃ��B �@�E�R�V�O�`�R�V�P���ߖڂ�molto cresc. �@�E�R�W�W���ߖڂ���̂g���A�s�����͉������������荇�킹�āB �@�E�o����U���߂�����accel.���A�`�������������̃e���|�� �@ �@�Ƃ��̂�����Łu�C�[�S�����v�̍��킹�͏I���B�㔼�͑��̂P�y�� �@�E�`����2nd Vn.�Ƃu���A�u�������̂A�������̂v�Ə����Ă���e���I�H �@�E�T�P���ߖڂ���͏d���Ȃ炸�A�������銴���ŁB �@�E�T�T���ߖڂ���̌��Ɗǂ̂��������́A�����Ԃ���炸�A�ْ����������� �@�E�V�S���ߖڂ͑S���������ɂ� �@�E�P�P�O���ߖڂ���̂u���̓��B�u���[�g�����܂肩�����ɒW�X�� �@�E�P�X�W���ߖڂ����1st �u���D�͂S�������ʼn��������Ȃ��悤�ɁI �@�E�R�U�R���ߖڂ�1st Vn.�̓W�F�b�g�R�[�X�^�[���C���[�W���āi�R�U�S���ߖڂ̓����傫���Ȃ肷���Ȃ��悤�Ɂj �@�E�R�U�X���ߖڂ͂����I�I �@�E�S�Q�V���ߖڂ�1st Vn.�͂S�������ʼn��������Ȃ��悤�ɁA���ł��������ŁB �@�E�S�Q�X���ߖځA1st Vn.�͂S��������cresc. �@�E�S�U�X���ߖڂ̌��y��͈�Ăɂ��@�g���͎���悭 �@ �@�搶�̌��t�������Ȃ��悤�A�������胁���������肾���ǁA�A�A�����Ă���Ƃ��낪���邩���B �@���ꂼ��̃p�[�g�Ńt�H���[����낵���ˁB �@����i�S�^�P�P�j�́A���̂R�A�S�y�͂���邻���ł��B �@�y�t���[�e�B�X�g���I�J�������H�z �@�u�C�[�S�����v�̍��킹�̎��A�N�����l�b�g��������Ɛ����ɂ������ɂ��Ă�����A�}�G�X�g���� �@�u�N�����l�b�g�Ƃ��I�[�{�G�Ƃ����[�h�y��͉��̗����オ��Ƃ������ˁB�_�u�����[�h�Ȃ{���ɓ���Ǝv����B����ɔ�ׂ���A�t���[�g�͊ȒP�Ƃ������E�E�E����Ȃ��ƌ����ƃt���[�g�̐l�ɓ{��ꂻ�������ǁB�i�j�v �@�Ƃ�����������B �@����Ȃɐ[���Ӗ��͂Ȃ������Ǝv�����ǁA�t���[�g�̂j����͌��\�C�ɂ��Ă����݂����B �@�m���ɁA���ꂼ��̊y��ɂ͂��ꂼ��̓�����J���������A�g�ȒP�E����h�Ƃ������t�ŒP���ɕЕt��������̂ł͂Ȃ���ˁB�܁A�Y�����ƌy�������܂��傤�`�B |
| �@�Q�O�O�X�N�R���Q�P���i�y�j�@�P�W�F�S�T�`�Q�O�F�S�T�@�u�C�[�S�������ȁv���u���v �S�y�� �@�@��˓c���u�C�[�S�����v����!? �@�����́u�C�[�S�����v���Ȃ̏����킹�E�E�E���Ă��Ăǂ�Ȋ����ɂȂ�̂��A�h�L�h�L�B �@�`���[�j���O���I����āA����������B �@�E�ŏ��̃t�F���}�[�^�́A�z�����A�`���[�o�A�e�B���p�j�̂݁B�ጷ����͔�яo���Ȃ��悤�ɁI �@�E���̂`�������������͂��Ȃ�������B �@�E�`�������������́A�e���|�ǂ��葬���i��������Q���q����j �@�E�T�W���ߖڂ̌��y��̂S�������̍��݂͂͂�����ƁB �@�E�b�ŏ����e���|�𗎂Ƃ��āi���B�I������A���݂Ńe���|�����ɂ��߂āj �@�E�c�̂S���ߑO����e���|�𑬂߂� �i�g�����{�[������A�e���|�A�b�v��낵���I�j �@�E�c�ł`�������������̃e���|�ɂ��ǂ�B �@�E�P�S�O���ߖڂ̃g�����y�b�g�Ńe���|�����߂�B�P�S�P���ߖڂ̂u���͋}���Ȃ��ŁB �@�E�P�S�Q���ߖڂ���͏����������̃e���|�ŏ���o���B �@�E�d�ɓ���O�ɊԂ����̂ŁA�t���C���O���Ȃ��悤�ɁB �@�E�d����͂P�U�� �@�E�g�̂Q���ߑO����Q�U��i���̌�ɑ����ጷ����A��낵���I�j �@�E�g����؊ǂ̂W�������ْ͋����������� �@�E�R�T�P���ߖڂ���̂P�������@�C�I�����͎キ�Ȃ�Ȃ��悤�ɂ�������ƁB �@�E�R�V�R���ߖڂ���łĂ���R�A���͂͂�����ƁB�i�����������āj �@�E�l�̂P���ߑO��accel. �@�E�l����͂`�������������̃e���|�� �@�E�n�łb�Ɠ����悤�Ƀe���|�𗎂Ƃ��āi���B�I������A��낵���I�j �@�E�n�̌�ɏo�Ă��郁���f�B�[�͑��������̂���P�U�������ŋ}���Ȃ��悤�� �@�E�o�̂V���ߖڂ���e���|�𑬂߂āi�g�����{�[������A��낵���I�j �@�E�S�W�R���ߖڂ̃g�����y�b�g�Ńe���|�����߂�B �@�E�S�W�T���ߖڂ���͂������߂̃e���|�ŏ���o���B �@�E�p�ɂ͂���O�ŊԂ��Ƃ�̂ŁA�t���C���O���Ȃ��悤�ɁB �@�E�p����͂P�U�� �@�E�p����̃`�F���̓A�W�A�̕��͋C��L���ɕ\������悤�� �@�E�q����̖؊ǂ��A�������܂��ɏ�����߂� �@�E�r����Q�U�� �@�E�r����̓����f�B�[�S���̃N�����l�b�g����������悤�ɑ��̊y��͏����� �@�E�T�U�R���߂��班��rit.���ĂT�U�T���ߖڂ���̃����f�B�[�͂����Ղ�� �@�E�s�Ńe���|�A�b�v �@�E�T�W�X���ߖڂ̌��y��͂��ɗ����Ă���N���V�F���h �@�E�t�̂`�������������͂��Ȃ葬�� �@�E�U�P�T���ߖڂ���͂P�U��ł���ɑ��� �@�E�Ō�̏��߂ɓ���O�Ƀe�B���p�j�̃��[���ŏ������o�[�g����̂ŁA �@�@�w�����݂ē�������킹�邱�ƁB�i�t���C���O���Ȃ��I�j �@�ƁA�搶����̎w�E�͂���Ȋ����ł����B�S�҂�ʂ��āA�A�W�A���`�b�N�ȕ��͋C�������Ƃ����ƕ\������悤�ɂƂ���������Ă��܂����B �@���x�݂����l�͊y���ɏ������݂��Ăˁ`�B �@�i���K�ɎQ�������l�́A���K�����˂ă`�F�b�N����B�j �@��˓c�搶�́u�C�[�S�����v���Ȃ́A�e���|�̂����������▭�ŁA�ƂĂ��h���}�e�B�b�N�Ȋ����Ɏd�オ�肻���ł��B���K�����Ă��ă��N���N���Ă����Ⴂ�܂����� �@���̌�A���E�S�y�͂������������킹�܂����B �@���T�́A������x�O�v���̍��킹�����āA���̂P�A�Q�y�͂���邻���ł��B �@�ł́A�܂��`�B |
| �@�Q�O�O�X�N�R���P�S���i�y�j�@�P�W�F�S�T�`�Q�O�F�S�T�@�u���v �S�y�� �@�@�����i�t�H���e�b�V���`�I�I�j �@�R�T�ԂԂ��tutti�́A�S�y�͂���B���K���Ԃ͏[���ɂ������̂ŁA�����͌`�ɂȂ邩�ȁH �@�����炩�Ǝv������A�����Ȃ�X�Q���ߖڂ���X�^�[�g�B �@�L���ȁu����v�̎�肪�`�F���E�R���g���o�X�����B�I���E�`�F�������@�C�I�������NJy��Ə��X�Ɍ��݂𑝂��ă����[����Ă����A�����I�ȕ����ł���B��˓c�搶�́A�I�P�݂̂ʼn��t����邱�̎��̕������ƂĂ���ɍl���Ă���炵���A�J��Ԃ��J��Ԃ����K�B���܂葬���Ȃ��A����ł��Đ�i�ފ����͎��킸�ɁB �@�r���A�t�@�S�b�g�̃I�u���K�[�g�ƃ��B�I���E�`�F���̎�肪���܂����ݍ���Ȃ��Ƃ��낪���������ǁA�t�@�S�b�g�̖��Ƃ�����胔�B�I���E�`�F���̕����S���ځi���ɂW�����������������߁j�����͂����Ƃ��낪�����Ă���Ă����悤�Ɏv�����B�����̑̓����Y���݂̂ʼn��t���Ȃ��悤�A������Ǝ�����c�����Ȃ��牉�t����]�T�𑁂����Ă�悤�ɂȂ�܂��傤�B �@�NJy�킪��������Ƃ���́A�܂����������撣��߂��Ȃ��ŁA�P�V�X���ߖڌ㔼���炆���ɂł���悤�ɔ����Ă����܂��傤�B�i�P�U�S���ߖڂ͖؊NJy���O�ʂɁA�P�V�X���ߖڌ㔼����g�����y�b�g�E�z�������\�ɏo��悤�Ɂj �@�Q�O�Q���ߖڍŌ�̂R�A���͂������e���|���ɂ߂āA���̏��߂ɓ���O�ɏ����҂B�i��э��܂Ȃ��I�j �@�Q�O�W���ߖڂ���O�ŐU��̂ŁA�悭���ē���B �@�Q�R�W���ߖڂ���̃s�`�J�[�g�́A�e���|���L�[�v�i�����Ȃ�Ȃ��悤�Ɂj���A�܂��������ȉ��ɂȂ炸�A�����̂��鉹�ŁB �@�Q�T�V���ߖڂ��猷�y��͏�Ƀ��K�[�g�A�؊NJy��̓��K�[�g�̕����͎v�������背�K�[�g�Ƀ��Y���n�̓����͂����߂ɂ�������ƁB �@�R�P�Q���ߖڂ���̖؊NJy��̃X���[�́A�̂Ɠ��l�ɃX���[���Ƃɋ�銴���ŁB �@�R�R�P���ߖڂ���A�z�����͑�ς��낤���ǂ������ێ����āA�s�b�R���������Ȃ��悤�ɁB�g�����y�b�g�́A�\�ɗ����}�[�`�Ƃ͖��W�ȕ��͋C�ʼnq�����̊����ŁB�Ŋy��́A����肶���ƃN���V�F���h�B �@�T�T�O���ߖڂȂǂ̃z�����E�g�����y�b�g�͑傫�߂ɂ͂�����ƁB �@�U�Q�U���ߖځA�U�R�O���ߖځA�U�R�S���ߖځA�R���ڂɓ���O�ɏ����Ԃ����̂ŁA�K���w�������āI �@�V�R�O���ߖڂ̓�����K���w�������č��킹��B�i�V�Q�X���ߖڂ̂U���ڂ�Timp���j �@�W�T�P���ߖڃA�E�t�^�N�g����e���|�ŁB�������A�܂������������Ă���̂ŁA����܂葬���Ȃ肷���Ȃ��悤�ɁB �@�X�P�U���ߖڂ�Maestoso����U�U��B �@�X�Q�O���ߖ�Prestissimo����Ō�̂ЂƓ���i�H�j�����I�I �@�X�Q�P���ߖځA�X�Q�R���ߖڂ̊NJy��̂W�������A�͂�����ƁB �@�X�Q�T���ߖڂ���N���b�V�F���h�B �@�X�R�Q���ߖځA�Ō�̂����I�I �@�s�S�̂�ʂ��āt�@���Ƃ����̍��������Ɩ��m�Ɂi�����̉��ʂ��܂��܂��`�j �@�Ƃ܂��A������y���Ƀ������邱�Ƃ������ς����ˁI �@����́A�O�v���́u�C�[�S�������ȁv�ƂS�y�́i���悢�擪����H�I�j�����܂��B �@��������A�����炢���Ă����Ăˁ�@ |
| �@�Q�O�O�X�N�Q���V���i�y�j�@�P�W�F�S�T�`�Q�O�F�S�T�@��� �P���R�y�� �@�@���̂s���́g�_�̐��`�h�I�H �@��˓c�搶�ɂ��R��ڂ�tutti�ł��B�c�O�Ȃ���A�����͂e�����S�łȂ̂ł����B(>_<) �@���A�P�y�͂̌㔼�ƂR�y�͂����܂������A�u�e���Ȃ��̂R�y�͂͂��ɂ����Ȃ��E�E�E�v�Ɛ搶�͋���Ă����܂����B �@������ƂĂ������ׂ₩�Ȏw���ŁA�����o������L�����Ȃ��̂ŁA��ۂɎc�����}�G�X�g���̌��t���������s�b�N�A�b�v���Ă����肵�܂��� �@�@���̕Ґ��́A�قƂ�ǂ��S���тŐ��藧���Ă���B�\���X�g�A�����A���y��i�u���Q�p�[�g�A�r�I���A�ጷ�j�A�؊ǁi�e���A�n���A�b���A�e���j�A�g���̑S�Ă��S�p�[�g�B�Ȃ̂ɁA�s���������Q�p�[�g�B�S���т����̑����Ƃ���ƁA�s���Q�{�͐_�̂悤�ȑ��݁B�I�P��tutti�̒��ɂ����Ă��A�˂������ĕ������Ă���悤�Ȃ���Ȋ����ŁB �@�A�b���A�e���A�g���̂Q���������肾�ƁA�I�P������ɒ��������E�E�E�ƌ�����͈̂�˓c�搶�ł͂Ȃ��A���̋����g�J�������h���Ƃ��E�E�E�B�����̂Q�����������ɏd�v�ŁA�܂�����p�[�g�ł��邩�E�E�E������Ă���G�s�\�[�h�ł��B���ɁA�g���̂Q��������́A��ɂP�����Ɋ�肻���悤�Ȋ����ŁA�����f�B�[�p�[�g�����������悤�A�S�n�悢�������n�[���j�[�̋��������߂Ď������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƁB�Ђ��`�A�Ȃ�č��x�ȁI�@���b�V�[����A�K���o���ĂˁI�I�@�N�Ȃ�ł���I�I�I �@�B�R�y�́A�o�����̂P���� �u������́A�����̏o����ł����������F�ʼn��t���邱�ƁB �@�@�����āA�W�R���ߖڂ���͒��������V���̎��Ԃ̎n�܂�B�b���́g�V��h���v�킹��悤�Ȑ[���L���ȉ��F�ŁB�X�U���ߖ�Hr�̃\���œV���̎��Ԃ͏I����������B �@���̂R�y�͂́A�{���ɔ������B�^�N�g�́A���̊y�͂���ԍD���ł��B�E�E�E���I�@�y�F�I�P�̂R�y�͂͂܂��܂����ꂩ��B�i���F�̂��Ƃ����邯�ǁA�c�̐����o���o���őS���A���T���u���ɂȂ��Ă��Ȃ��[�B�܁j �@���ɁA�؊ǃg�b�v����́A�Õ����邮�炢�̋C�����ŗ��K���ĂˁI �@�i�R�y�͂����łȂ��A���̊y�͂ł��؊ǃg�b�v�ɂ�邩�������◍�݂����������ˁH�j �@ �@���āA����Q���Q�P����tutti�͂Q�y�͂ƂR�y�̗͂\�肾���ǁA�؊ǐw�̏o�ȏłR�y�͂͂��Ȃ����Ƃ����邻���ł��B �@���̑O�ɁA�Q���P�S���̕��t�ł��ꂼ�ꂵ�����蕜�K�����Ă����܂��傤�I |
| �@�Q�O�O�X�N�P���Q�S���i�y�j�@�P�W�F�S�T�`�Q�O�F�S�T�@��� �P���S�y�� �@�@���y���������A�y�����E�E�E �@��������˓c�搶�ɂ��tutti�ł��� �@�������o�[�͂X�T���̍����o�ȗ��B�E�E�E���A�NJy��́A�s���Ƃe�����S�ŁB(>_<)�@�e���̂����������x�݂Ȃ̂͒������Ȃ��Ǝv������A���s��a�i�C���t���G���U�I�I�j�ɂ������Ă��܂����Ƃ̂��ƁB��������S��肨�F�肵�Ă���܂��`�B �@�ł́A���K�̗l�q���B �@�����́A�P�y�͂ƂS�y�͂̍��킹�ł��B �@�܂��́A�P�y�́B���߂���Ǝv������A�P�U���ߖڂ��琔���߂����x�����x���J��Ԃ��B�ǂ����A�����͂Ƃ��Ă��厖�ȂƂ��炵���B �@�ȉ��A�搶����̎�Ȏw�E�ł��B �@�E�P�U���ߖڃA�E�t�^�N�g�i�P�U�������j�̃��͋Ȃɏ��߂ďo�Ă���剹�Ƃ��āA�g�����h���āA���j�]���ŋC���������Ēe���i�����j���ƁB�i�ł��A�Ȃ����A�g���̂R�������S���������́A���j�]���ł͂Ȃ��A�������̘A���H�j �@�E�P�X���ߖڂ̃��܂ł̉��~���`��cresc.�������ŁA�����āA�Ō�̎剹�͏\���ɖ炵�āA�g��ԕ|���`���h�i�I�j�ʼn��t�B �@�E�P�X���ߖځA�^�C�̌�̃t�@�~���̓t�@�̉����狭���A���̏��߂̃��\�~���܂őO�����ɁI�i�x��Ȃ��I�I�j �@�E�Q�P���ߖڂ��疈���߂��邆�͉��ʂ̈Ӗ��ł͂Ȃ��A�����E�A�N�Z���g�̈Ӗ��ŁA�����f�B�͏����i�s���ď�s���Ă���̂������āB �@�E�V�S���ߖڂ���̂��͂�����dolce�B���Ƃ��̍��������Ƃ��āB �@�@�i�����̕����̊NJy���tutti�ł͂Ȃ��̂ŁA�̂������Ƃ����ӎ��A�����̉��F�⎩���Ȃ��dolce�����������Đ������ƁB���ۂɉ̂��Ă݂�̂��厖�B�j �@�E�X�T���ߖڂ̂����̂W�������͒Z�� �@�E�P�O�Q�A�P�O�R���ߖڂ̃��Y���͂����Ƃ����ŁI�i���������ވׂɁA�݂�ȉ̂킳��Ă܂����B�j �@�E�P�O�W���ߖڂ���̂���dolce�ł����Ƃ������āB�i�P���� �u���͉�������������I�j �@�@dolce�ɂ�dolce=���َq�Ƃ����Ӗ��ɂ����āA�����̓��`�̂悤�ɗ͋����A���̓A���̂悤�ɊÂ��B �@�E�P�Q�O���ߖڂ���́A1st Vn�Ƃe���ɑ��āA2nd Vn�Ƃb�������������ɂȂ��Ă���̂ŁA�Q���߂��P�t���[�Y�ɕ�������悤�ɂȂ��āB�P�Q�S���ߖڂ���͂��݂��ɏ�������cresc.�������悤�ɁB �@�E�P�T�S���ߖڂ���̂����͏d�X���������B�i���y��͑S�|�Łj �@�E�P�T�X���ߖڃA�E�t�^�N�g�̂P�U�������Ƃ��̌�̂S�������̃V��͂܂����B�S�������͒����B �@�@�i�u���͂��̂S���������_�E���Œe���������Ƃ��납�玟�̂P�U��������e���悤�Ɂj �@�E�P�V�X���ߖڃA�E�t�^�N�g�̂e���̃����f�B�͑傫�߂ɁB�ȍ~�̖؊ǂ̃����f�B�͂Ƃ��Ă��厖�I �@ �@�ƂP�y�͂͂��̂�����ŃX�g�b�v�B������������Ƃ̂����炢�����˂āA�Q��قǂ����܂ł����킹�B �@ �@���ɁA���҂����˃g�����{�[������̓o�ꂷ��S�y�͂̍��킹�B �@�s���̂��߂Ƃ������Ƃłl�̂Q���ߑO����B�i���̕����A�݂�Ȃ���Ăɉ��t���钆�A�Ȃ����b���������x�݁H�j �@�E�l�͊�т̕����B�̎������ŏI��錾�t�͎q�����L�т銴���ɂȂ�̂ŁA���t�ɍ��킹�Đ����悤�ɁB �@�E�U�O�R���ߖڂ���̂s���͉����ɃE�G�C�g�����o���āA�F����\�킵�Ă���悤�ɁB �@�E�m����̂s���A�u���A�b���͂����Ɨ͊��������āB �@��˓c�搶�́A�s�������o�[�̂��Ƃ��l���āA�s���̏d�v�ӏ��Ƀ|�C���g��u���Ă�낤�Ƃ��Ă��ꂽ�̂ł����A�����o�[�̕����܂��܂����K�s���Ő搶�̗v�]�ɉ�������悤�ȉ��t���ł����A�r������s���͕ʎ��Ōʗ��K�Btutti�͂P�y�͂ɖ߂�܂����B �@�i�搶�̊��҂ɉ������Ȃ������s���̃����o�[����A���̋@��Ƀ��x���W�ł���悤�A��������l���K���Ă����ĂˁI�j �@ �@�Ӂ[���A�搶����̎w�E�͂����Ƌ����Ă��A����ȂɂȂ�܂��I�@�����ɓ��e�̔Z�����K�ł��邩�͂�������ɂȂ�ł��傤�E�E�E�B����ȍ~�A����Ȃɏڍׂɂ͏����Ȃ���������Ȃ��̂ŁA���ꂼ��ł������胁�����Ƃ��Ăˁ[�B �@�y�}�G�X�g����˓c�k�@�x�[�g�[���F���̉��y�Ƃ́H�I�z�@ �@tutti�̓r���ŁA��˓c�搶����x�[�g�[���F���ɂ��Ă���Ȃ��b������܂����B �@��ȉƂƂ��Ă��s�A�j�X�g�Ƃ��Ă��łɖ��������Ă����x�[�g�[���F���́A�\���ȏ���������A���x�����z�����ł���قǗT���������B���������T���ȃx�[�g�[���F���̉��́A�����đ��������ł͂Ȃ��A���݂̂���grandioso�łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��I �@����́A�P�y�͂̌㔼�ƂR�y�͂̍��킹����邻���ł��B�搶�́A�P�y�͂̓x�[�g�[���F���̍�i���V�ԓ��l�A�ƂĂ��[�����Ă���̂ł�������݂Ă��������Ƃ̂��ƁB �@�i�S�y�͍͂����������Ă��܂��A���Ƃ͐����݂����ȁE�E�E�B��j �@�ł͂ł́A���ꂼ�ꎟ���tutti�܂łɂ������肨���炢���Ă����܂��傤�� �@ |
| �@�Q�O�O�X�N�P���P�V���i�y�j�@�P�W�F�S�T�`�Q�O�F�S�T�@��� �P���Q�y�� �@�@  �V�����搶�A��������̐V�����o�[�ƂƂ��ɁA�V���Ȉ���� �V�����搶�A��������̐V�����o�[�ƂƂ��ɁA�V���Ȉ�����@�x����Ȃ���A�݂Ȃ���A�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��� �@�{�N���A�s���s�y�F����A���̃^�N�g����̃I�P�����L����낵���I �@���āA���N�̉Ă̊y�F����́A�v�X�Ƀx�[�g�[���F���́u���v�ɒ���ł��B �@���m���R���g���o�X�t�҂̈�˓c�搶���w���҂ɂ��}�����A�s���s�����A���Ƃ̃^�C�A�b�v�Ƃ������Ȃ�͂̂��������R���T�[�g�ł��B �@��������N�����番�t���K���n�܂��Ă���A�������҂��ɑ҂����g��tutti�h�ł����B �@�ŁA���K���ɓ����ăr�b�N���I�I �@�u���̃����o�[�������Ȃ�{�����Ă���܂����B �@�u���v�l�C���Ă���ς荂����ł��ˁB �@�ƌ����Ă��A�قƂ�ǂ��R���E�~�X�̂���q����B���������Ȃ�Ⴂ�B��C�Ɋy�F����̕��ϔN��O�O�b�Ǝ�Ԃ�܂����B(^_^;) �@���K���������ꂪ���������邭�炢�l��������̂͂����ł��ˁB�݂�Ȃ̃��`�x�[�V�������オ���Ă���悤�ł����B �@���K�̗l�q�͂Ƃ����ƁE�E�E �@�u�������o�[���A�u�����ƒe���āI�@�����ア�I�I�@�����Ɨ͋����I�I�v��A�Ă���Ă܂����B���������A�g�c�搶������������Ƃ������Ă��Ȃ��Ɖ��������v���o���܂����B �@�NJy��i���ɖ؊ǁj�́A�����Ȃ��l�Ő������ꂽ��A�A�A�ْ��������Ղ�B �@�����̗��K�ŁA���ꂼ�ꎩ���̉ۑ肪��������i�荞�߂���Ȃ����ȁH �@���āA������˓c�搶����������������łƂĂ���ۓI���������t���s�b�N�A�b�v�B �@���̂P�@�x�[�g�[���F���̉��y�͔������I �@���̂Q�@Vivace�͑������������APresto�͐��ւ̈Ӗ����܂�ł��邱�Ƃ��ӎ����āB �@�Ƃ�����ŁA�Q�y�͂�Presto�݂͂�Ȃ̑z���������Ȃ�̃n�C�X�s�[�h�B�B�B������ׂ��I �@�����ӂ����������ɂȂ�Ȃ��悤�A���ꂼ�ꂵ������l���K���Ă����ĂˁB�i�n������A�\����ς����ǁA�K���o���[�I�j �@����́A�P�y�͂������������Ă���A�S�y�͂���ʂ荇�킹�邻���ł��B�`�F���E�o�X����A�S�y�̖͂`���A�Õ��Œe���邮�炢������Ă��悤�ˁ`�B �@�ł́A����B(^o^)�� |
�@![]() �i�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�j �@�@�@�@
�i�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�j �@�@�@�@![]() �ߋ��̓��L�������@�@
�ߋ��̓��L�������@�@![]() �ŐV�̓��L�������@�@
�ŐV�̓��L�������@�@