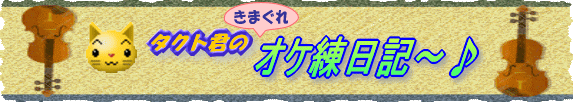
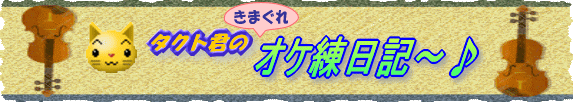
2014年12月14日(日)  第37回市民コンサート本番!! 第37回市民コンサート本番!!終わりました〜、2時間超えの長丁場! 前日のリハでは、指揮がよく分からず(!)、たびたび崩壊するシーンが見られ、だ、大丈夫なのか?!とかなり不安を抱えたまま、練習時間が終わってしまいました。当日朝の練習は、通す時間はないので、ソリストさんのアリア、レチタティーヴォを合わせるのみ。 さあ、どうなることか・・・。 開演前に、恒例となりつつある、弦楽器によるウェルカム・コンサート。今年は、コンミスさんアレンジの「ロンドンデリー・エアー」と今年大流行だったあの曲。(曲名は内緒。) 団員と将来団員として有望なジュニアヴァイオリニスト達による演奏は、なかなかいい感じ。  この波に乗って、本プロの演奏も上々といけばいいんだけど。 そして、いよいよ始まった! 出だしは心地よい緊張感に包まれて、エリア登場。そして、序曲へ。早速、やや危うげな所が!! しかし、それ以上崩れることはなく、無事に次の曲へ。 その後も特にレチタティーヴォでヒヤヒヤする箇所があったものの、ソリストさんが全く動揺することなく、きっちり歌ってくれたので、事なきを得ました。第1部、第2部、それぞれが1時間を超える大曲で、お客様の反応がとっても心配でしたが、メンデルスゾーンの作曲力はすごかった!!! 多彩なメロディーで時間の長さを感じさせることなく、「初めて聞いたけど、素敵な曲だった」という声があちこちから聞かれた。 本当にどれもこれも印象的な曲満載のオラトリオでした。こんな曲を演奏できたなんて、みんな幸せだよ♪ もっと自分の幸運を噛みしめて、これからもしっかり練習に励んで下さいね。  そんな訳で、今年の本番も無事終了しました。みなさん、お疲れ様でした。 さて、次は、「くるみ割り人形」&「田園」です。気持ちも新たに頑張りましょう♪ 【打ち上げで】 今回のソリストさんは、若い方ばかりでしたが、4人ともとても楽しい方で、打ち上げのコメントが面白過ぎでした。 ぜひまた市原に来ていただきたいですね。 |
| 2014年12月6日(土)〜7日(日) エリア全曲、合唱合わせ 思い出して!! アマオケ三大原則!!! 今年もいよいよ本番間近となりました。 みなさん、それぞれ仕上がり具合はいかがですか? まだまだ練習が足りないと感じている人も多いのでは・・・。 土曜日はオケのみの最後の練習、日曜午前は弦分奏、午後は合唱合わせと、特に弦楽器のみなさんはオケ漬けの週末でしたね。 Y先生からは相変わらず、「音が軽くならないように。地面にしっかり根を生やす感じで。」と随所で言われました。 何か、今回は1週間前でもいつもよりお休みの人が多いような。 練習のモチベーションも下がり気味になっている印象です。 特にまずいと思うのは、お休みがちな人が迷子になっていることです。曲が長大ではあるけど、自分の出る箇所、役割は把握して練習に参加しましょう。 仕事、家の都合などそれぞれ事情はあると思いますが、毎回きちんと練習に参加し、頑張っている人もいます。そういうメンバーの足を引っ張るようなことはいけませんよね。音は出せなくても、音源を聞きながら楽譜を見るのも十分よい練習になります。各自がもう少しオケのために時間を割いてほしいなぁと思う今日この頃のタクトです。 今こそ、もう一度、アマオケ三大原則を思い出しましょう! 1.極力練習に参加する。 2.個人練習をする。 3.オケを人任せにしない。 メンデルスゾーンの「エリア」はほとんどの人にとって演奏するのは、今回が最初で最後だと思います。本番まで残り時間は少なくなりましたが、それぞれ更なる努力を!! |
| 2014年11月1日(土) 18:30〜21:00 エリア第1部 Nr.1〜10 おかえり〜♪ 前回のオケ練日記の影響ではないと思うけど、今日の弦団員の出席率は90%近かった。最初からこのぐらい揃っていると嬉しいんだけどな。 そして、とっても嬉しいことにクラリネットのSさんが久々の復帰です! 今年4児のママとなり、楽器から少し離れていたりしたようですが、腕前は全く衰えていません!! これからの木管のハーモニーが楽しみです♪ さて、練習の方はというと、今日もやはり、「音が浮かないように。地面にドシッと!」のお言葉が何度も聞かれました。 音の立ち上がりが弱くならないように気を付けるといいかもね。 とにかく曲数が多いので、曲の雰囲気、テンポをつかむのが大変。合唱合わせでどうなるか・・・。 それぞれ、空き時間にしっかり曲を聞いて頭に入れましょう。 次回は、今回の続き・・・第1部Nr.11からやります。 じゃあ、みんな、頑張って〜。 |
| 2014年10月18日(土)、19日(日) Vnメンバーのみなさん!! 大変お久しぶりなタクトです。エリアの練習の進行状況が気になる中、土曜日は合奏練習、日曜日の午後は弦練習という練習強化週間でした。 が、、、Vnメンバーってこんなに少なかったっけ?? エリアは、長い、超長ーい。そして、弦楽器は、“アルペッジョ! しかも高速で!! 時にはトレモロで!!!”という難所がかなりあり、くじけてしまったメンバーがいるのか。心配で眠れない日々を送るタクトです。 弦、特にVnメンバーのみなさん、おそらく二度と弾くことはない曲ですから、勇気?を持って練習に参加しましょう。みんなで弾けば怖くない?! という冗談(半分は本気)はさておき、本当にここのところ弦とそしてクラリネットさんの出席率が低迷しており、そろそろやばい空気が。さすがのY先生も焦りだした様子です。前日のゲネが長時間とならないためにも、今からしっかりみんなで揃って練習しましょう。 さて、練習の内容はというと、相変わらず言われてることは、「音が後から膨れてこないで! 出だしからはっきりと。地面に向かって!! 音が浮かないように。」です。これ以外の言葉、、、あんまり聞いてないかも。 でも、確かにどれも大事なことではあるけど。一人一人がしっかり音を出していれば、それなりに迫力のある演奏にはなるかと。あとはやっぱり音程だよね。 音程については、管楽器の方がもっと注意が必要だね。ハーモニーとして聞こえてこないと、ソリストさんも合唱さんも歌えないよ。 音量を増すためにも、音程により気を配るようにしましょう。管楽器は、弦楽器のような超絶アルペッジョはないんだから。(^^;) 残り1か月とちょっと、みんな、頑張れ―! |
| 2014年9月6日(土) 18:30〜21:00 エリア第2部 Nr.41〜42、第1部 序曲〜Nr.10 新練習記号リスト、公開中★★ 今日は、体調不良でお休みしていたコンミスさんも復帰し、久々に弦楽器が揃いました。 管楽器もほぼ揃っているということで、41番から練習スタート。サラサラ進むと思いきや、Y先生はどうしても管楽器の吹き方が気に入らないらしく、何度も何度もやり直し。今日はどこまでやれるんだか・・・ちょっとため息。 その後も管楽器がやたらと捕まりましたが、10番までは合せました。次回は20番までいけるかな? 今回もおっしゃっていましたが、やはりスラーはつけない方がいいようです。(特に管楽器) スラーは思い切って消しましょう! それから、Nr.5の79小節目のフェルマータはなしです。×をつけておきましょう。 さて、ようやくヴォーカルスコアに合わせた「新練習記号リスト」ができたようです。 こちら↓にありますから、みなさんしっかり書き込みをお願いします。○で囲むとか、色をつけるなどして、すぐに見つけられる工夫もしてね。 ♪エリア 新練習記号一覧♪ では、また〜。 |
| 2014年8月16日(土) 18:30〜21:00 エリア第1部 Nr.12〜第2部 Nr.23 スラーは不要?! お盆休み期間のせいか、今日は集まりがイマイチ・・・。ヴァイオリンはコンミスさんに2ndのトップりえちゃんもお休みで、かなり心細い状況となっておりました。対照的にチェロチームはとても積極的で、難しいパッセージにも果敢にチャレンジ! ヴァイオリンのみなさんも難しい部分が多くて大変だと思いますが、トップ陣にお任せではなく、一人一人が計画的に弾ける部分を増やしていくように頑張ってほしいです。こればっかりは本人次第なので。とにかく時間をかけて練習するしかないんですよね。社会人には厳しいことですが。 さて、練習内容はというと・・・ ゆっくりな曲はともかくとして、ある程度テンポがある曲は、四分音符、二分音符ははっきり区切って、決してつなげて演奏しないようにと言われました。 例えば、Nr.13の14小節目からの付点四分音符は一つ一つを「トゥーン、トゥーン」と響きを残しつつ、はっきりとだそうです。次の音につながってはいけないとも。 さらに、その後に出てくる木管のスラーはいらないみたいです。「レガートでもトゥン、トゥンと音の動きをはっきり」とY先生がおっしゃっておりました。 ってことは、、、スラーではなく、メゾスタカートでやればいいのか?(ポルタートとも言う?) 声楽と器楽の奏法の違いなのか?? もちろん、Nr.14のようなゆっくりのアリアはスラーでOKのようです。 Nr.15の6小節目、10小節目のフェルマータは歌詞がつながっているので、なしだそうです。 Nr.22の最後の方、111小節目から始まる2分音符は111〜113小節目1拍目までで1フレーズ、113小節目2拍目〜115小節目1拍目までで1フレーズ、115小節目2拍目〜最後までが1フレーズと歌詞に区切りがあるので、オケもそのように区切って演奏すること。 (全部の2分音符をダラダラとつなげてはいけない。) 次回は、Nr.24から最後までやる予定だけど、今のペースだと終曲までたどり着けないかもなぁ。 みんな! あんまりY先生に突っ込まれないように、音の出だしははっきりくっきり、いえ、出だしだけでなく、動く音は常にくっきりはっきりと、決して後膨れしないで弾ける(吹ける)ように練習してきて下さい。 |
| 2014年8月2日(土) 18:30〜21:00 エリア第1部 序奏〜Nr.11 ★練習記号が変更になります! いよいよ「エリア」の合奏開始です! 長い曲だけに、どこまで合せられるか・・・8月の練習で一通り通す予定なので、細かいことはさておいて進んでいくと思いきや、Y先生は音の出し方、音色などこだわるこだわる。結局、予定の半分しか進まず、今日の練習は終了。 残り31曲!! 8月に全部通せるか?! さて、ちょっと困ったことに、練習記号を合唱さんたちが使用しているボーカル譜に合わせることになりました。とりあえず、今日判明した練習記号は下記の通りです。 【序曲】 A・・・23小節目 B・・・32小節目 C・・・42小節目 D・・・57小節目 E・・・67小節目 【Nr.4】 A・・・20小節目 B・・・37小節目 【Nr.5】 A・・・15小節目 B・・・29小節目 C・・・43小節目 D・・・52小節目 E・・・89小節目 【Nr.8】 A・・・25小節目 B・・・46小節目 C・・・99小節目 D・・・113小節目 E・・・123小節目 【Nr.11】 A・・・12小節目 B・・・24小節目 C・・・60小節目 D・・・76小節目 E・・・96小節目 F・・・112小節目 G・・・124小節目 おそらく、この間の曲にも練習記号の変更はあると思います。 全部がはっきりしたら、リストにしますが、練習時は耳をダンボにして(古い!)、各自で楽譜に記入をお願いします。 ※大切なお知らせ 前回お知らせした「小節番号リスト」に一カ所誤りがありました。 Nr.11のCは106ではなく「104」です。大変失礼いたしました。 訂正したリストを添付しておきます。 次回は、8月16日です。今日の続きからやります。 |
| 2014年7月22日(火) 吉田先生のシーズンが終わり、なんとなく寂しい感じがありますが、センチメンタルになってはいられません! 今年の12月は、今までにない長大な曲に挑戦ですから。 という訳で、練習が円滑に進むように、あらかじめ各自で小節番号を振っておきましょう♪ 振り間違えがないように下記を参考にして下さいね。 メンデルスゾーン オラトリオ「エリア」の小節番号一覧はこちら! とりあえず、夏休みの宿題ってことで、よろしく!! |
2014年7月6日(日) 第36回市民コンサート、本番! 第36回市民コンサート、本番!今回もいろんなことがありつつ、本番を迎えました! 前日夜のリハーサル、そして午前中の最終リハーサル、吉田マエストロは直前まで諦めることなく?!、さまざまな要求を出されます。 中には、要求だけして「後は本番でよろしく〜♪」みたいなこともあり、大丈夫なのかぁ?と慎重派のタクトとしてはかなり心配でしたが、本番はまずまずの出来栄えでした。 ただ、弦楽器はもっとpとfのメリハリがほしかったし、管楽器は音程がね・・・。 相変わらず問題は山積みなのですが、前回よりは今回、そして今回よりは次回と一歩一歩確実にステップアップできるように、各自でしっかり反省をして、これからも頑張りましょう。 今回は、前半がリストの「レ・プレリュード」、後半がシューマンの「交響曲第3番”ライン”」というちょっと短めのコンサートでした。「レ・プレ」が終わってすぐ、会場から割れんばかりの拍手をいただきながら、吉田マエストロ一旦退場。次に、各楽器のソロ奏者を紹介すべく、ステージ上へ出ようとしたら、あらら・・・拍手が止んじゃった・・・シーンとした中、出ていくこと訳にもいかず、もやもやとした気分で前半戦終了。 シューマン演奏後は、拍手も長く続き、奏者紹介、花束贈呈、アンコールと無事につながりました。(笑) 今回は楽章ごとの拍手はなかったので、まあよかったのですが、「リストでソロをやった人には申し訳なかったなぁ。市原の聴衆をみんなでもっと教育しておいて!」と打ち上げでマエストロが笑いながらおっしゃっていました。(汗) そうそう、今回のアンコールは、先生の発案で、メモリアル・イヤーであるリヒャルト・シュトラウスの歌劇「カプリッチョ」より月光の音楽を演奏しました。アイちゃんのホルンソロがとーっても美しかった♪ これを聞けたお客様はかなりラッキーだったかも!! 子育て期に入った団員も多く、集まりがイマイチの日も多く、どうなることやらと心配していた本番でしたが、熱意ある若手新入団員が3名も加わり、大きな推進力となって、よい演奏会となりました。 みなさん、本当にお疲れ様でした。そして、新入りのケースケくん、ミクさん、ナオヤくん、これからも末永〜くよろしくお願いいたします! 【打ち上げで・・・「ライン」クイズ!】 前日のリハで、「ラインは3、4、5楽章はアタッカで続けていくから、そのつもりで準備しておくように」とマエストロがおっしゃった。 4と5は、曲想からいってもつなげてやった方がいいかなぁと漠然と思っていたけど、3と4も?? そして、打ち上げでマエストロから「今回3楽章以降をつなげてやったのには、深い音楽的な理由があったんだけど、わかる人はいるかな?」というクイズが出されました。Vnトレーナーのるね先生から「目から鱗の話。」というヒントも出され、かなりいい線まで近づいたのだけど、結局謎を解ける人はいませんでした。マエストロから明かされた回答はいかにシューマンが作曲家として優れていたか、あらためて思い知る内容でした。 答えを知りたい!というそこのアナタ! ぜひ市原市楽友協会オーケストラへ!! 土曜日の夜に八幡宿でお待ちしております!!!(笑) |
| 2014年6月30日(日) 全曲 市原市青少年会館 今年もいよいよ本番です!! 合宿を終えて、本番がすぐそこに見えてきました。さすがに、この時期になると出席率は高く、練習会場がギュウギュウしてきます。 特に土曜日は音楽室でしか音が出せないので、もう熱気ムンムン。日曜日は集会室が使えますが、こちらは空調がオンオフしかなく、つけると冷え過ぎ、止めると蒸し暑く、、、なかなか厳しい状況です。 さてさて、そんな中、練習の方はというと・・・もちろん本格化してきている訳ですが、う〜ん、あと一ケ月早くこういう練習ができていたらなぁと思ってしまうタクトです。 吉田先生は曲を通しで練習するより、その曲の構成を理解した上で演奏できるようにと、部分部分をつまんで指導されます。 みんなが確実にそれを体にしみこませるくらいになったらいいんだけど、1週間空くと忘れてしまうことも結構あって、ふりだしに戻っていることもしばしば。 なかなか吉田先生の思うような音にはなっていないようです。(>_<) まだまだ完成形には遠いようですが、本番は待ってくれません。 この1週間、各自でできる限りの練習をして、本番でよりよい演奏ができるように頑張りましょう! |
| 2014年6月7日(土)〜6月8日(日) 合宿(岩井海岸 いとうRYOにて) 今年も岩井海岸での合宿を迎えました。せっかくの海辺なのに、雨〜。前日に梅雨入りしちゃいましたね。ちょっと残念?! 管楽器はほぼフルメンバーが参加でしたが、弦楽器は・・・もともと少ないのに、結構お休みの人が。吉田先生はかなりガッカリされていたよう。 でも、2日目の朝からぞくぞくと参加メンバーが増え、tuttiの半分は弦練習という感じでした。 まあ、これだけじっくりやったのだから、次回からはさらに進んだ練習ができるでしょう。(そのために、各自でしっかり復習しておいてね!!) 吉田先生からはそれはもう細かい細かい指示があり、全部はとても書ききれないので、詳細はパートごとに確認をして下さい。(エキストラさんへの申し送りもこぴっとね。←朝ドラ見てる人は分かるはず。笑) とりあえず、全体に関することをかいつまんでお知らせします。 【リスト/レ・プレリュード】 ・NとPは2拍子で軽快な感じ ・Oの3小節目にTempo di marciaが抜けていたら書く。ここからしばらく4拍子で歯切れよく ・378小節目・・・Piu maestoso どっしりとした感じ ・Pの2小節目(Vivace)で再び2拍子系 ・403小節目のpoco ritard.はあまりやらない ・405小節目・・・Andante maestoso ・終わり4小節の弦楽器の装飾音は前に出す(本来の音をオン・ザ・ビートで) 【ライン1楽章】 ・17小節目でデクレシェンドしたら、18小節目からはクレシェンドしながらリズミカルに(73小節目〜と427小節目〜も同じ) ・Cの1小節前のトランペットの16分音符をちゃんと聞いてCに。(フライングしないように)472〜473小節目も同じ ・121小節目からは2分音符、4分音符ともテヌートでそれまでとはガラッと変えてやわらかい雰囲気で。(483小節目からも同じ) ・215小節目はpに落としてからゆっくりクレシェンド。本格的なクレシェンドは225小節目から ・264小節目でデクレシェンドして265小節目はppからクレシェンド ・299小節目からの3拍目の4分音符はアクセントのあるなしをはっきり分けて弾く (307小節目〜、333小節目〜も同じ) ・538小節のクレシェンドはpの中で。(あまり大きくし過ぎない。) 【ライン2楽章】 ・冒頭の低弦、ファゴットのメロディはスラー単位で、二人の人が会話しているように弾く。 ・9小節目からのメロディは2小節単位のフレーズで ・25小節目からの16分音符は出だし1拍はやや大きめに吹いてだんだん消えていく感じで弾く ・41小節目からはコントラバスの16分音符の動きに乗って弾く。(そこからはみ出ないように) ・Eに入る前は少しルバートするので、必ず指揮を見て合わせること。 【ライン3楽章】 ・5小節目〜sehr getragen=sos tenuto(音は切るが、なるべく滑らかに弾くように) ・15小節目3拍目で一旦終止。4拍目からは新しく始める。 ・23小節目の3拍目で一旦終止するので、3拍目は強くならないように 【ライン4楽章】 ・全体を通して、教会で祈りを捧げるような厳かな雰囲気を持って弾く ・26小節目から8分音符4コの音型が出てきたら、突出するように大きめにはっきり弾く。 ・33小節目からsfははっきりわかるように弾く ・43小節目1拍目のsfは他のパートと揃える気持ちで ・Dからの管楽器のファンファーレは音の立ち上がりをくっきりさせる。他の楽器と音が溶け合うように意識して。 ・Eの3拍目〜1拍目はデクレシェンドする 【ライン5楽章】 ・頭のアウフタクトは長めに存在感を出して ・17小節目から46小節目3拍目までは基本pで軽快に。fが出てきてもすぐpにする。(Gからも同じ) ・69小節目の付点2分音符はたっぷりした音でその後も少しテンポを緩める。(214小節目からも同じ) ・71小節目4拍目の前でカンマ。指揮を見て合わせる。(フライングしない) ・94小節目最後の8分音符ははっきりと。(その後も同じ) ・Cの2小節目からの8分音符の動きは動き出しをはっきりと。 ・128小節目からはクレシェンドを忘れない ・151小節目4拍目からテンポを少し緩めて。Gでa tempo ・239小節目からの8分音符ははっきりと。(埋もれないように) ・Lの2小節目から少しaccel. ただし、2分音符は4分音符2個が詰まっている感じを失くさないように ・287小節目でsubito pでクレシェンドしながらaccelして299のテンポへ リストもシューマンも印象的な演奏(もちろんいい意味で!)ができるように、みなさん、頑張りましょう!! 【合宿の夜の楽しみ?】 今年も平ポンさんの見事な三味線から余興がスタート。 その後のVn&Cbアンサンブルはかなり危うげ・・・で、お手本をよろしく〜というみんなのラブコール?!に応えて、吉田先生がVnを。「老眼で細かい音符が見にくいー。」と言いつつ、初見でさすがの演奏を披露。はい、みなさん、脱帽!! そして、ラストはゲーム大会。お絵かき、楽しかったですね☆ さらに、その後も先生を囲んでの団欒?は続き、、、朝まで続いていたそうな・・・。キャ〜〜〜〜!! |
| 2014年3月15日(土)〜4月5日(土) リスト、シューマン1,4,5 や、やばい!! うかうかしてたら、2回もtuttiが終わっていた〜。 という訳で早速、先生からの貴重なご指摘を。 【リスト/レ・プレリュード】 ・35小節目から常に先へ先へと前進する感じで弾く。 ・36小節目の管楽器、付点四分音符+四分音符は音をしっかり持続して。そのあとのリズムは正確に合わせる。(以降も同じ) ・Bから小節の頭の四分音符は長さをきちんと保つ。 ・93小節目からのVnはトレモロでよい ・96小節目のVnは少し大きめに入る ・119小節目からの弦はトレモロでよいが、Eからは正確に。 【シューマン/第1楽章】 ・4分音符、8分音符を正確に。(アバウトにやるとぐちゃぐちゃになります。) ・8分音符はスタカート気味に。 ・159小節目のsfははっきりと。 ・206小節目から213小節目まではpを持続 ・213小節目はpで、231小節目のfまで長い長いcrescがあるので、計画的に音量を上げていく。(すぐに大きくならない) ・275小節目、sf!! ・321小節目、sf!! ・561小節目次の小節のsfzに向かってcresc. ・572小節目、574小節目のsfははっきり。 【シューマン/第4楽章】 ・Es moll(変ホ短調)は非現実かつ哲学的な色合いが強い調だということを頭に入れておきましょう。 ・頭のsfzは大きく。次の低弦のppは少し大きめに。 ・7小節目はデクレシェンドをしっかりつける ・8小節目のObはテーマなので大きく。 ・8小節目3拍目、4拍目はpppくらいのつもりで。 ・12小節目3拍目からの動きは固めに。 ・13小節目からは21小節目のfに向かってじわじわとクレッシェンド ・13小節目のVn,Fl,Hrはお互いの音がブレンドするように意識して。 ・26小節目、28小節目、30小節目3拍目からの8分音符は突出して強く ・33小節目からはsfをはっきりとつける ・43小節目のsfは全員で揃える。 ・45小節目からはできるだけレガート ・Dの前で少しテンポが緩むので、フライングしてDに入ったりしないよう、ちゃんと指揮を見て。 ・Eの1小節目から2小節目はつながりを大切に ・61小節目3拍目からのCl,Fg,Vaのテーマをみんな聞くように。 【シューマン/第5楽章】 ・頭の4分音符はテヌート、2分音符2個は常に大事に弾く ・17小節目アウフタクトから軽い雰囲気に変化、4分音符は短めに。fが出てきてもすぐpに戻って。 ・150小節目で少しテンポを落とし、Gで元の速さにもどる ・171〜172小節目にかけてデクレシェンド ・253〜254小節目でrit ・268小節目の8分音符→4分音符のリズムは正確に合わせて。 ・279小節目の最後の8分音符の前でカンマを入れて、次の8分音符は揃えて ・321小節目、クレシェンド とりあえずこんな感じだったかな・・・だいぶ日が経ってしまったので、記憶が〜〜〜。 ちなみに練習出席状況は、、、Vnさんがちょっと少なめなので、特に2ndのところは音抜けが! みなさん、そろそろ動き出して下さい!! |
| 2014年3月1日(土) 18:30〜20:45 ライン3、5、4楽章 3楽章は、夢うつつで。 今日は、ラインの3、5楽章の合わせです。 でも、、、弦の欠席者が目立つなぁ。コンミスさんまでもがお休みとは! 大丈夫か? などという心配をよそに練習が始まりました。 3楽章はゆっくりゆったりのテンポ。 吉田マエストロから「夢の中みたいに、ほわっとした感じで、優しさと幸福感に包まれている雰囲気で。絶対に音をとがらせないで!」と指示がありました。3楽章全体を通して、柔らかい感じになるように音を出しましょう。 5楽章は・・・どのくらいの速さでやるのか、団員内に緊張がはしっておりましたが、意外や意外、思っていたよりゆっくりめのテンポで、みんなホッとしているようでした。 中には、「本番もこのくらいなんですね?」と念を押す団員もいました。((笑)) ゆっくりめでも、重たくならずに先へ先へ、軽やかに演奏するようにとのことでした。 主な指摘は下記の通りです。 【第3楽章】 ・冒頭のメロディー、16分音符の音価を正しく。(短くなり過ぎないように。) ・メゾスタカート(スラーとスタカートが同時に付いている)は、音を長めにして柔らかく弾く。 ・9小節目4拍目からの16分音符もメゾスタカートで。 ・17小節目の3拍目で一度終止して、4拍目からは新たに始める感じで。 (35小節目も同じ) ・37小節目のVn1の付点2分音符はクレシェンドで。 ・短いクレシェンド・デクレシェンドが付いている音は、その音を十分に歌うつもりで。 (その音にニュアンスがほしいという作曲者からのメッセージです。) 【第5楽章】 ・冒頭の2分音符は、4分音符がちゃんと2個詰まっているように実のある音で。 ・3小節目のアクセントは、強く発音するのではなく、重みがある感じ ・16小節目4拍目から、ガラッと雰囲気を変えて。ここからの4分音符は短めに。 (後半も同じ) ・25小節目4拍目で少しrit.して、26小節目4拍目からまたガラッと雰囲気を変えて。 ・30小節目、31小節目のFl,Vn1の16分音符は正確に ・68小節目3拍目の2分音符はテヌート。(213小節目も同じ) ・150小節目で少しゆっくり ・162小節目でテンポを元にもどす ・233小節目からの4分音符はスタカートで ・253〜254小節目でrit. ・259小節目3拍目の2分音符はテヌート ・267小節目の最後の8分音符は正確に揃えて。 ・279小節目の複付点2分音符はデクレシェンドして、次の8分音符に入る前にカンマを入れる。 ・287小節目でsutibo p(すぐに小さく)か294小節目まで長いクレシェンドをする ・290小節目あたりからaccelして299小節目Schnellerのテンポに持っていく ・314小節目の最後の8分音符でpに落とす。その後各パートsfzの前の小節でそれぞれクレシェンドする ・321小節目、木管とVn2はクレシェンド ・322小節目、金管、Vn1、Va、Vc、Cbはクレシェンド とここまで、割りとサクサク練習が進み、ちょっと時間が残ったので、4楽章も合わせました。 来週は、貴重なミーティング。 次のtuttiは15日で、ラインの4楽章と、レ・プレリュードをやります。 ・ |
| 2014年2月22日(土) 18:30〜20:45 ライン1、2楽章 初tutti、いきなりの・・・!! みなさん、とってもお久しぶりです! 1月からオケの練習は始まっておりましたが、タクト君はながーいながーい冬眠状態でした。ごめんなさい。m(__)m 2月からいよいよ吉田マエストロの合奏開始の予定でしたが、何十年ぶりという大雪で貴重な練習が2回もお流れになりました。残念無念!! そして、今日、ついに念願の吉田マエストロ登場! この日を待ち望んでおりました〜。 早速練習が始まったのですが・・・。 エッ? いきなりのインテンポ?! 昨年の「運命」は、かなりゆっくりのテンポでとにかくリズムを正確に取るというところからスタートしたので、今回もゆっくりとリズムを合わせていくことから始めるのかと思いきや、かなりのハイスピード。 正直、みんな全然ついていけてない・・・。 もたつき、ゴチャゴチャしながらも、とにかく1楽章を最後まで。いや〜、こりゃあ、大変だわ。 みんな、心して練習しないとね! さて、今回も全体に関する注意点をお知らせしておきます。 【ライン 第1楽章】 (全体を通して) ・sfはきつくなり過ぎないように。ロマン派の音楽なので、その音に重みがある感じで弾く。 ・8分音符の動きは雑にならないよう、ていねいかつ正確に。 ・冒頭のメロディーは、音がデコボコにならないように。 ・冒頭から4小節間は2拍子、5小節目からは3拍子の感じで。 ・スタカートがついている4分音符とついていない4分音符をちゃんと区別して弾く ・17小節目は次の小節へ向かってデクレシェンド。18小節目はmfで。 (以降同じフレーズは同じようにする。) ・21小節目から3小節間、メロディー以外はmfで。 ・23小節目の3拍目ははっきりとした音で ・25小節目の1拍目は短くなりすぎない。 ・32小節目アクセントをつけたりしないで平らに弾きつつ、33小節目に向かう感じ ・53小節目、fpで ・61小節目は1小節間でデクレシェンド ・Bから4小節間は一つの流れで。(2小節ごとで切れない) ・103小節目はmfpで。 ・106小節目からは先へ先へ行く感じ。 ・114小節目はスタカート、116からは何もついていないので音をちゃんと保って、区別して弾く。 ・121小節目からは一つ一つの音をテヌートで、122のスタカートは消す。sfはきつくならない。 ・159小節目3拍目のsfははっきりと。 ・185から同じ音が続くパートは186小節目に入る直前でデクレシェンドし186小節目はmp、188小節目でクレシェンド。(193小節目からも同じ) ・200小節目からの木管はそーっと入る感じで。(強引に割り込まない!?) ・205小節目からはしばらくpを保ち、231のfに向かってゆっくりゆっくりクレシェンド ・264小節目でデクレシェンドし、265小節目の2拍目はppからクレシェンド ・294小節目からはsfに向かってクレシェンド(328小節目殻も同じ) ・309小節目3拍目はアクセントがついてないので、やわらかく。(335小節目も同じ) ・310小節目でデクレシェンドしてpへ ・375小節目3拍目からはmfで動きが見えるように ・382小節目でデクレシェンドし、383小節目はp ・386小節目でデクレシェンドし、387小節目はpp ・Mから4小節かけてクレシェンド、5小節目はf、403小節目でデクレシェンド 【ライン 第2楽章】 ・冒頭から8小節間のメロディーはあまりつながり過ぎないように、適度に区切りを入れる ・9小節目からのメロディーは2小節間が一つのフレーズ、デコボコせず穏やかな感じで ・25小節目からの16分音符は縦型アクセントをしっかり出したらあとは可能な限り小さく。 ・29小節目からはメロディーが聞こえるように。16分音符の動きは小さく。 ・33小節目からは低弦の16分音符をよく聴いて意識をして、そこにはまるように弾く。(はみ出さない) 他にもそれぞれのパートに注意がありましたので、お休みした人は必ずパート内のメンバーに確認して下さい。 次回は、ラインの3楽章、5楽章を合せます! |