�@�@�@�@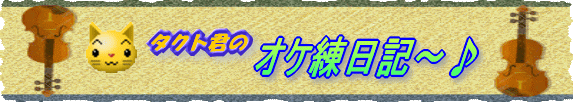 �@�@
�@�@
�E���̃y�[�W�ł́A�s���s�y�F����I�[�P�X�g���̗��K���ɂ�����ߊ삱���������y�������邭�����ɁH���`���������Ǝv���܂��B
 ���ӌ��E�����z�͂�����܂�
���ӌ��E�����z�͂�����܂� 
�@�@ �i�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�j �@�@�@�@
�i�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�j �@�@�@�@ �ߋ��̓��L�������@�@�@
�ߋ��̓��L�������@�@�@ �ŐV�̓��L������
�ŐV�̓��L������
����ł́A���������E�E�E�B
| �Q�O�O�S�N�R���Q�W���i���j �@�@�@�I�y���u�[�߁v�@�{�ԁI�I �@�}�G�X�g���A�Ō�̑唎�ŁH�I �@�s���s���̃I�y���A�����Ȃ邩�H �@ �@�Ƃ��Ƃ��{�ԓ����E�E�E�݂�Ȃ͂ǂ�ȋC�����ō������}�����̂��낤���H �@�{���̏W���͂P�Q���B����܂ł̉��t��ł́A�ߑO���݂�������K���Ė{�Ԃ���������A���ƂȂ���a���B���������A��N���́u�l�G�v�̎����A�}�G�X�g����{�ɂ��{�ԓ����̗��K�͔��q��������قǁA�y���������B���ꂪ�A�x�搶�Ȃ�A�{�Ԃ��Ȃ���A���₢��A����ȏ�̎��Ԃ������āA���K���������Ȃ��Ƃ��낾���ǁE�E�E�B �@���̂R��������Ă������Ƃւ̎��M���炩�A����Ƃ��H �@�P�P������鍠�A�|�c���|�c���ƃI�P�̃����o�[���W�܂�n�߂�B�����y����o���āA���K������l�A�y���������炦����l�A������ׂ�ɉԂ��炩����l�Ȃǂ��܂��܁B �@�P�Q���Ɋy���ɂāA�y���~�[�e�B���O�̂��ƁA���悢��Ō�̍��킹���K�����ɁA�s�b�g�ցB �@�S�������Ȃ��A�`���[�j���O���I����ƂقǂȂ��A���w���̏��ѐ搶�ƂƂ��Ƀ}�G�X�g���o��I�@�݂�Ȃ̒��Ɉ�C�ɋْ����͂���B�}�G�X�g���̃X�R�A�́A����̗��K��A���镔���������{�̌����ɂȂ��Ă����B�w�����Ȃ���A�u���̕����̓_���I�v�Ƃ����Ƃ���̃y�[�W�̒[�����₭�܂肽����ł����̂������B���Ɍ����A�h�b�O�C���[�i���̎��j�Ƃ�������B �@����͂����A���R�݂�����ƒʂ�����������̂Ƃ���A�����o�[�̒N�����v���Ă������낤�B���w���̏��ѐ搶�́A�O���̗��K�ŃI�P�̊낤�������������`�F�b�N�����X�R�A��n�����Ƃ��Ă���B�������A�}�G�X�g���͂����f��A�݂�ȂɌ�������Ɓu�Ō�̗��K�ł́A�݂Ȃ���ɃA���T���u�����邱�ƁA���݂��̌ċz�������ĉ��t���邱�Ƃ���������F�����Ă��炢�����Ǝv���܂��B�I�y�������t���邽�߂ɂ́A��Ɏ����̌܊��̃A���e�i���s���ƒ����Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���䂩�����Ă��鉹���������ł��A������������蒮���A�w���҂̖_�̓����ɋ@�q�ɔ������A���t�ɉ������f�������Ă����Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ł��B�ł́A����܂�����Ŗ`������B�v �@�����āA���킹�n�߂ĂQ���ߖڂŁA�����Ȃ�X�g�b�v�B�u�����̌��̃g�����͎キ�Ȃ�����_���I�n�[�v�̓����ɂ����ƌĉ����ăN���b�V�F���h���邭�炢�̂���ŁI�v�@�u�I�[�{�G�͂����ƃt���[�Y�ɔg�������āB�Q�ԃt���[�g�ƃt�@�S�b�g�͎��̂P�ԃt���[�g�̃����f�B�[�������o���C�����ŁI�v�u�؊ǂ̃����f�B�[�̉��ŗ���錷�̎l�������̓u���E�`���@�`�A�u���E�`���@�`�ƕ�������悤�ɁB���Ɏ㔏�̕����̒e�����ɂ����Ɛ_�o���g���āB�v �@�`���̕����ɑ����āA���̓I�P�݂̂ƂȂ钆�ԕ��������B�u�s�b�R���́A������̓����������Đ����A�������Y���ł����ꂼ��Ɉ�����j���A���X�ɂȂ�͂��B������́A���ɗ�������悤�ɁB���̌�ɏo�Ă���u���͏o������������Ƒ�����B�~�X�e���I�[�\��������āA����܂ł����邨����o���o���̃~�X�e���I�[�\�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁB�i�j�v �@�����āA�P���̍Ō�B�u�����̍Ō�̂̂��ŁA�j��������Ă��܂�����A�ǂ��Ő邩�͎w���_�ɍ��킹�ĂˁI�v �@���ɁA�Q���̓��u���̊ԑt�Ȃƌ����̂́A�Ƃ��Ă��d�v�ȋȂł��B�x�e���I����ĐȂɒ��������q�l���ӂ����уI�y���̐��E�ɂ����ƈ����߂���ڂ��Ă��邩��ł��B�����āA���̃I�y���[�߂̊ԑt�Ȃ͂����������Ӗ��ł͔��ɂ悭�ł��Ă��āA�ߌ��̗\�����Ђ��Ђ��Ɗ��������A���������ƒ��O�����̐��E�Ɉ����߂��͂������Ă��܂��B���A��������邩�ǂ����͉��t����݂Ȃ���ɂ������Ă��܂��B�ǂ����A�������蓪�̒��ɃC���[�W�������Ĉ��̉����o���ĉ������B�v �@���̌�A�����@��D��I���ďo�Ă���V�[���ƁA��C�ɔ��ōŌ�̕����B�u�u���́A�Ōタ����Ƃ���rit�������B������Ƃ��������C�ɂ��āI�@�Ō�͏���ɏI���Ȃ��ŁI�I�@���������Ō�̏u�Ԃɉ��t���s�^���Ƃ͂܂�悤�A�w���҂͌��\���������Ă����肵�܂��B�i�j�@�ł�����A�l�̖_���������茩�āA��ɍ��킹�ĂˁI�@����A���K�͂���ŏI��B�{�Ԃ�낵���ˁB�v �@�ȏ�A�g�[�^���P���Ԃŗ��K�͏I�����Ă��܂����B���K�̍Ō�ɁA���g���[�i�[�̈��搶����u�I�y���͕��͋C�������ĉ��t���邱�Ƃ��厖�B���䂪�����Ȃ��Ă��A�����̒��ŕ����̓W�J���C���[�W���Ȃ���A���t����悤�ɂ��܂��傤�B��������A�����Ƃ������t���ł���͂��ł��B�v�ƃ_�������̂��b���������B �@�͂Ă��āA�{�Ԃ͂����Ȃ邱�ƂɂȂ�̂��H �@�����āA���悢��J���I �@�q�Ȃ́A�قږ��ȁB�����܂ł̒i�K�ł́A�I�y�������͐����Ƃ����悤�B�������A�̐S�̉��t�͂��ꂩ��E�E�E�X�e�[�W��ɂ̓C�V���^�搶�̋�J�̌����Ƃ������镑��Z�b�g�����z�I�ȕ��͋C�������o���Ă���B���̐ፑ�̕��͋C������ɍ��߂鉹�y�������ݎn�߂�B�I�P�̉��t�ɂ́A�����d��������������̂́A�Ȃ��Ȃ���������o���̂悤�ł���B�Ƃ肠�����A�ق��B�����āA�q�������A�^�Ђ傤�Ǝ��X�ɃL���X�g�����炵���̐����I���A���͏u���ԂɁu�[�߁v�̐��E�ɖ�������Ă����͂��������B�������A�����ŐM�����������Ƃ��N�������B�����炱���炩��t���b�V���������ꂽ�̂��I�@�J���O�ɒ��ӂ𑣂����ɂ�������炸�ł���B���t���̎B�e�֎~�͏펯�Ȃ̂ɁE�E�E�s���s���̕����ӎ��̒Ⴓ���v��������I�悷��V�[�������̌�����x�����x������ꂽ�B����ȉߍ��ȏ̒��ł��A��������͂�������Ɩ��ɐ��肫��A����A���A���̂������Ă����B�������Ƃ������A���グ���v�������ł���B����ɂ��Ă��A����Ȃ��Ƃ��N����Ȃ�āI�@�����s���Ƃ��āA�������܂�Ȃ��C�����ł����ς��������B�Y���҂ɂ͏\�����Ȃ��ė~�������̂ł���B �@����ȗl�X�����z���A�P���͂܂��܂������ɏI���E�E�E�ƂȂ�͂����A����Ă���͂����j�����Ȃ��Ȃ�����Ă����A�������̃}�G�X�g���������Q�ĂĂ����悤�������B�Ƃɂ����\�Ȍ���A�Ō�̉����t�F���}�[�^���āA���Ƃ����܂��������ǁB �@�����ł���B �@�P�T���̋x�e�̂̂��A��Q���ցB����̃t���b�V���̌��Ŕ��Ȃ𑣂��Ӗ������߁A�Ăсu�㉉���̎B�e�͂������������B�v�̃A�i�E���X�B���ނ�A�z���g�ɁI �@�P�������Ƃ������ɏI����Ăق��Ƃ����̂��A�I�P�̉��t�͗��������������Ă����悤���B�܂��A�P�����Q���̕����A����ړ����₷���Ƃ����̂�����݂��������ǁB�s���̃q������́A�u�r���ł��ݏグ�Ă�����̂������āA�����Ȃ��Ȃ肻���ɂȂ��ˁ`�v�ƌ����Ă������A���ɂ��u���̕����̂��̉̂��Ƃ��邤�邫������ā`�v�ȂǁA�ʂ̈Ӗ��ʼn��t�s�\�ɂȂ�S�z���������肵�āH�I �@�ȂǂƂ����Ȏv�����̂��āA�Ƃ��Ƃ��Ō�̍Ō�B���x�́A�^�C�~���O�悭�j��������n�߁A�ꓯ�}�G�X�g���̃^�N�g�ɍ��킹�āA�Ō�̉����h���I�@���`�A���ɏI������I�I�I�@��ꂩ��́A����̔��芅�сB�v���A�������R�����Ƃ����Z���Ԃł悭����ȑ�Ȃ���������̂��B�N���������tutti�Łu����Ȃ�A�S�R�_���I�v�ƁA�����Ȃ�}�G�X�g������␅�𗁂т����A���K�ɕ��N�������X�E�E�E�B���Ă������ɃG�L�X�g�������ꂸ�A�₫����������ꂽ���Ƃ��������B �@�{���ɂ����܂ł����Ȃ��Ƃ�����������ǁA�������Ė{�Ԃ��ɏI����ƁA��������̐l�Ɋ��ӂ������C�����ł����ς��ɂȂ�B �@�������āA�s���s�n�܂��Ĉȗ��̃I�y�������́A��������̐l�X�̗͂����W���A�听���̂����ɖ�����܂����B �@��{�搶�A�n��搶�A���ѐ搶�A�����̑�т���A�^�Ђ傤���̂x�搶�A�^���̏��R����A�y�ǂ̈�コ��A�䂤�Â鎙�������c�݂̂�ȁA�����ăX�^�b�t�݂̂Ȃ��܁A�{���ɖ{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����A�����l�ł����B�܂��A�������Ћ��������肢���܂��I |
| �Q�O�O�S�N�R���Q�V���i�y�j �@�@���P�S�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�y�Q�l�����E�v���[�x�z�@�I�y���u�[�߁v�@ �@���ӂƗ��_�̃Q�l�E�v���E�E�E �@ �@���悢�斾�����{�ԁB�I�P�j���w�́A���X���ɏW�����A�X�e�[�W�E�I�[�P�X�g���s�b�g�݉c�̂���`���B�P�Q���ɂ͏����c���������A�s�b�g���z�u�B�Ȃ�ƁA�s�b�g���g�p����̂́A�s����َn�܂��Ĉȗ��g�����h�̂��Ƃ��Ƃ��I�@�u����ȂɎg���ĂȂ���A�K�ѕt���Ă����Ɠ����Ȃ���Ȃ��̂��`�v�Ƃ����ꕔ�̐S�z���������藠��A���Ƀ��b�p�ɂ��̋@�\���ʂ������̂������B�������A����Ȑݔ��������Ă��Ȃ���A���܂ň�x���g�������Ƃ��Ȃ��Ƃ́E�E�E��́A���̂��߂́H�H �@�s���s���̕����ӎ������ꂾ���Ⴂ�Ƃ������Ƃ��A�͂��܂��A��ق������͊W�e���̌[�֊���������Ȃ̂��A�^�N�g�̂悤�Ȏq���ɂ͂킩��Ȃ����A�Ƃɂ������������Ȃ��b�ł���B����B �@�ƁA����Șb�͂��Ă����A�����ɂ͂�������x����̌����Ŏg���ɂ͐ɂ������炢���h�ȃZ�b�g���o���オ���Ă����B���Ɨ^�Ђ傤�̂��ƂȂ̂����A���ꂪ�A�˂͂����ƊJ���߂ł���悤�ɂȂ��Ă��邵�A�����������肵�Ă��āA�I�������ɁA��q�͂Ȃ�Ɩ{�����g�p�i�I�P�c���j����Ƃ́I�j�B����A�\�Z���Ȃ��Ƃ������ƂŁA�v���ɂ͗��܂��A�y�F�����̃C�V���^�搶���哹��S���ƂȂ�A�����̃Z�b�g���قƂ�Lj�l�ł����ɂȂ����̂������I�I�@�����́A�x�j�A�ɂ���炵���G�������������炢�ɍl���Ă��������Ȃ̂����A���o�Ƃ���Ɩ��ł�����ƉA�e���o��悤�ɒ��͂��̂��炢�̑����ȏ�̂��̂��g���āA�l�������Əo����ł���悤�Ɉ����˂����āE�E�E�ȂǂȂǁA����͂���ׂ͍��Ȏw���Ƃ��������N�G�X�g���o�āA�������������Ԓ��A�u���ł���Ȋ�������l�ł���Ȃ��Ɓ`�I�v�Ɩ҂苶���Ȃ���A�쐬���ꂽ�Ƃ��B����͂�A�����l�ł���B�������ŁA�X�e�[�W�̕��͋C�͂����o�b�`���B�\���X�g���݂Ȃ���A�o�b�`��������A�c����́E�E�E��͂�I�P�̉��t�B �@�I�P�s�b�g���̔z�u�͗\��ʂ�ɏI��A���H�x�e��A���悢��I�P���K����J�n�B �@�Ă�����ʂ������̂��Ȃ��Ǝv���Ă�����A�u�݂̂̂Ȃ���ɁA���C���N�����������Ȃ�����A�̂̕������ɂ��܂��傤�v�Ɣ�{�搶�B�c���̒��ɁA�����s�����悬��B�����āA����܂ŁA�قƂ�ǒʂ��ŗ��K�������Ƃ��Ȃ��̂��B���ꂾ���A�I�P�̗��K����Ԏ���Ă����Ƃ������Ȃ��ǂ��B�܂��A���ɉ̂̕����́A�e���|���h���̂ŁA�O����ɂ���Ă����ɂ��������Ƃ͂Ȃ��̂�����A�}�G�X�g���̂�������邱�ƂɊԈႢ�͂Ȃ����낤�B �@���킹�Ă݂�ƁA�Ă̒�A���Ă���Ȃ������o�[������ق�E�E�E���̊��ɋy��ŁA�y���ɂ�������̓_������I �@�j���A���X�Ȃǂ��m�F���Ȃ���A�I�P���͂ЂƂ܂��I���B���̌�A�X�e�[�W��ŃL���X�g�݂̂Ȃ��ꓖ����i�ǂ̈ʒu�ɗ����ĉ̂����Ȃǂ̊m�F�j�����̂ŁA�I�P�͗[�H�x�e�B �@�����Ă����āA�R�O���x��ŁA���悢��Q�l������v���[�x�̎n�܂�n�܂�`�B�i�Ȃ�ĕ�����Ă���ꂽ�͍̂ŏ������B�j �قƂ�ǂ̃����o�[���I�y���͏��߂āA�������X�e�[�W��̓������قƂ�nj����Ȃ����Â��s�b�g�Ƃ���������`���āA�I�P�͊��S�ɉ̂̑������������Ă��܂��Ă���B����Ɏ����̃e���|�Œe���Ă��܂��l����A�o�Ԃ��������藎�Ƃ��Ă��܂��p�[�g����ŁA�����������Ⴉ�߂����Ⴉ�B�^�N�g�́A�����S��������t���Ă��܂�����I �@���܂�̃I�P�̎S��ɁA����͂����كM���M���܂ŋ��c������낤�Ȃ��Ǝv���Ă�����A�ӊO�ɂ��}�G�X�g���́u�͂��A�����͂������U�B���Ⴀ�A�����P�Q������̍Ō�̗��K�A��낵���v�ƌ����c���A�����Ă����Ă��܂����B �@�R���i�`���E�V�f�A�A�X�m�z���o���A�`�����g�G���\�E�f�L���m�_���E�J�H�@ �@�݂�Ȃ̋��ɂ��s���A�����ė��_�������܂��B �@�ʂ����āA�����̉��t�́A�ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂��H �@�q�Â��r |
| �Q�O�O�S�N�R���Q�P���i���j �@�@���X�F�R�O�`�P�T�F�S�T�@�ytutti���̍����z�@�I�y���u�[�߁v�@ �@�\���X�g�݂̂Ȃ�����I�[���ɕ�܂�āH�I �@ �@�����A�{�Ԉ�T�ԑO�I�@�����͌ߌ�̍����̗\��`�� �@��T�A���K�̏I��ɁA�}�G�X�g����{���u�����A����͉̍����E�E�E�B�I�P�Ɖ̂Ƃ��ꂼ��ʁX�ɗ��K��ς�ł������̂����݂��Ɍ��������A�ł����N���N���鎞�ł��ˁB�����āA����ɍ��߂����āE�E�E�v�Ƃ���������Ă����B �@����́A�{�ԃM���M���܂ʼn̍����̗\�肪�Ȃ���������A���҂����s�����傫�������B�E�E�E���ǁA�����ȃ}�G�X�g�������߂����Ƃ�����A�����Ƒ��v���B �@�ߑO���́A�܂��l�߂̗��K���I����Ă��Ȃ���T�̑�������E�E�E�B������̗��K�Ƃ����āA������Ƃ݂�Ȃ̃G���W���̂����肪�悭�Ȃ��݂����B�ł��A�P�O��������ƁA�u���`�A�I�y�����`�A�[�߂��`�v�̊��������Ă����悤�ȁE�E�E�B �@��̏C���������Ȃ���A���ƃX���[�Y�ɗ��ꂽ���ȁB�c��̎��ԂŁA�I�P�݂̂ƂȂ镔���̍��킹������āA�����x�e�B���̋x�e���̊ԂɁA���`�[���́u�����`��c�v�Ȃ���̂�����Ă����B�^�N�g�́A�������s�I�H �@���āA�ߌ�A�q�������ƃ\���X�g�݂̂Ȃ��A���X�o��B���K���ɐS�n�悢�ْ������Y���n�߂�B �@�L�����K��ꂪ�m�ۂł��Ȃ��������߁A�ŋ��Ȃ��A�̗��K�݂̂ƂȂ�A�q�������͂�����ƌ˘f���Ă���悤�������B����ł��A�O���ɕ��w���̏��ѐ搶�i�����ꃖ���A�q�������̎w���͔ނ�����Ă����j�̎p�������āA�悤�₭���q�����߂����悤�������B �@��ɁA���������̕����݂̂�����āA�q�������Ƃ̓o�C�o�C�B���T�̖{�ԁA�K���o���E�ˁ� �@�����āA�\���X�g�݂̂Ȃ���Ƃ̍��킹�B�I�P�̂قƂ�ǂ̃����o�[�́A�I�y�����̌��Ƃ����āA���Ȃ�ْ��C���E�E�E�B�����Ă���^�N�g�܂ŐS�����o�N�o�N���Ă���������B�ł��A�\���X�g�݂̂Ȃ���A���ɁA���̑�т���̔����ɁA�݂�Ȃ������薣������A�g�[�߁h�̐��E�Ɉ������܂�Ă������悤�������B�@����̃\���X�g����́A�݂�ȃI�y���̃x�e�����Ƃ����āA���I�[�����������I�I�@����́A�����{�Ԃ��y���݂Ȃ�Ă���Ȃ��B�ςȂ���A�ꐶ������邩���B �@���`�A�����{�ԂɂȂ�Ȃ����Ȃ��B �@�����ƁA���̑O�ɁA�݂�Ȃ��u���K�K�C�h�v���Q�l�ɁA�������蕜�K�����K���āA�{�Ԃɔ����ĂˁI �y�^�N�g�̂ǁ[���Ă��C�ɂȂ�E�E�E�z �@�����ɂ��|�p�ƂƂ��������̃����т��g���[�h�}�[�N�������A���w���̏��ѐ搶�B�{���́A�����肳���ς�w�A�œo��B �@���������Ȃ��H�@�S���̕ω��H�@���`��A�C�ɂȂ�C�ɂȂ�B����́A��ɒ������˂I |
| �Q�O�O�S�N�R���P�R���i�y�j �@�@���P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�ytutti�z�@�I�y���u�[�߁v�@ �@�y���ɂ�������Ȃ��Ł`�I �@ �@���������R�̂��ƂȂ���A�W�܂�͂��������`��@�������A�O�X��̔��Ȃ܂��A���������V�C���y�N��l�������Ă��ꂽ�B���K�o���\��\�ɉ����A�C���y�N�����܂ł�������Ɨp�ӂ��Ă���A�Ȃ��Ȃ����ʂ��̂悢��ԂɂȂ����I �@���K�O�̃}�G�X�g���Ƃ̑ł����킹��������ŗ��K�J�n���X���[�Y�B���ꂩ��͗��K�������悭�Ȃ肻���`�B �@�����A�̐S�̗��K�̕��́E�E�E�B �@�O��̑�������Ƃ������ƂłP���̂R�W�̑O��Andante misterioso����B�S�̓I�ɗ�����悭�Ȃ��Ă��Ă��邪�A����ς���͉����I�@�����́A�u���[���ƁI�v�Ƃ����}�G�X�g���̂������肵�����ƂƂ��Ɏ~�߂�ꂽ�����̔����͉����̈����������B�c��̔����́A�҂ׂ��Ƃ����҂����ɓ����Ă��܂��t���C���O�A�t���[�Y�̗���ɂ��Ă̒��ӂȂǁB �@�t���C���O�͐S�z���Ȃ��E�E�E�݂�ȁA�u�[�߂̗��K�K�C�h�v�Ȃǂ��Q�l�ɂ��āA���ɃG�L�X�g���̕��ɂ͓`�B����������ˁB �^�N�g�����Ă�������A�����͂u��.1�̃t���C���O�����������悤�ȁE�E�E�B �@���ꂩ��A�t���C���O��h��������̕��@�́A�y���ɂ���������A�w����R���}�X�������ƌ��邱�ƁB �@��{�搶���u�I�y���̉��y�͂������肾����A��������y���ɓ���āA������ɒ��ӂ��]�T�������Ă����Ȃ��ƁE�E�E�B�y���ɂ�������Ă��ẮA�_���ł��I�v�Ƃ͂����肨��������Ă�����ˁB �@�������A����̓I�[�P�X�g���s�b�g�����A�Ɩ��͂��Ȃ�Â��A�y���͂ƂĂ����Â炢���Ƃ��\�z����܂��B������x�Õ����Ă����Ȃ��ƁA��ςȂ��ƂɂȂ邼�`�B �@���āA�[�ߖ{�ԑO���E�����̃X�P�W���[�����z�z����A���܂ňȏ�ɋC���������߂ė��K�E���K���ˁB �@�݂�ȁA�K���o���E�I�I |
| �Q�O�O�S�N�R���U���i�y�j �@�@���P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�ytutti�z�@�I�y���u�[�߁v�@ �@�����A�����A����Ă��`�I �@ �@��T�̏��ѐ搶�A���搶�̋ꌾ�������Ă��A�����Ԃ�̔�{tutti�ɂ݂͂�ȑ��X�ɏW�����A�l���E�p�[�g���Ȃǂɗ]�O���Ȃ������B����Ȓ�������Ƃ����g���u�������I�@�Ȃ�ƁA������Ƃ����A���~�X�ʼn���e�B���p�j�[���^�яo���Ȃ��H�I�@�t�҂͂Ƃ����ɑ����Ă���ƌ����̂ɁB�c���E���c�������������Ƃ��钆�A��{�搶�o��B������A�e�B���p�j�[�̃Z�b�g�A�b�v���Ԃɍ���Ȃ��`�B�i���̌�悤�₭�A�����Ƃ�āA�e�B���p�j�[���������B�j �@�������A���͋��Ȃ�E�E�E�e�B���p�j�[�͂Ȃ��Ƃ�tutti�͊J�n�B�̂ݏ��Ԃ̃����o�[�����邽�߁A�u�㔼�R�O�����炢�͓����܂��v�Ɣ�{�搶�B���C�����A�������܂��B �@���āA���K�̕��́A�O��܂ł͋Ȃ̕��͋C�������Ƃ��ނƂ������ƂŁA�ׂ��ȂƂ���œ˂����肹�������Ă������ǁA�����͂ƂĂ��ƂĂ��O����ɍ��킹�Ă������̂������B�����Ȃ�ƁA�Q���Ԃ�����Ƃ̗��K���Ԃ͂����Ƃ����Ԃɉ߂��Ă��܂��A�S�̂̂S���̂P���炢�����ł��Ȃ������B���`��A�{�ԂɊԂɍ����̂��H�@��{�搶���u���̃y�[�X���ƁA�Q�P���ߑO�̗��K�܂ł���Ă悤�₭��ʂ������Ċ������ȁB�Ƃ͂����Ă��A����͂����܂ł݂Ȃ������̂悤�ɂقڑS����������W�܂��Ă��ꂽ��̘b�ł����E�E�E�v�Ƃ���������Ă����B���Ƃ��A�{�ԃM���M���Ɏd�グ�ɂȂ낤�Ƃ��A���悢���y��n�邽�߂ɑË��������Ȃ��}�G�X�g���̎p���́A�{���ɑf���炵���ƃ^�N�g�͎v���B �@�����āA�݂�Ȃ��{���ɂ��̒Z���Ԃł悭�撣���Ă���B�E�E�E���A�A�}�I�P�̋������i�H�j�A�g�����h�̕ǂ��݂�Ȃ̑O�Ɍ������������͂�����̂������B�����������A����lj����Ȃ�ˁE�E�E�B���������A���ѐ搶���A�}�I�P�̍��]�̈�Ɂu���L�������A�L���ȃ��Y���v�Ƃ����̂����ɂ�����������Ƃ�������Ă����Ȃ��B���`��A���܂��ɁA�g���L�������h�ɔY�܂���Ă���̂��B���������́A�l�l���C�����邵���Ȃ�����ˁB�����̗��K�I�����Ɉ��搶������ꂽ�悤�Ɂu���K���K�v�����������邵���Ȃ��B�������łȂ��A�ǂ��ˁ� �@�����A���f�G�ȗ[�߂̉��t�ڎw���āA�������e�����K�ɗ�݂܂��傤�`�I �@�y�����ҥ�����̖��̓c���C�H�z �@�����́A�Q���� �u���̐ȂɃc���C����̎p�������Ȃ��B�ނ̂u����e���t�H�[���͑�ϔ������A�^�N�g�͂����ڂ�D���邱�Ƃ������B�ǂ������̂��Ȃ��Ǝv���Ă�����A�ǂ����Ă��d�����I��炸���K�ɂ͎Q���ł��Ȃ��Ƃ̂��ƁB����ł��A�Ƃ肠�����ނ��ۊǁE�^����S�����Ă���o�X�h������K�ɊԂɍ����悤�ɉ��܂œ͂��ɗ��Ă���āA�I�����ɂ͂����ƈ������ɗ��Ă��ꂽ�̂������B����ɂȂ�Ȃ��`�B���āA�C�ɂȂ�ނ̐E��́E�E�E�m��l���m��s���s�s����ق̂��������ɗ����̃��b�p�Ȍ����̒��ɂ������肵�܂��B |
| �Q�O�O�S�N�Q���Q�W���i�y�j �@�@���P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�ytutti�z�@�I�y���u�[�߁v�@ �@�_�a�Ɍ����邪�A���̎��́E�E�E�H �@ �@���T����T�Ɉ��������A���ѐ搶��tutti�`��@�Ƃ����낪�`�A�Ȃ�Ǝ��ԂɂȂ��Ă��A�؊ǃg�b�v������Ȃ��I�H�@���̑��g�����y�b�g�E�g�b�v���g�����{�[���Q���̎p�������Ȃ��B�ǂȂ��Ȃ��Ă�̂�[�B����ɂ͂܂��A�g���[�i�[�̈��搶���炿����ƌ������ꌾ�B�u�ǂ̃p�[�g�����Ȃő���Ȃ����A�N���c�����ĂȂ��́H�@���ꂶ��A���K�̌����������Ȃ�ł���I�@�}�G�X�g�������̓��d�_�I�ɗ��K�������ӏ����������邵�E�E�E�B����͂����������Ƃ��Ȃ��悤�ɁI�I�@�w���҂̐搶�Ɏ��炾��B�v �@���ѐ搶����́A�u�{�N�̂��Ƃ͂������ǁA��{�搶��tutti�݂͂�ȂɂƂ��ăv���X�ɂȂ邱�Ƃ��肾����A�݂Ȃ��ꂼ��Ɏd���₢�낢�뎖����邱�ƂƎv���܂����A�Ȃ�ׂ����Ԍ���ŏW�܂��ď����ł�����tutti�ł���悤�ɂ��Гw�͂��ĉ������B�v�ƁB�@���`�A�搶���ɂ���Ȃ��Ƃ����킹��Ȃ�āA������Ə�Ȃ��Ȃ��B�C���y�N����l�Ƃ��������Ƃ���ŁA���̂ւ�̑̐����ǂ��ɂ����Ă����Ȃ��ƂˁB �@���āA���K�̕��́A��T�̕��K�����˂āA������E�E�E�������A�̐S�̃I�[�{�G�����Ȃ��̂ŁA������Ƃ��ɂ������B �����̎�Ȓ��ӓ_�͉��L�̒ʂ�B �@�E�S�Ԃ���͎��������̔��t�ł����A�q�������͂ǂ����Ă����肪���ɂȂ�̂ŁA�I�P�͐�Α���Ȃ��悤�ɁB���ɁA���y��̃s�`�J�[�g�͋}���Ȃ��ŁB�i�x�����������芴���āB�j �@�@�܂��A���̕����́A�q���̑��Â����̃j���A���X��Y�ꂸ�Ɂi�ǂ́A�u���X�̃X�s�[�h���グ��j �@�E�T�Ԃ̂e���͎q���̃\�����x�������ŁB�i�����ْ����邾�낤����B�j �@�E�V�ԂT�O����̖؊ǂ̃g�����̓N���b�V�F���h��K���B�i�������Ȃ��悤�Ɂj�@�܂��A���Y���𐳊m�ɁI �@�E�U�R�ԂS���ߖڂ̓��̉��͂������荇�킹��B�i�������Ȃ��ƁA���̂��A������Ƃ��Ắu���H�v�Ɍq����Ȃ����I �@�E�U�R�ԂT���ߖڂ���̌��́A�d�X���������ŁB���������Ȃ��悤�ɁB �@�E�U�U�ԁ`�U�W�Ԃ̃e���|�̗h��ɁA���ӂ��āB �@�E�U�X�ԂS���ߖڂ���̂P�U�������̓����́A���𑵂��A�ϓ��ȉ��ŁB�����ăf�R�{�R�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁB �@�E�U�X�ԁ`�V�P�Ԃ܂ł��e���|�����Ȃ�h���Ǝv���̂ŁA�v���ӁB �@�E�V�P�Ԃ���A�_�C�i�~�N�X�i���`�����j�̕�������Ƃ���B �@�E�V�S�Ԃ̂Q���ߑO�A���Ȃ�e���|��������̂ŁA�w���_����ɂ����Ȃ��悤�ɁB �@�E�V�W�Ԃ̂Q���ߑO�Ameno�ɂȂ��Ă�͂��A�w���_��ǂ��z���Ȃ��悤�ɁI �@���ꂩ��A���ѐ搶�͂���������������Ă�����B�u���{�ł͉��̂Ȃ������g�x���h�ƖĂ��܂������ǁA�x�݂Ƃ����ϔO���Ⴄ��ˁB�x�݂Ƃ������A�g�ԁh���Ǝv���ė~�����B���͂Ȃ��Ă��A���y�͊m���ɗ���Č����Ă�킯������B���ɁA�Z���x���́A���̗������������̂Ŋ����Ă��Ȃ��ƁA����͂�����Ă����Ĕ�������Ă��܂�����A�t�ɏ��x�ꂽ�肷�邩��ˁB�v�@�Ȃ�قǁA�x���ł͂Ȃ������Ɗ����邩�E�E�E����́A������Ɩڂ���E���R���̂���ˁB�@�������A��{�搶�̎����̂���q���[�I �@���ɂ��A���ѐ搶����̓A���T���u�����ӎ����ĉ��t���邱�Ƃ��A�������J�ɋ����Ă��������܂����B���܂ł́A�����̂��Ƃł����ς������ς����������̋��������y�F����I�P�̉��t�ɁA�܂���G�b�Z���X��������������B �������A�݂�Ȃ������Y��Ȃ��Ŏ������Ă����Ă���Ȃ��ƂˁB �@����A���y��t�҂ł����鏬�ѐ搶���w���҂Ɍ}�������ƂŁA�I�P�̈����o�����m���ɑ������Ǝv���B�}�G�X�g����{����܂Ōv�Z���Ă������ǂ����͒肩�ł͂Ȃ�����ǁA���Ƃ��V����Ƃ��������悤�̂Ȃ��f���炵���єz�Ԃ�ł���B �@���ѐ搶�E�E�E�D�������Ɍ����āA���\�V�r�A�ȂƂ�����B�ł��A�����炱���݂�Ȃ��X�Ɋ撣�낤�A���K���Ȃ���I�Ƃ����C�����ɂȂ�����Ȃ����ȁH �@�����A���ƈꃖ���A�w�͂���݂̂��I�@�i���݂̂Ȃ���A���������V�N�ˁI�����ѐ搶���j �@ |
| �Q�O�O�S�N�Q���Q�P���i�y�j �@�@���P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�ytutti�z�@�I�y���u�[�߁v�@ �@�Ƃ��Ă��_�a�ȁ`���w���F���ѐ搶 �@���T�Ɨ��T�́A��{�搶�s�݂̂��߁A�}�G�X�g���C�`�����̂���q����Ƃ������Ƃŏ��ѐ搶���w���ɗ��ĉ�����̂��B �Ƃ͂������̂́A����́g�I�y���h�Ƃ�������ȋȖځB�}�G�X�g���̊����ɗR��Ƃ��낪�傫�������ɁA�ǂ�ȗ��K�ɂȂ�̂����Ҕ����s���������E�E�E�B �@�����āA���ꂽ���ѐ搶�́A�Z�~�����O�̔��łƂ��Ă��F���A������҂�ӂ��悩�Ȋ����ł������t�����h���[�ȕ��ł����B �ǂ���烔�@�C�I������e�����炵���A�I�P�����o�[�̐S�����悭��������Ă��āA�悫�q���g�A�A�h�o�C�X���������������܂����B�\�z���͂邩�ɏ���L�Ӌ`�ȗ��K�ł����B �@�u�{�N�̎w���̓}�G�X�g���ƈقȂ邱�Ƃ�����Ǝv���̂ŁA�������ޕK�v�͂Ȃ��ł��B�����܂ŎQ�l�Ƃ������ƂŁE�E�E�B�v�Ƃ��������̂ŁA����u�[�߂̗��K�K�C�h�v�͂��x�݂������E�E�E�Ƃ������ƂŁA�^�N�g���璍�ӓ_�������Ƃ��m�点���܂��B �@ �@���I�[�v�j���O�̋��ǂ͉������������茈�߂āI�i����������Ȃ��悤�Ɂj �@���P�`�̖؊ǂ̓����́A�y�킪�ڂ邲�Ƃɔ����ȊԂ��Ă��܂�Ȃ��悤�ɁB���ׂĂ���̗���ƂȂ�悤�ɁB �@�i���ق��̉ӏ��ł��������Ƃ������܂��j �@���V�̑O�̌��͏�ɂ��Łi�g�����Ŏキ�Ȃ�Ȃ��悤�Ɂj �@���P�O�͂Q����. Vn�̉����𐳂�����������B���̏�ɂP���������ɂ̂��āB �@���P�Q�̊ǂ̃A���T���u���͉����d�˂Ă��������ŁB �@���P�U����̓f�N���b�V�F���h�ʼn��������炭�Ȃ�Ȃ��悤�ɁB �@���Q�P����̌��̃��j�]���̉����́A�������������荇�킹�āB �@��2���P�P�R�̂S���ߖڂ���́A�ٔ����������āB���ǂƃ`�F���͂W���̘A���ŋ}���Ȃ��B �@���P�P�R�̂U���ߖڂ̂P���߂̂W�������͌����ē]�Ȃ��悤�ɁB �@���P�P�S�̂R�A�S���ߖڂ̌��̃X�^�J�[�g��Adagio�̒��ł̃X�^�J�[�g�Ȃ̂ŁA���܂�s�߂��Ȃ��悤�ɁB �@��̎w�E�̒��ŁA���ɁA�g�����Ȋԁh�ɂ��ẮA�ǂ�ȋȂ����t���鎞�ɂł����ʂ��Č����邱�Ƃ��Ǝv���܂��B �@������ӎ����邵�Ȃ��ŁA���t�����Ⴆ��悤�ɕς���ĕ���������I�i�������A�悢���Ɂj �@�Ƃ��Ă���Ȃ��Ƃ�����A��ΖY��Ȃ��Ńl�I�I �@�ӂӂӁA���T�̗��K���y���݂Ȃ̂��`�� |
| �Q�O�O�S�N�Q���P�T���i���j �@�@���P�O�F�O�O�`�P�U�F�O�O�@�ytutti�z�@�I�y���u�[�߁v�@ �@�@���͏t���ɏ���ā`�H�I �@�����A�Q�T�ԂԂ��tutti�I�@���t���l���̐��ʂ͂ǂ����ȁH �@����̔z�u�ɂ́A�݂�ȑ啪�Ȃ��悤���ˁB�ł��ł��E�E�E�����́A�Ƃ��Ă��c�O�Ȃ��ƂɃI�[�{�G�����x�݂Ȃ̂��B����������̂̃~�h�������͂����Ƒ�t�̎�z�����Ă��Ă��ꂽ���ǁA���̔ނ��O�X���Ƀ_���ɂȂ�A�Ȃ��Ȃ����ɂ�����x��`�B�}�G�X�g���ɂ͐\����Ȃ��̂����ǁA�����̓I�[�{�G�����A�Q�����t���[�g�����i�m�������͏C�w���s��j�Ƃ����ƂĂ��������ł�tutti�ƂȂ��Ă��܂��܂����B �@�������A�ǂ�ȏ��ɂ����Ă��A���ׂ����Ƃ����������������Ďw�����Ă����̂���{�搶�̑f���炵���Ƃ���B�������ƂĂ��L�Ӌ`�ȗ��K�ł����B �@���K�J�n���Ɂu�̍����̕��������ɐi��ł��āA�ƂĂ��������̂��o���オ���Ă��Ă��܂��B�I�P����������撣��܂��傤�I�v�Ƃ����}�G�X�g���̂Ђƌ��������āA�݂�Ȃ͐^�����̂��́B�ƂĂ������ْ������Y���Ă���B �@���āA�������ׂ����w�����u�[�߂̗��K�K�C�h�v�ɔC���܂����A�}�G�X�g�������x���������Ă���ꂽ�_�ɂ��Ă����ċ����Ă����܂��B�݂�ȁA�������蕜�K���Čl���ɐ������ĂˁI �@�P�D�f�N���b�V�F���h�͂������� �@�Q�D���̕������傫���Ȃ肷���Ȃ��悤�Ɂi���Ɍ��y��͑S���̉������킹�Ă��ɂȂ�悤�Ɂj �@�@�@�������A�n��ȉ��ɂȂ��Ă̓_���I�i����`�j �@�R�Drit.��accel.���X�̃e���|�̕ς��ڂ͎w�������č��킹�āI�i��ɍs������A��яo������̓_���I�j �@���āA�����̃}�G�X�g���͑�ϐh�����ł������B�ԕ��ǁ��A�����M�[���@���ɂ��@���Ɗi�����A�K���Ɏw���_��U���Ă���ꂽ�B�u�����ăS�����v�ƌ����A���[��Ɵ�������ł����ɃX�R�A�Ɍ�������p�͒ɁX����������A���̔M�ӂɊ�������o�����B �@���悢��{�Ԃ܂łP�����Ƃ�����ƁB�܂��܂����K�ɗ��ŁA�������t�����悤�ˁI �@�y�}�G�X�g���̈�l�V���I�H�z �@�}�G�X�g���́Atutti�̎������w���ȊO�ɁA�g���h�A�g�^�Ђ傤�h�A�g�^���h�A�g�y�ǁh�A�g�q�������h�̖��܂ł��Ȃ��Ă����B���������y�Ȃ𑲋Ƃ���Ă��邾������B�i�u���̃}�~�����́A�}�G�X�g���́g���h�̉B��t�@���炵���E�E�E�B�j�������ŃI�y�����̌��ł��A�݂�Ȃ��̓�Ȃɂ��܂�����Ă����Ă���B�Ƃ��낪�A�����̓I�[�{�G�����x�݂������̂ŁA���̕��܂ʼn̂��Ă���Ă����B�@���Őh�����A�Ȃ�ƈ�l�łV�����I�@�̗́��A�̏��Ղ�������ςȈ���������낤�Ȃ��B �@�����l�ł��A�}�G�X�g���I�@���`�A���ӥ���ӁB |
| �Q�O�O�S�N�P���R�P���i�y�j �@�@���P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�ytutti�z�@�I�y���u�[�߁v�@ �@���m�ȉ����ɂ́A���K���K���s���I �@�����́A��{�搶�ɂ��u�[�߁v�̂R��ڂ�tutti�B��ϐS�������ƂɁA���搶���Q�����Ă���āA������肳��ɏ[������tutti�ƂȂ肻���B�o�ȗ������ɍ����I�Ŋy����S���������A�n�[�v�ƃt�@�S�b�g�T�ȊO�͂��ׂẲ����������B �@�������݂�Ȃ̈ӋC���݂̍�����������������B���B�I���ɂ͐e�q�ŏ����l�ɋ삯���ĉ���������A�{���ɖ{�Ԃ��y���݂ł���B �@���āA�����o���O�ɁA�܂����搶���A�I�P�z�u�̑S�ʌ��Ē������āB���̐l���̂悳�ƋZ�p�̊m�����ō���v����I�P����R�̂悤�ɃG�L�X�g���̈˗������錻��t�҂̂��̃A�h�o�C�X�́A�����̂悤�ɉ����킩��Ȃ��A�}��I�P�ɂƂ��Ă͑�ς��肪�������̂������B���搶�́A�}�G�X�g����{�̈ӌ������Ȃ���A�Ȃ�ׂ����Ȃ��X�y�[�X�ʼn��t���W�����Ȃ��悤�ɋC��z��Ȃ���A���ꂼ��̊y��̔z�u���w���B�P�O���قǂ��āA���Ƃ�����Ȃ�̌`���ł����������B �m���ɁA��T�ɔ�ׂ�ƁA�����ǂ��e���₷�����ŁA�}�G�X�g�������̕����f�R�U��₷�����E�E�E�������I �@�z�u�����܂����Ƃ���ŁAtutti�J�n�I�@�����͗��K�ԍ��P�P�V�Ԃ���B�c���Ƃ��날�ƂW���̂P�B�}�G�X�g������ׂ̍����w���ɂ��Ắu�[�߂̗��K�K�C�h�v�ɔC����Ƃ��āE�E�Etutti�R��ڂƂ��Ȃ�ƁA�݂�Ȃ������ԁu�[�߁v�̕��͋C�����߂Ă����悤�ŁA��T�ɂ��܂��āA�����ɍ��킹���i��ł����B�O��Ɠ����悤�ɁA�v���v���ŋȂ��Ƃ߂āArit.��accel.�Ȃǂ̎w�����o�����B�����́A���搶�����邨�����ŁA�`�F���p�[�g�����q�ɂȂ邱�ƂȂ��A���Ă��Ă���B �����āA�R��ڂ�tutti�ɂ��āA�u�[�߁v�S�Ȃ�ʂ��I�����B �@���S����Ԃ��Ȃ��A���ɖ߂��ė��K�ĊJ�I�@���x�́A���悢��}�G�X�g���ɂ��O�ꂵ���F�t�����n�܂����B�ׂ��������̈��ɂ���������Ɖ��߂��Ȃ���A�w�����o����郁���o�[�̕����ƂĂ��������₷���A���̃C���[�W�ɋߕt����悤�ȉ����o�����Ɗ撣���Ă���B���ɗ��z�I�ȗ��K���i���W�J����Ă���I�@ �@���āA���̔�{tutti�܂ŏ������Ԃ����ǁA����܂łɌl��p�[�g�E�Z�N�V�����Ȃǂł���������K�����Ă������ˁI �@���݂̂�Ȃɂ́A���T�̕��t���K�ɔ����āA���搶����d�v�ȉۑ肪�o���ꂽ�B����́E�E�E�u���K���K�v �@���搶�H���A�u�[�߂́A���ʂÂ�͑O��̎l�G�Ȃǂɔ�ׂ�Ƃ����ƈՂ�������ǁA���̕��������������茈�܂��Ă��Ȃ��ƋȂ���f�B�[�̎��Ɠ��̕��͋C���o�Ȃ����肩�A�Ԃ��ɂȂ��Ă��܂��B����͉����ɑ��ăV�r�A�ɂȂ邢���@��B�������������܂���`�B������Ƃ��������Œe�����߂ɁA�܂��݂Ȃ����ׂ����Ƃ́A���K���K�ł��I�@�����ł��\���܂���A�Ƃɂ��������P�O���ł����K���K������ĉ������B����̕��t�ň�l���e���Ă��炢�܂�����A���̂���ŁI�v�Ƃ̂��ƁB �@����́A�������łȂ��A�ǂ݂̂�Ȃɂ������邱�Ƃ��ˁB����ς��b���K�͑厖����B������x���S�ɂ������āA���������Ƃ��납�炫��������܂��傤�I �@���ꂶ��A�܂��`�B |
| �Q�O�O�S�N�P���Q�S���i�y�j �@�@���P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�ytutti�z�@�I�y���u�[�߁v�@ �@�����I �G���W���S�J�`�H�I �@�����́A���K���ɓ����Ăт�����I�@�O����T���̂R���炢�̂�����̏��i���イ����j�ɐԂ��Ђ������꒼���ɒ����Ă���B����H����́H�H�@�܂����w��荇�����낤���Ă�H�@����ȃ��P�Ȃ������I �@�����I�@����́A�n�c�����s����قɖ₢���킹�Ċm�F�����I�[�P�X�g���s�b�g�̃T�C�Y�Ɏd���Ă���̂������B �O��A��{�搶���u�I�y���̃I�P�̔z�u�́A�ʏ�̃R���T�[�g�̂���Ƃ͑傫���قȂ邩��A���ǂ݂��ς�{�Ԃ̔z�u�ŗ��K����悤�ɂ��悤�v�Ƌ������Ƃ������������H�B���₢�`�B �@�ł��A���ڂ͂��Ȃ苷���`�B���̂P�v���g�ڂƂn��.���e��.�Q�{�����炬�イ���イ�B����ɂ́A�������ɔ�{�搶���u���ꂶ�Ⴀ�A�����牽�ł��e���Ȃ���Ȃ��v�Ƃ�ނȂ��A�Qnd Vn������Q��ڂɉ������̂ł����B �@�Ƃ���ŁA�����̓R���~�X�l�����ׂŃ_�E���B���`�B�E�E�E�������A�NJy��͂P���� Fg�ȊO�͑S���o�ȂƂ����P���Ƃ͎v���Ȃ����o�ȗ��I�I�i�e���̂l���D�t����́A�Q���W���̎s�t�B������̃G�L�X�g���o���ŖZ�����̂��B�}�[���[�̋��l�̂ق��A�g������h�̎��Ȃň��r���𗁂т��u��B�Ɓv������\���X�g�Ɍ}���ăx�[�g�[���F���̂u���R���`�F���g�������āI���Ԃ̓s�������l�͂��В����ɍs�����I�j �@���͊ǂقǂł͂Ȃ��ɂ��Ă��A��͂肢���̂��̎����ɂ���ׂ�Ƃ��Ȃ�̍��o�ȗ��ł���B���B�I���ɂ͂Q�l���G�L�X�g���̕����Q�����Ă��ꂽ���A�X�g�o�C�ɂ����͂ȏ����l�l������. S���삯���Ă���A�ق��I �@���āAtutti�̕��͂Ƃ����ƁA�O��̑����T�V�Ԃ���B�i�ׂ����w���ɂ��ẮA�u�[�߂̗��K�K�C�h�v�����ăl���j �@�O��̔�{�搶�̋ꌾ�������������悤�ŁA�݂�Ȃ̊፷���͐^�����̂��́B�搶�̃^�N�g�ɒu���Ă���܂��ƋC�����犴����B�����o�[���ꂼ��ɁA�Q���ԋ߂����邱�̃I�y���𑊓���������ł����l�q�E�E�E�B �@�}�G�X�g���̊������̏�M�Ƃ݂�Ȃ̐^�������Ԃ��荇���āAtutti�͑O��Ƃ͑ł��ĕς���ăX���[�Y�ɐi�s���Ă����B�v���v���ŋȂ��~�߂Ȃ���A�e���|�̕ω��ɂ��Ă�ǂ������V�[���̉��y�Ȃ̂��A�ǂ��������͋C���o���Ēe�����ȂǁA�}�G�X�g�������������Ă����B�����́A�P�P�W�Ԃ܂Ői��B�c�肠�Ə����B����ň�ʂ荇�킹�͏I��肻���B �@����ɂ��Ă��A�Ȃ�Ɗ��C��тт����K���i�ł��邱�Ƃ��I�@�v���Ԃ��A��N�Ăɐē��搶�����āA�����������������̂��A�H����~�ɂ����Ă̔�{�搶�̒Z�����[�������w���ł�������Ɛ������A���܂���{�搶�̎�ɂ��A�������荪��A�m���Ɏ������ڂ��Ƃ��Ă���\����������B�P�N���炸�̊ԂɁA����ȂɃI�P���ς��Ȃ�Ďv���Ă��݂Ȃ������I�I �@����Ȃɑf���炵���w���w�Ɍb�܂ꂽ���ƂɊ��ӂ��āA�݂�Ȃ��ꂩ����撣���Ă������ˁI �@���K�̍Ō�ɁA�搶������u�����́A�݂Ȃ�����I�[���������āA���ɂ悢���K���ł��܂����v�Ƃ��J�߂̌��t���������������Ƃ����ˁ`�� �@����֑����E�E�E �@�y��͕ʂ�̎n�߂Ȃ�H�z �@�c�̃��[�h���[�J�[�ł�����A�C���X�y�N�^�[�Ƃ����d�v�Ȗ����Ă����A�N�����l�b�g�̎R����Q�����{����_�˂ɓ]���邱�ƂɂȂ���������I�@�u��������A�����H�v�Ǝv�킸�c�b�R�~��������̂́A����͕�����Ȃ������B �@�����A�����B(T_T)�@�V���W�����i�C�A�W���W�^�N�i�C�B���ǁE�E�E�����̗��K��u���ʉ�v�������B�}�Șb�������ɂ�������炸�A��������̃����o�[���W�܂��Ă����B�R�����̐l�����Ȃ���Z�ł��낤�B����Ȃɂ݂�ȂɈ�����Ă�̂ɁA�s���Ă��܂��̂ˁA�R�����B�^�쉮�̎В��̃o�J�[�I�I �@�܂��A������t�ɖ߂��Ă��Ăˁ`�B�Č��B |
| �Q�O�O�S�N�P���P�O���i�y�j �@�@���P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�ytutti�z�@�I�y���u�[�߁v�@ �@�����������������̕ǂ��E�E�E�H �@����A�u�����͔�{�搶�ɂ��tutti�ɗ��K���e���ύX�ɂȂ�܂����v�ƒc���ɋً}�A�������ꂽ�B �@�������I�@�Ȃ�Ă������I�I�@�����o�[�̒��ɂ́A�ututti�͂Q�S�������炻��ɊԂɍ���������v�ƍ��Ƃ����蕈�ǂ݂��낭�ɂ��Ă��Ȃ��l�����邾�낤�B����ȏŔ�{�搶�����}�����邱�ƂɂȂ낤�Ƃ́I�I �@�����āA���K�����A�A��H�����Ƃ��ڂ����c�������߂ɉ��ɂ��ĕt���Đn�i�H�j�̖җ��K�E�E�E�ʂ����ĊԂɍ����̂��H �@�Ə�k�������Ă�ԂɁA��{�搶���o��B �@���K�ɓ���O�ɁA�I�y�������ۂ̐S�����X�����b���ĉ��������B �@�u���ɑ厖�Ȃ̂́A�I�y���͊F������Ă����V���t�H�j�[��I���g���I�Ƃ͈���āA�����ł̓�����i�s�ɍ��킹�ĉ��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�e���|�����ł͂Ȃ����A��ɗՋ@���ς���v�������B�܂��ɉ��y���̂��̂��������̂Ƃ����������ɂȂ�܂��B�܂��A�v���I�P�ł��ꍇ�́A�������x�����K�ł��Ȃ��̂ŁA�̂�����I�P�����݂�������x�̑Ë����������Ă��܂��B�ł��A����́A�̂���ɉ̂������悤�Ɏ��R�ɂł���悤�A�ނ�̌ċz��������������t���x���܂ł����Ă��������Ǝv���Ă��܂��̂ŁA�݂Ȃ����낵���I�v �@�ȁA�Ȃ�ƍ����u�I�@���܂łȂ�A���[�̂ō����n�j�Ƃ��������������̂ɁB�i���ɍ���̂悤�ɗ��K���Ԃ��Z���ꍇ�́j �@���������A�݂�ȁI�I�@�}�G�X�g���̗v���ɏ����ł���������悤�A����������K���悤�ł͂���܂��I �@�Ƃ�����ŁA�ׂ����w���ɂ��ẮA�g�o�Ǘ��l�̂r�����u�[�߂̗��K�K�C�h�v�Ƃ����y�[�W��݂��Ă���܂����̂ŁA�����o�[�͕K���`�F�b�N���Ăˁ� �@�t�q�k�Fhttp://www007.upp.so-net.ne.jp/ichihara/orchestra/yuzuru-guide.htm �@��{�搶�ɂ��ƁA���̗[�߂́A���̃��[�O�i�[�����p�����W�������g���C�g���e�B�[�t�h�Ƃ�����@���ӂ�Ɏg�p���Ă��邻���ł��B�g���C�g���e�B�[�t�h�Ƃ����̂́A�ȒP�ɂ����Ɠo��l���Ȃǂɂ��ꂼ��e�[�}���y����������Ƃ�����@�ŁA�Ⴆ�Η��K�ԍ��P�U����o�Ă���g�����{�[�����ጷ�͈����i�y�ǁ��^���j�̃e�[�}�A�T�R�̂�����͓s�̃e�[�}�A���ɂ����̃e�[�}����Ɨ^�Ђ傤�̈��̃e�[�}�݂����Ȃ̂�����܂��B�Ȃ�قǁ[�A�킩��₷�����I �@���̓��̗��K�́A��{�搶�̂������肵���o�g���e�N�j�b�N�̂������ŁA�S�̂̂R���̂P���炢�܂Ői�݂܂����B �@�݂�ȁA���ǂ݂��܂܂Ȃ�Ȃ���ԂȂ���A�K���ɐ搶�̖_�ɋ��Ă����Ă܂������A����p�[�g�����͑S���Ŗ��q������ԁB����ɂ́A�搶���u�ЂƂ������I���K�ɏo��Ȃ�A�Œ�����ǂ݂������Ƃ�����Ƃ��Ă��邱�ƁI�I�����łȂ��ƃI�P�S�̂ɖ��f���������Ă��܂��B�v�Ƃ��Ȃ�茵��������������Ă��܂����B���܂ł́A�����킹�͂���Ȓ��x�ł����ċ�����Ă�����Ȃ��B���Â��A���܂łǂꂾ���Â����K�����Ă��������߂Ďv���m�炳�ꂽ�肵�āB �@����́A����Ȃ��Ƃ̂Ȃ��悤�A�݂�ȋC���������߂Ă���낤�I �@�y��͂艊�̃}�G�X�g���H�I�z �@�����A���K�̋x�e���Ƀ}�G�X�g���̃X�R�A����Ă݂������o�[�ɂ��ƁA���łɏ������݂��т����肾���������ȁB�m���A�X�R�A���搶�̎�ɂ킽�����̂́A��N���̂͂��E�E�E�B�Ƃ������Ƃ́A�搶�͂������P�O���Ԃ��炢�̊Ԃɂ������܂ŋȂ��������A�i���[�[�����ƁH�@�Ђ��`�I�@�Ȃ�ӋC���݁B���y�ɑ���^���Ȏp���I�I�@ �@����Ⴀ�A�����o�[�݂̂�Ȃ�����������Ȃ���ˁ� |
�@![]() �i�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�j�@�@�@�@
�i�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�j�@�@�@�@![]() �ߋ��̓��L�������@�@�@
�ߋ��̓��L�������@�@�@![]() �ŐV�̓��L������
�ŐV�̓��L������