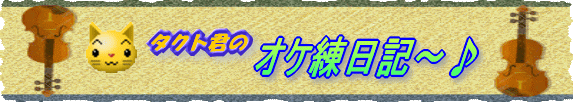
・このページでは、市原市楽友協会オーケストラの練習時における悲喜こもごもを楽しく明るく正直に?お伝えしたいと思います。
 ご意見・ご感想はこちらまで
ご意見・ご感想はこちらまで 
 (トップページに戻る)
(トップページに戻る)  過去の日記を見る
過去の日記を見る  最新の日記を見る
最新の日記を見る
それでは、さっそく・・・。
2003年12月14日(日) 第16回市民コンサート無事終了! 第16回市民コンサート無事終了!マエストロ樋本のみごとな手腕とみんなの熱意、そして優秀なソリスト・・・すべてがうまく融合して、信じられない奇跡が起きた! ハイドン作曲オラトリオ「四季」全曲(2時間強)を何とか無事に通せたのである。 もちろん、何箇所も危ないところはあったし、コーラスのバスがごっそり落ちてしまったりなど、ミスはあったものの、曲は決して止まることなく、流れ続けた。昨日は、あんなにダメだったレチタティーボも、居残り特訓の成果がばっちり現れている。あ〜、本当によかった。お客様も対訳を見ながら、曲を楽しんでくれていたようだし、まずまずの本番だった。 開演には、新市長の佐久間隆義氏も応援にかけつけ、短い時間ながらもお祝いのスピーチをして下さり、演奏会に花を添えて下さいました。思えば、10年前の市制30周年の時もハイドンのオラトリオをやったんだよね〜。 「天地創造」を抜粋で・・・しかも、今回と同じように客演指揮で。なんか、ハイドンには因縁を感じるなぁ。ってことは、10年後の市制50周年もハイドン作品でお祝いすることになるのかな? さて、ここで、打ち上げでの各先生方のコメントをご紹介しましょう! まずは、偉大なるマエストロの樋本先生から 「今日は演奏していて、オレ、今指揮者してるよーと思いました。いつもだったら、こんなにきっちり1,2,3,4なんて振らないのに、今日はもう、拍できっちり点を打ってたりして。(笑) それに、p(ピアノ)の時だって、体をかがめる指揮者を見てオーバーアクションだなぁと苦笑していたのに、今日は自分も無意識にそうやってました。(大笑) あと3,4回tutti練習やれたら、もっといいものができたと思うんだけど、まあ短い期間でこんな大曲をよくやりました。」 樋本先生には、打ち上げ開始直後にもコメントをもらったんだけど、ビールが入った2回目のこのコメントの方が超ウケました。 次に、バスの戸山先生 「実は、ボクは今年4月に“四季”を歌っていて、どんなにこの曲が難曲か知っていたので、話をもらった時、本気なのかと耳を疑いました。また、昨日の練習では、かなり不安にもなったりしましたが、無事に終わって、ほっとすると同時に、アマチュアって本当に怖いもの知らずだなぁと思いました。“四季”はオーストリアの田舎を歌った曲ですが、今日は偶然にもその田舎くささがうまい具合にでていたような・・・。(笑) みなさん、本当にお疲れ様でした。」 戸山先生は、一度歌っていただけあって、そりゃもう素晴らしいソロでした。 次に、ソプラノの本田さん 「私は、今ドイツに住んで音楽を学んでいますが、今回のソロでは、自分の学んでいるドイツ語がうまく活かせたらいいなと思って歌っていました。来年、楽友協会ツアーでヨーロッパにいらしたら、市内観光案内をしますので、ぜひ声をかけて下さい!」 本田さんは、これで3回目の出演かな? 回を追うごとに、着実に進歩されていて、しかも美しくなっていらっしゃるような・・・今回は、肺炎を患ってしまった中での苦しい本番だったにもかかわらず、そんなことはおくびにも出さず美しいソロを聞かせて下さいました。 そして、樋本先生、Y先生、ソリストのみなさんの恩師である原田茂生先生もいらしていて、感想を述べてくださいました。 「私は、今年偶然にも“四季”の批評を書いてくれと依頼があり、あらためて聞いて、これは素晴らしい曲だと思ったけれど、ものすごく大曲でもあって、康童くん(Y先生のこと)から話があった時は、半信半疑だった。知らないということは、時には強みにもなって、アマチュアゆえにこんな大胆なことができるんだなぁと恐れ入りました。樋本君の指揮者ぶりも見ることができて、本当にいい一日でした。」 最後に、Y先生 「“四季”がこんなに大変な曲だとは知らずに、合唱の団長から次は“四季”でいきましょうと言われた時に、合唱は次回公演まで1年半あるし、何とかなるかなと簡単にOKしちゃったけど・・・いやあ〜、本当に大変でした。自分自身もちょっと甘く見ているところがありました。これからは、もうちょっと選曲には慎重になりたいと思います。(苦笑)」 今回の演奏会は、オケにとっても合唱団にとっても、とても思い出深いものになりましたね。ありがとう、マエストロ&ソリストのみなさん! オケは引き続き、3月の「夕鶴」で樋本先生の指導が受けられるね!! 「夕鶴」は「四季」以上に難曲かも・・・。お正月休みの間に、各自しっかり譜読みをしよう! とにもかくにも、みなさんお疲れ様でした。 |
| 2003年12月13日(土) *13:00〜21:00 【セッティング&ゲネプロ】 炎と執念のマエストロ、その名は・・・Mr. Himoto?! 予定通り、13時に団員は集合し、せっせとステージ作り。今回は、合唱団のメンバーもいるため、準備は着々と進んだ。そして、tutti開始予定の14時には、エキストラを含むオケ・メンバーがステージにスタンバイ、ソリストを迎えてのレチタティーボの合わせが始まった! ・・・が、悪い方の予想が当たり、しょっぱなから足並みが揃わず、バラバラボロボロ。これで明日の本番に間に合うの?とタクトの胸は早くも絶望に包まれていくのだった。 しかーし、マエストロ・樋本は全く動じる様子もなく、淡々とtuttiを進めていく。限られた時間を最大限に生かし、着実にオケを一つにまとめていく。まさに、これは、マジックだ!! レチタティーボの後は、合唱団も加わってのゲネラル・プローベの始まり始まり〜♪ あまりにも長大な曲なので、通しで演奏するのは、今日が初めて。うまく流れるだろうか? 泣いても笑っても通しで練習できるのは、今日のこの時間しかないのである。みんなの表情にも緊張の色が。 そして、「春・夏」・・・何曲か、出だしでテンポがとれず、危ういものがあったが、まあ何とか通る。 休憩をはさんで、「秋・冬」・・・テノール・ソロで出演のY先生、今一つといった調子。さっき合わせたばかりのレチタティーボでややてこずりながらも、一応最後まで通る。 当初の予定では、このあと1時間食事休憩をとって、再び練習の予定だったが、マエストロは「ソリストさん、管楽器及び合唱団のみなさん、お疲れ様でした。今日は、これでおしまい。弦楽器のみなさんは、申し訳ないけど、もうちょっと残って練習です。」とおっしゃった。管楽器や合唱団のメンバーの中には練習し足りなそうな顔をした人もいたけれど、鈴木会長差し入れのまだ温かさの残るおにぎり2個を手にステージを降りた。 弦メンバーは、すでに相当疲労している様子だったが、マエストロの執念の特訓に文句一つ言わず、必死に喰いついていた。1時間半休憩なしに練習は続けられたが、マエストロもメンバーも最初から最後まで恐ろしいほどの集中力で、ステージ上には他を寄せ付けない迫力がみなぎっていた。 その練習風景を見ていたら、タクトはなんか感動してしまって、涙が出そうになっちゃったよ。 みんな、本当にお疲れ様。明日は、いい演奏ができるといいね。 |
| 2003年11月30日(日) *9:30〜12:15 【tutti】 ハイドン「四季」 個人練あるのみ!! 4回目の樋本先生によるtutti。やらなきゃいけないところはいっぱいあるのに、今日は午前しか練習時間がない! 出席したメンバーからは、先生の言葉を一つも漏らすまいというような気迫めいたものさえ感じる。非常にいい感じの緊張感がある。たった3回のtuttiでオケをこんなにも変えてしまうなんて、樋本先生の手腕、おそるべし!である。これぞ、プロ中のプロってことか・・・。 さて、今日は限られた時間の中でどんな練習をしたのか、さっそくお伝えします。 まず、この長いオラトリオのオープニングとなる春の序奏からtuttiが始まりました。 ・冒頭の伸ばしの音は、弦・管ともずっしりしっかりとした音で。最後のディミヌエンドでppに。 ・掛け合いのフレーズ、出遅れないで、上手に会話して。 ・どの部分も、音が軽くならないように、また、fzをうまくきかせて、フレーズ全体にうねりを持たせて。 ・レチタティーボからは、拍どおりにはやらないので、拍を数えない。指揮を見て、合わせる事。 次に、夏の「嵐」の曲 ・ヴァイオリン群の細かい音の動きは、曖昧にならないよう音程まできっちりさらっておくこと。 (本当は、一人ずつ弾かせて注意を与えたいところだけど、もう時間がないから・・・とマエストロ) ・管楽器は、もっと音程に注意して。 次は、後半の幕開けとなる秋の第一曲目。 ・付点のリズムの弾き方を工夫して、弾むような感じで。 ・それぞれのフレーズがイキイキと活力の満ちたものになるように。 そして、休憩をはさんで、秋の目玉(?)、ホルン大活躍の26番。 ・冒頭のホルンは同じ音の連続になった時にテンポをひきずらないように、前へ前へ進む感じで。 ・ここでも、細かい音の動きが続くパートはしっかり個人練をして、かちっとはまるように。 ・装飾音符は拍の頭にうなるような感じではっきり入れる。 次は、秋の最後の曲 ・音の出だしをはっきりと。 ・8分の6拍子になってからの動きは急がない遅れない! 急ぐ人、遅れる人様々いるので、全体ではバラバラのメチャクチャ。まずは、拍の頭で合わせるように意識しよう。(でも、アクセントはつけないように) ・後半はシンコペーションの形をはっきり出して、曲が進むにつれて、どんどん盛り上げていって頂点で曲がおわるように。 次に、このオラトリオの締めくくりとなる冬の終曲 ・ここでのリズムは固めに、かっちりきびきびとしたイメージで。 ・C−durのハーモニー、もっと音程を正しく、きれいに響かせて。 (C-durは完全無欠と言える調なんだから、もっともっと開かれた響きがするはず!) 残り15分で、冬の最初の曲をやりました。 ・臨時記号のついた音をすこし低めにとって。 ・曲の持つ雰囲気をもっと感じながら、一つ一つの音を丁寧に! ・p、ppを忠実に守って!! 全体を通して言われたことは、細かい動きの部分はまだまだ個人練が必要なこと、音程に対してもとシビアな耳を持つことでした。 樋本先生曰く、「みなさん、それぞれに仕事があって、なかなか練習する時間がとれないこともよくわかっています。それでも、よりよい音楽を演奏するために、私はみなさんにもっとさらって下さいと言うしかありません。」と。 険しい道はまだまだ続く・・・。 あ、それと、みんな、今のうちから、しっかり体力つけておいてね! 特に弦楽器のみんなは、「秋」の中盤でばてないようにしっかりお願いします☆ |
| 2003年11月24日(月) *9:30〜16:45 【tutti】 ハイドン「四季」 午前:オケのみ 午後:合唱合わせ アンサンブル〜!! さあさあ、今日は、樋本先生による3回目のtutti。午後は合唱合わせもある。 みんな、体調は万全かな? 今日は先生をがっかりさせないようにという意気込みからか、みんな早くから練習場に来て、個人練習に励んでいる。どのメンバーも目の色が違う。真剣そのもの。う〜ん、この緊張感、いいねー。やっぱり、練習はこうでなくっちゃ! 午前中は、前回やり残したレチタティーボ&アリアの部分の合わせ、午後は合唱合わせをやりました。 今日も樋本先生から、様々な注意や指摘を受けたけれども、どれも頷けるものばかりだった。 また、興味深い話などもあったので、箇条書きにまとめておきまーす! ・「オラトリオ」は、オペラを禁止された当時の人々が生み出した苦肉の策の“エンターテイメント”。舞台装置は一切使わないので、音でものや情景などすべてを表現しなければならない。ハイドンは、そういう点ではまさにうってつけの作曲家で、この「四季」では彼の素晴らしい才能が余すところなく発揮されている。しかし、それを演奏するのは本当に難しい。何しろ、音のみで聴く人に伝えなければならないんだから。だからこそ、みなさんは、もっともっとこの曲をよく理解して演奏に臨まなければいけません! ・後から練習に加わってきた人が、せっかく出来上がってきたアンサンブルを壊すようでは、困ります。後から来る人ほどしっかり練習してきてもらわないと。 ・体を動かして拍をとるのはやめましょう! 自分のテンポになっちゃってて、みんなと合わなくなるんだよ。それに、音楽もフレーズも細切れになっちゃう!! 拍は、体の中(お腹)で感じればいいんだ! ・楽譜にかじりついてないで、もっとしっかり指揮を見て、呼吸を合わせて! ・みなさんの音楽は重過ぎる。もっと前へ前へ進むような感じで! ボクがこんなに大汗かいて必死にタクト振ってるようじゃダメなんだよ〜。 ・自分自身が楽しむんじゃなくて、もっと聴いている人に伝えようと言う強い気持ちを持って! ・ボクらは、音楽をやっているんだ。どんなに短い音符でも絶対に気を抜いたり、投げやりに弾かないこと。 う〜ん、樋本先生にかかると、果てしなく長いなぁと感じられた「四季」という曲が、とてもドラマティックでワクワクしたものに変わる。本番がとっても楽しみになってきたゾ〜。 しかし、その前に、演奏するみんなは越えなければならないハードルがたくさんあるけどね。 とにかく、残り3週間、さらにさらに頑張っていこう!! キタイしてるよ☆ |
| 2003年11月22日(土) *18:30〜20:40 【分奏】 弦:磯野先生 管:個人練習 今日は、磯野先生による弦練。前回樋本先生のtuttiで指摘されたところをきっちり復習するため、まずチェロ・パートのみを特訓していただいた。まだまだ、ひよっこのような楽友協会チェロパートに対し、磯野先生は呆れることも声を荒げることもなく、終始、噛んで含めるように懇切丁寧、熱心に指導をしてくれた。 後半は、弦全体の合わせもみていただいた。これで、2日後に迫った樋本先生のtuttiへの準備は万全・・・と言いたいところだけど、曲が曲だからねぇ〜。まだまだ、見ていただきたいところは、山ほど残ってる。でも、今日は、もうすでに時間切れ。残念。 でも、磯野先生のエネルギーがみんなに伝わって、弦のメンバーは随分元気付けられたみたい。よかったー。 さすが、磯野先生! これからも、楽友協会の弦をよろしくお願いします〜♪ |
| 2003年11月16日(日) *9:30〜15:45 【tutti】 ハイドン「四季」 ピンチこそチャンス! る、る、るんるんるん〜♪ 今日は、樋本先生による2回目のtutti。どんな練習になるのか楽しみ楽しみ☆ 午前中は、トランペットの出番がある曲を優先して合わせ。前日、Y先生による合唱合わせでもやったし、その前2回の練習でも合わせていた曲ばかりなので、わりと順調に進んだ・・・かな。 弦楽器群は、八分音符の弾き方から直されていた。「無造作に弾かないで! もっと一つ一つの音にきちんと響きを持たせて!!」など、とにかく、どんなに短い音符であろうと常に音楽を要求される。う〜、なんか久々の緊張感。ワクワク、ぞくぞく。 午前中は、まあまあの滑り出しだったので、午後もさぞや充実した楽しいtuttiになるだろうと思っていたんだけど・・・ところがところが、午前中やった以外の曲は、これまで1〜2回しか合わせたことがなく、午後の練習は大いに紛糾。時間を経るごとに雰囲気も次第に重苦しいものになっていった。 樋本先生は、「単純なかけあいのアンサンブルが出来ていない! 演奏の大前提となる楽譜にある強弱ができていない。何よりも音楽をしようという意識が感じられない。」と曲の途中で何度も止めて、地団駄を踏んでおられました。ひょえ〜、これは、とてもまずい状況。 練習が終わると、樋本先生は悲壮感を全身に漂わせながら、団長の車で送られて行きました。メンバーのみんなも、先生の要求に応えられなかった不甲斐なさにがくっとうなだれているのでした。 本番まで一ヶ月を切ったと言うのに、こんなことで大丈夫なのか・・・いや、大丈夫な訳がない! 確かに、今回の「四季」の弦楽器は、パート譜が50ページ近くもある、2時間を超える大曲。練習しても練習してもなかなか追いつけるものじゃないよね。ましてや、普段はなかなか楽器を持つ時間さえままならないのだから、なおさらきつい。でもさ、何も楽器をもってやるのだけが練習じゃないよね? 音出しが無理な時間でも、CD聴きながら譜読みをすることはできるし、もっともっと自分の中に「四季」という曲をしみこませるように、可能な限りの努力を試みよう! それから、「四季」の解説にも必ずしっかり目を通すようにしようね。自分が弾いている曲が何を表現しようとしているかがわかったら、イメージが膨らんできっと音に繋がっていくと思うよ。そうすれば、樋本先生の要求している“音楽”的な音に近づけるはず。 練習時間が残り少なくなってしまったけれど、最後の最後まで努力することを忘れずに、少しでもよい演奏ができるよう、がんばろうよ、みんな! なんか説教くさい内容になってしまったけれど、これはタクトからみんなへのエールだよ!! ファイトォ〜。 |
| 2003年10月11日(土) *18:20〜20:40 【tutti】 ハイドン「四季」 今日は、次回の樋本先生のtuttiに備えて、先週やらなかった曲を山本先生の指揮で合わせた。 初合わせの時よりは、形になってきたけれど、やっぱり音程が〜! それに、まだまだ楽譜を追うのに精一杯って感じで、それぞれの曲が持つニュアンスが全然伝わってこないよ〜。 むむむ・・・みんな、CDの曲目解説は必ず目を通そうね! そしたら、もっともっと楽しんで演奏できるようになるはず。 今日の合わせでは、若干弾き方・吹き方を修正しただけで、終了。何しろ曲数が多いから。それでも時間がいっぱいいっぱい。突っ込んだ練習をしたくても、なかなか・・・。(^_^;) 今後の大目標:1.音程、もっとシビアに!! 2.fz(フォルツァンド)の音が汚くならないように! 3.ザッツを揃えましょう!(←前からずっと言われ続け) 4.音が浮かないように。 5.後ぶくれにならないように。 「2時間があっという間だった」というような演奏ができるよう、ひたすら練習でござるよ〜。 そいじゃ。 |
| 2003年10月4日(土) *18:20〜20:40 【tutti】 ハイドン「四季」 樋本先生のバトン・マジックにタクト、敬服!! あはは・・・またもや一ヶ月ぶりの日記となってしまった。(^_^;)←笑い事じゃない! 9月21日の「アンサンブル・フェスタ」は無事に終わりました〜。出来は・・・まあまあってところかな。 さて、今日は、Y先生ご推薦の12月の本振り指揮者樋本先生による初tuttiである。芸大の講師であり、ふだんプロオケばかりを相手にされている先生にとって、今日はかなりのカルチャーショックとなるかもしれない。 何しろ、みんなまだ譜読みさえ怪しい状況なんだもん。う〜〜〜、やばっ! などと心配している間に、Y先生とともに樋本先生登場! が、あいさつもそこそこに樋本先生はtuttiを始められた。一分でも時間が惜しいというところか? さて、最初の3小節で早速弦のボーイングに鋭いチェックが入る。「ここは、もっと重々しい感じで、こういうボーイングでいってみましょう。」 さすがY先生が、「歌のことも楽器のことにも詳しい素晴らしい先生」と絶賛していただけある。この後も非常に的確な指示で、オケ全体の音がみるみる変わっていく。 「ここの部分は、水の流れをイメージして!」「オーボエのうずらのあと、フルートのこおろぎね」「はい、牛の声〜」と実にわかりやすく、ユニークな指導が続く。樋本先生が言葉を発するとみんなの音に命が吹き込まれていくような感じさえする。これぞ、プロフェッショナル!! 最初、緊張気味だったみんなの顔にもしだいに笑みがこぼれ始め、「四季」という曲の持つ楽しさがどんどん伝染していくみたいだ。 が、しかし、随所で悲鳴にも近い「音程〜」の声も連発されちゃったね。 アマチュアの泣き所・・・“音程”。こればっかりは樋本先生もおっしゃっていたように個人個人でシビアに取り組むしかないからね。次のステップに上がるためにも、しっかりガンバロウ! tuttiの後、樋本先生があらためて自己紹介をされた。 「今、合わせてみて大体わかったと思いますが、まあ、こんなヤツです。どうぞよろしく。最初にいろいろ自己紹介をするより、実際に音を出してみて、音楽を通しての方が、早くお互いをわかりあえると思いまして・・・。」 な、な、なんて素敵なお言葉! なんか、ファンになってしまいそう。 という訳で、今日の練習は、とてもとても内容の濃いものとなりました。あ〜、次回が楽しみ☆ 【親子共演】 今年のアンサンブル・フェスタの楽友協会オケのステージには、 何組かの親子が共演していたのだった。 印象的なのは、1st Vnの大野さんとVlaで参加した大学生のお嬢さん。Vlaは普段から人手不足だっただけに大変嬉しい助っ人の登場だった。 そして、今度の「四季」にも親子共演が見られそう。Vlaのひらポンさんの息子さんはなんとOb吹き! いつもパートナー探しに苦労していたミドリちゃんにもオケにとっても、またまた心強い助っ人の登場。さっそく今日のtuttiに参加してくれたんだけど、そりゃもう柔らかい素敵な音色で・・・タクト、うっとり〜。 これからも、楽友協会のステージでどんどん親子共演が見られるといいなぁ。 |
| 2003年9月13日(土) *18:30〜20:40 【分奏】 弦:モーツァルト「ディヴェルティメント」 管:個人練習 鬼のかく乱じゃないぞ! 一ヶ月ぶりの日記でござる〜。 じ、じ、実は、タクトはこの夏“水疱瘡”になってしまったのだー!! ドクターから自宅安静を厳しく言い渡され、練習はおろか、お出かけもままならないつら〜い夏休みを過ごしたのでした。うっく。(T-T) 漏れ聞いた話によると、8月30日(土)のtuttiは、前回の続きの12番からだったそうな。 出席率もかなりよかったらしい。でも、とにかく合わせただけって感じで特に何か指摘があったとか、重要と思われるような注意などはなかったらしい。 ただし、24番がかなり速くて、それは強烈な印象だったらしい。(誰から聞いたんだ?) 結局秋の最後くらいまでしか進まなかったと。やはり「四季」全曲は無謀な試みであったか・・・。 ふと胸をよぎる不安。いや、頑張り屋のみんななら、きっと・・・。 てな訳で、ようやくタクト、復帰〜。 ちなみに、今日の練習は、来週の日曜本番の「アンサンブル・フェスタ」に向けて、ラスト・スパート!! 今年も楽友協会オーケストラ・ストリングスには、可愛らしいおチビちゃんたちが参加。モーツァルトは難しそうだけど、みんな頑張っているよー。先週は、磯野さんの熱意あふれる楽しい弦練もあったしね☆ 管楽器の方は、三重奏で細々(!)と出演するらしい。 さてさて、どんなステージになるのか楽しみだぁ。 じゃ、また。 |
| 2003年8月9日(土) *18:30〜20:40 【tutti】 ハイドン「四季・春〜夏」 Y先生、仰天・タジタジ〜!! 昨年12月の本番以来のY先生のtutti。四季の初合わせでもあるこの日、団長から全員参加のお達しが回っていたこともあって、出席率は上々〜。しかし、コンミス様はお休み。 いつもなら、この時点で、tuttiとは名ばかり、Y先生のピアノに合わせて、延々と弦楽器の音取り大練習、管楽器メンバーげんなりという状況が想像できるのだが・・・ところがところが、今や楽友協会はそんなヤワ(?)なオケではないのである。 今までの初tuttiとはうって変わって、初合わせとは思えないくらい、しっかりした音が弦からも管からも出ているのである。(よそのオケでは、こんなの普通のことなんだろうけど・・・) もちろん、細かいパッセージなどはごまかしごまかし状態ではあるが、要所要所できちんと音が合い、止まることなくtuttiが続いていく。この成長ぶりには、Y先生ビックリ仰天! 「みんながこんなに弾けると思ってなかったから・・・」と苦笑い。 ふふん。この半年間、最初こそちょっとギクシャクしていたものの、優秀な指導陣に囲まれ、みんな今までにないくらいそれぞれが練習を積んだのさ。もう、ボクらは昨年までの“のほほん”としたボクらじゃない! 見くびってると痛い目にあうぜ〜。なーんちゃって。(^^ゞ 「それじゃあ、合わせられる所までどんどん先へ進みましょう。」という訳で、その日早くも「夏」まで突入したのだった。次回、30日は、12番からだよー。 さて、本日のY先生からの注意事項は2つ。 ・音が後膨れにならない。(人によっては、後押しとも言う) ・地面にめり込むような音を出す。(音が軽くならない) う〜ん、2点とも以前からずっと言われ続けてることだね。一人一人が注意して早く同じ事を言われないようになろうね。 それじゃ。 |
| 2003年7月27日(土) *18:30〜20:45 【分奏】 弦:モーツァルト「ディヴェルティメントへ長調KV138」&ハイドン「四季・春」 管:個人練&「四季・春」の合わせ 異例の・・・!? 本番が無事に終わって、ホッ。 タクトもしばし夏休み〜♪と思っていたんだけど、今日練習場をのぞいてみて、びっくり! 本番翌週にしては、異例の高出席率!!なのである。 しかも、今期入会の新人さんが多い。管楽器の女子高生4人も全員出席。みんな、楽器が好きなのねぇ。 新人さんの中でも、特に熱心なのが、本番直前に入団した2nd Vn.のツリイさん。いつも練習場に一番乗り! そして、念入りに音出しをしている。「思う存分楽器を弾けるいい機会(場所も含めて)だから、有効に使わないともったいないっスよ!」とニコニコ顔でさらりと言っていた。オ〜、まさにおっしゃる通り。毎月初、真夜中に決死の思いで施設予約しているメンバーの苦労も報われるというものだ。 さて、練習の方はというと、弦はコンミスが中心になってのアンサンブル・フェスタ&四季の練習。モーツァルトのディヴェルティメントは2nd Vn.がちょっと難しそうだけど、一通り通してみて、曲の雰囲気はわかったんじゃないかな。後半、「四季」の「春」をやっぱり一通り合わせてみたけど、こちらはそれぞれの曲を把握するまでに時間がかかりそう・・・しっかりCDを聞いて、まずは曲を覚えないとね。また、ヴァイオリンはハイドン特有の早いパッセージがこれでもかこれでもかと言うほど現れるので、個人個人での地道な反復練習が必要だね〜、はぁー。 それはともかくとして、今年思い切って新体制で臨んだ成果か、昨年までの音とは明らかに違ってきている! 一人一人の音が格段によくなっている。 これは、おそらく、磯野先生による的確なアドバイスと、練習当初、混沌としていた音を、時には厳しすぎるくらいの指摘できっちりまとめあげたマエストロSaitoの指導がしっかりと実を結んだものと思われる。 そして、管の方も、9日に予定されている初tuttiに向けて、それぞれ譜読みに余念がない。人数もそれなりに集まっていたので、後半40分で「春」の部分を合せてみた。ドヴォ7に比べると非常に合せやすかったみたいだけど、まだどれがどんな曲だか・・・これからが大変そうである。こちらも丸山先生による指導のおかげで、それぞれの音に芯が出てきたと言うか、初合わせとは思えないくらいしっかりとした音が出ていた。 本当に、マエストロSaito&丸山先生・磯野先生には、感謝・感謝でございます。 お三方、今後もぜひよろしくお願いいたします! では、また来週〜♪ (更新されるかどうかは・・・まだ不明) |