�@�@�@�@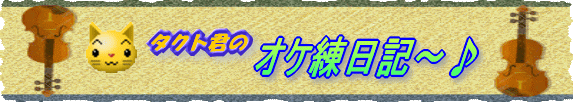 �@�@
�@�@
�E���̃y�[�W�ł́A�s���s�y�F����I�[�P�X�g���̗��K���ɂ�����ߊ삱���������y�������邭�����ɁH���`���������Ǝv���܂��B
 ���ӌ��E�����z�͂�����܂�
���ӌ��E�����z�͂�����܂� 
�@�@ �i�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�j �@�@�@�@
�i�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�j �@�@�@�@ �ߋ��̓��L�������@�@�@
�ߋ��̓��L�������@�@�@ �ŐV�̓��L������
�ŐV�̓��L������
����ł́A���������E�E�E�B
�Q�O�O�U�N�V���X���i���j�@ �@��Q�P��s���R���T�[�g�A���悢��{�Ԃł��I �@��Q�P��s���R���T�[�g�A���悢��{�Ԃł��I�@ �@�Q���̉��{���珬�ѐ搶�A�����Ĉ��g���[�i�[�̎w���̂��ƁA���K��ςݏd�˂Ă�����Q�P��s���R���T�[�g�A���悢��{�ԓ����ƂȂ����I�@�����͂ǂ�ȉ��t��ɂȂ邩�ȁH�@�ł��グ�Ŕ��������������ۂ߂邩�Ȃ��H�@���x�}���Ă��{�ԓ����̓h�L�h�L�� �@���āA��N�ʂ�X���R�O���Ɋy���ɂĒc���̓_�āi�I�j�y�уG�L�X�g������̂��Љ�B�P�O���P�T������Ō��tutti���K�J�n�B�̗͂̉������l���Ă��A�����ł͍���̃Q�l��v���Ő搶���C�ɂȂ��������݂̂��s�b�N�A�b�v���Ă܂ݗ��K�B�ʂ��͂Ȃ��B���̂��������{�搶�Ɠ��������B�x�搶�Ȃ�A��ΑS�Ȓʂ��Ƃ��낾���ǁE�E�E���āA���ꂪ�g�Əo�邩�A���Əo�邩�H�I�@����`���B(>_<) �@�قڃC���y�N����̃X�P�W���[���ʂ�A�P�Q��������Ɖ߂��ɗ��K�I���B���H�x�e�̌�A�{�Ԃ����`�I�I �@�y�V���ƒn���z �@�I�[�v�j���O�Ƃ������ƂŁA�p���[�S�J���Ċ����B�\���̃g�b�v�o�b�^�[�i�I�j�A�j����̂b���\�����o�b�`�����܂�A�������c���l�����������̃I�[�{�G�\���A���g���[�i�[�̂����ɂ������ď���I�ȃ`�F���\���A�R����~�X��̂u���\���Ǝ��ɋC�����悭�o�g�����n���Ă����E�E�E�����āA���X�g�X�p�[�g�A�L���ȃt�����`�E�J���J���̉��y�B����`�A���̂������n�C�X�s�[�h�I�I�@�����Ȃ�Ƃ����N���~�߂��Ȃ��B���ѐ搶�A�w����U��Ȃ���唚�B�܂��A�y������Ⴂ�����H�I �@�y�������킪�c����胂���_�E�z �@�w���_���\����O�ɁA�t���[�g�p�[�g�̃����o�[�Ɂu���������ă����V�N�I�v�Ƃ�����݂𑗂鏬�ѐ搶�B�o�����̃t���[�g�������_�E�̗���̌��������Ă��邩��ˁB�ӔC�d�傾�B�����ْ����[�h�Ȃ���A�s���s�y�F����́u�����_�E�v�͂������Ɨ���n�߁i�N�H�u�{�V�삾�[�v�Ȃ�Č����Ă���l�́I�j�A���X�����͂��������̂́E�E�E�����Ō�܂ŗ��ꒅ���A�`���A�`���B �@����̃v���O�����̒��ōł���ȂŁA���~��������荹�����ꂽ���̋ȁA���ɉ��t�������I�@����́A���M�̈�ɂ��Ă����Ǝv���B�i�Ə��ѐ搶���ł��グ�ł���������Ă����B�j �@�y���������h�i�E�z �@���ѐ搶�̍��肪�ӂ��ƕ����ƁA���@�C�I�����̃g���������Â��ɖ�n�߁A�z�����̂������Ƃ��������f�B�[�������E�E�E�D���ȃ����c�̎n�܂�`�B���q�l���悭�m���Ă���Ȃ����ɁA�Ō�܂ŋC�͔����Ȃ��I �@�Ȃ�ċC�����͕K�v�Ȃ��������ȁB�Ƃɂ����A�C�����悭�����c������Ă������B �@�y�����ȑ�W�ԁz �@�Q�y�͂ł�����Ƃ����g�������������̂́A�����������悢���t�������Ǝv���B�V���ƒn���̌㔼���l�A�S�y�͂œ˂������Ȃ����Ƃ������O�����������ǁA����Ȃ��Ƃ͑S���Ȃ��A�u��ɗ�ÂɎ��������߂�ڂ����킸�ɉ��t���ĉ������v�Ƃ������ѐ搶�̌��t�ʂ�A�ߔN�ɂȂ��n�ɑ��̂������t�ƂȂ����B�A���P�[�g�̒��ł����̋Ȃ������Ƃ��D�]�������̂����Ȃ�����B �@���芅�т̒��A���ʂɏ݂��������āA���ѐ搶���Ăюw����ɏオ��A�A���R�[���u���̈��A�v�i�G���K�[�j�B�������S�y�͂̌�ɁA�����Ƃ肵�����̋Ȃ͐▭�̑I���B�i�E�߂Ă����������̂͏��ѐ搶�B�G�N�Z�����g�I�j�@�����āA�����Ƀh�������[���������A�u���f�b�L�[�s�i�ȁv�B���ƈ�̂ƂȂ��āA������Q�P��s���R���T�[�g�͏I���B�݂Ȃ���A�����l�ł����B �@���ѐ搶�A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�����āA�A�A���ꂩ����܂���낵�����肢�������܂��I�I �@�s�s���s�y�F����I�[�P�X�g���̃j���[�E�X�^�[�E�v���C���[�a���I�H�t �@����̉��t��ɂ́A���ɂU�l���̐V�l���f�r���[���ʂ������̂����ǁA���̑��ɂ܂��e�B�[���G�C�W���[�Ȃ���A���̃��C���ȃg�b�v�̑���ߐ����I�[�{�G�̃J�i������B���T�C�h�̂��o���ܕ��ɏ������Ȃ���A�����ɐ��������A�g�����y�b�g�̃q������ɑ����y�F�I�P�̃X�^�[�E�v���C���[�ƂȂ����̂ł����B �@����̉��t��ł��A�N�̊�������҂��Ă��܂��I�I |
| �Q�O�O�U�N�V���W���i�y�j�@�Q�l�����E�v���[�x �@�u�����傱�v�ƃr�[���́u�W���b�L�v�H�I �@��N�E���N�ƉẴI�P�P�ƌ����́A�ߖ�ɐߖ���d�ˁA�o����l�߁A�`�P�b�g����グ�̓w�͂����E�E�E���̍b�゠���ĂQ�N�����č�����v�������̂ŁA���N�͎v�����đO���̗[������z�[�����m�ہI�i�c���̑�p�f�I�I�j�@����́A���t����݂�ȂɂƂ��āA�S���I�ɂ��傢�Ƀv���X�ɂȂ����Ǝv���B �@�P�R������P�U���߂����炢�܂ŁA��]�҂݂̂����̎s�����N��قŌl���K�B�P�V���߂��ɖ{�ԉ��ł���s���s����قɏW�����A�����Z�b�e�B���O�J�n�B�����Ȃ���A�Z�b�e�B���O�͂��������o�[�ɂƂ��Ă͂���̂��̂ŁA�Ă��ς��Ɛi�s�B�\���肸���Ƒ����Z�b�e�B���O�����B���������`�I�@������O�l�A�ߖ�̂��ߕ��ʑ���e�����Q�Ƃ����̂��悩�����݂����B��ق̏d�����ʑ���^�Ԏ�ԂƎ��Ԃ��啝�ɃJ�b�g�ł����B �@�����āA�P�W���R�O���A���d���⏔�X�̎���łǂ����Ă�����Ȃ������o�[����������̂́A�قڑS���������āA���K�J�n�I �@�u�Q�l������v���[�x�̌��t�ʂ�A�i��������Ė{�ԓ��l�ɐi�߂Ă����܂��B�v�Ə��ѐ搶�B �@�܂��A�I�P�S���ŗ��^�C�~���O����`���[�j���O���ǂ��œ���邩�܂ŁA�Ƃɂ����Ȗ��Ɍ��߂Ă����A���ɉ����̃`�F�b�N�B���ѐ搶�͎w����U��Ȃ���q�Ȃ֍~��A���ǂƌ��̃o�����X�����₭���f���A���y��S�̂̔z�u���O�O�b�ƃX�e�[�W���ֈړ��������B���̂�����̒i���́A��{�搶�̕��w�������x�����߂Ă��邾�������āA����������I �@�����������āA���悢��Q�l������v���[�x�̎n�܂�n�܂�`�B �@��T�̗��K�Œʂ����K�͂������̂́A��͂肢���̗��K���Ƃ͉��̋������A����⎩���̉��̕����������܂�ňႢ�A���̌˘f�������딽�f���Ă���悤�Ȃ������Ȃ����I�n�������鉉�t�������E�E�E�B �@���ѐ搶����́A�u�����̗��K��ꂪ�g�����傱�h�Ȃ�A�����͂��Ȃ���r�[���́g�W���b�L�h�ƌ������Ƃ��납�ȁB�����݂̂�Ȃ̉��t�́A���̂����傱�̂����𔖂߂āA�W���b�L�������ς��ɖ������������B�ł��A�{���͒��̂����̎��͗��Ƃ������Ȃ���ˁH�@�����͂�������ȏ�tutti�͂��Ȃ��̂ŁA������tutti�܂łɊe���łǂ�������������������ŃW���b�L�������Ƃ��ł��邩�A�l���Ă݂ĉ������B�v�Ƃ̌��t�B�����A���Əd���h����������������Ƃ��E�E�E�B�ł��A��N�܂ł͓����̒��������ƃZ�b�e�B���O���āA�Ō�̍��킹���K�����āE�E�E�Ɖ����Ɋ����܂��Ȃ��{�Ԃ������B����ɔ�ׂ��炸�[���ƌb�܂ꂽ����ˁB������肢�����t���ł�����͐����Ă����A����͂����撣��Ȃ�����I �@�Ƃ������ƂŁA�����̖{�ԂɊ��ҁI �@ |
| �Q�O�O�U�N�V���P���i�y�j�A�Q�i���j�@�S�� �@�c��P�T�Ԃłł��邱�ƁE�E�E�H �@�Ȃɍ��߂�ꂽ��ȉƂ̑z���E�E�E�I �@�{�Ԃ��P�T�Ԍ�ɍT���A�Q���Ԃ̏W���������K�̎n�܂�`�B �@�y�j���́A�V���t�H�j�[���T���Ȃ������P�y�͂̕����ƁA�c��̊y�͂��قڒʂ��ŗ��K�B �@���j���A�ߑO���̓n�[�v������}���Ă̑O�v�����K�B���`�A����ς�n�[�v�̉��͂����˂��B�S���������`�B�����āA�ߌ�́A���ѐ搶�H���A�g�Q�l�v���̃Q�l�v���h�B�����̗��K��ꂾ���ǁA�����Ɠ����i�s�őS�Ȓʂ��B����ŁA������x�y�[�X�z�����v�ꂽ��Ȃ����ȁH �@�{�ԋ߂��Ȃ�ƁA���K�Q���l�����O�O�[�b�Ƒ����āA�����̉��y���ł͂��Ȃ�苷�ɂȂ�B���j�̌ߑO�͏W��i���N��قň�ԍL�������j�������̂ŁA�n�[�v�������Ă��]�T���������ǁA�ߌ�͉��y�������m�ۂł����A������Ƃ��イ���イ�l�ߏ�Ԃ�tutti�������E�E�E�G�A�R��������V���ł悩�����I �@�Q���Ԃ̗��K��ʂ��āA�搶���猾��ꂽ���Ƃ́E�E�E �@�E�����ɂ��ẮA����܂ł��܂茵��������Ȃ���������ǁA�A���T���u���ɂ����鉹���͑��ΓI�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA�l���ǂ��̂����̂Ƃ������A�Ƃɂ�������̉��Ƃ̋����𒍈Ӑ[�������悤�ɁB �@�E���ɁA�V���t�H�j�[�̕������ǁA�����e���|�̂Ƃ���ōی��Ȃ��˂������Ă����Ȃ��悤�ɁB �@�E�c��P�T�ԁA���ꂼ��悭�������āA�Ȃ̗����͂�ł����܂��傤�B �@�i���F�e���|�̗h��Ȃǂ������Ɉ�����肷��̂ŁA���܂���܂�߂��Ȃ����x�ɁI�j �@���āA���j���̒ʂ����K�̉��t���ă^�N�g�����������Ƃ��R�قǁE�E�E�B �@�������_�E�́A�e���|�̗h�ꂪ��������ĂȂ������B�S�̓I�ɏd�����̂ŁA�����Ɛ�֗����悤�ɉ��̏o�������H�v�������������Ǝv���B �@���h�i�E�A�����ƃ_�C�i�~�N�X���������肷��Ƃ����Ȃ��B �@���V���t�H�j�[�A�搶�������Ƃ���A�����e���|�̂Ƃ��낪�ǂ�������C���B�ƂĂ������������Ȃ��B�܂����̏o�����i���ɁA�NJy��j�����Ȃ����Ă���̂ŁA�e�������Ǝ�����]�T�������Ȃ��ƁI �@�Ō�ɁA���t����Ȃɂ́A���ꂼ��l�X�ȃG�s�\�[�h�A�����č�ȉƂ̔M���v�������߂��Ă��܂��B�����������ƒm���Ă��邩�ǂ����ł����t���ς���Ă���Ǝv���܂��B�܂��̕��́A�������A�N�Z�X���Ă݂ĂˁI�i�g����A���ӁI�j �@�ł́A���T�̖{�ԁA�撣��܂��傤�I �@ |
| �Q�O�O�U�N�U���Q�S���i�y�j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�O�v���������ȑ�P�y�� �@�v���X�������y���I�@ �@�����́A�����������͂��Ă����l�X�������y�c����̃Q�l�v���Ƃ������ƂŁA�R���E�~�X����ƃr�I���̂Ђ�|���������c�[��y�����x�݂ŁA������ƌ��y��͎₵�������B�ł��A������̖{�Ԃ��Q�T�Ԍ�A���X�g�E�X�p�[�g�����Ċ撣���Ă����܂��傤�I�@���`�I �@�ŁA�����̗��K�͂Ƃ����ƁA�g���ꂾ���́I�h�Ƃ����Ƃ�����Ċm�F���Ă���A�O�v�����P�Ȃ��ʂ����B �@���́g���ꂾ���́I�h�̑S�p�[�g�Ɋւ�����̂��L���Ă����ƁE�E�E �@�y�V���ƒn���z �@�E�P�S���ߖڂ͂R���ڂ��炫���ς肆�ŁI �@�E�P�T���ߖڂ���^�C�łȂ����Ă��鉹�͍Ō�܂ł��̂܂܂Łi�������Ȃ��j �@�E�V�X���ߖڈȍ~�̌��y��A�����r�X�����܂܂ŁB �@�E�X�T���ߖڂŕK�����Ƃ��Ă���N���V�F���h �@�E�P�O�O���ߖڂ���NJy��̓^�C�łȂ����Ă���W���������W���x���ɂ��āA�W�������A���̂��������͂������ �@�E�P�U�Q���ߖڂ���̌��y��A���߂āI �@�E�I��V���߁A�e���|���ɂ܂Ȃ��悤�ɁB�Ō�܂Ńp���[�Ɛ���������Ȃ��B �@�y�����_�E�z �@�E�P�P�X���ߖڂ����肩��rit.�������ĂP�Q�P���ߖڂ͊��S�ɂS�U�� �@�E�Q�Q�X���ߖڂ��炵�炭�Q���ڂ͂�⑬�߂ɂ��āA�t���[�Y�ɂ��˂�� �@�E�R�R�R���ߖځAPiu moto����͐�i�ފ����ŁB�d�����Ȃ�Ȃ��B �@�E�S�O�X���ߖڂ���y��ɂ���ăf�N���V�F���h�̂���������Ⴄ�̂ŁA�y���ɒ����� �@�E�����U���߂ł��Ȃ�rit.����̂ŁAVn�͎w�����݂Ă��킹��l�ɁB�t�F���}�[�^�̂P���ߑO�͊��S�ɂR�U��~�Q �@ �@�y���������h�i�E�z �@�ENo.2�����c�Ń_���E�Z�[�j������O��rit.�Ȃ��B���̂܂܂̃e���|�œ��ɖ߂��� �@�ENo.�S�����c�A�ŏ��̂P�J�b�R�S���ߖڂ���͂��Ȃ肽���Ղ�߂̃e���|�� �@�ENo.�S�����c�A�ŏ��̂Q�J�b�R���́Aaccel.�C���ɐi��ł��̌�̃t���[�Y���₩�� �@�E�I��P�P���ߖڂ���̌��y��͏���accel. �@ �@�y�����ȁE��P�y�́z �@�E�P�T�X���ߖڂ���S���ߊԁA�P�U�R�`�S���߂͒i�K��ǂ��đ傫�� �@�E�Q�S�O���ߖڂ���̖؊ǁA�P�U�������͂Ȃ�ׂ����ɂ��� �@�E�R�O�P�`�Q���߂̖؊ǂ̂����͂͂������ �@�E�R�P�Q���ߖځA�\�Ȍ���N���V�F���h �����Ƃ܂��A����Ȋ������������ǁE�E�E���`��A����ς艹�����Ȃ��E�E�E���ѐ搶�͂��܂茵�������������Ȃ����ǁA���������ӂ��������Ȃ�悤�ȂƂ��낪�Ȃ��ɂ������炸�B�����Ɋւ��ẮA�X�����{�l�̎��o�������Ȃ̂ŁA�܂��͎����̃N�Z�i�ǂ̉������߂Ƃ���߂Ƃ��j����������c�����āA�����悤�ɂ��܂��傤�I �@����ƁA���̉����Ă��˂��ɉ������ׂ����Ă��͂�������肹���ɒe����悤�A���K���K����B �Ō�ɁA�e�����Ɛ������ƂɈ�S�s���ɂȂ炸�A��������������]�T�������܂��傤�B����������D���Ȕޏ��ƃh���C�u���Ă�̂ɁA�ړI�n�Ɍ������Ĉ꒼���Ȃ�Ă܂�Ȃ��ł���H�@�ޏ��Ƃ̉�b���y����A�ԑ��𗬂��i�F�������ƒ��߂�]�T���Ȃ��ƂˁB �@�����āA���Њy�F����̂��̃����o�[�ł����ł��Ȃ����t�����ĉ������I�I �@����A�܂����T�I |
| �Q�O�O�U�N�U���P�W���i���j�@�P�O�F�O�O�`�P�T�F�S�T�@�S�ȁ`�� �@�C�������Ă������I�I�@ �@�����A�����͈���W�����K�I�@�t�@�C�g�H�I �@�܂��́A����̑����A�����Ȃ̑�S�y�� �@�y�����ȑ�S�y�́E����̑����z �@�E��������������ǁA�b����̃t���[�Y��P�Q�R���ߖڂ���̃t���[�Y�łQ���ߖڂQ���ڃE���ɂ���W�������̓X�^�J�[�g�ŁB�i���̌�ɏo�Ă��铯�l�̃t���[�Y�������悤�Ɂj �@�E�R�R�W���ߖڂ̓t�F���}�[�^���ĉ�����Ă���q�� �@�E�r��Piu animato�ŃX�C�b�`�I���I�i���̓����ѐ搶�͂��̌��t��A�����Ă����E�E�E�j�@���ւƐi�ނ悤�� �@�E�R�V�Q���ߖڂ���rit.������A�R�V�U���ߖڂ̃A�E�t�^�N�g�̉�����in tempo �@�����āA�ߑO���c��̂S�O���ŃV���t�H�j�[��ʂ��܂����B �@�ߌ�́A�O�v���̗��K�`�B �@�y�V���ƒn���z �@�E�`����con fuoco�I�I�@�Q�������@�C�I��������A���B�I������A�����o�邭�炢�C���ā`�I�H �@�E�P�S���ߖڂ̂�����������o���B �@�E�V�X���ߖڂ̌��y��A�����Ȃ�傫�� �@�E�P�Q�U���ߖڂ̑O��P�S�V���ߖڂ̑O��rit.�͋C�����̍��Ԃ肩�炭����́B��������C���������āI �@�E�`�������������A���y��̓����A�����ā`�B �@�E�P�V�W���ߖځA�y�₩�� �@�E�P�W�S���ߖڂŃX�C�b�`�I���A���� �@�E�P�X�O�A�P�X�S���ߖځA�Ŋy��ڗ����āI�I �@�E�Q�Q�V���ߖځA�X�C�b�`�I���A���� �@ �@�y���������h�i�E�z �@�ETempo di Valse�@�ŏ��͏��������ŁA�E�L�E�L�����C�����������o���悤�� �@�E�R�U���ߖڂ��牽�����]����悤�ɗ���� �@�E�����c�P�̂Q�T���ߖځA�R���ڂ͒Z������ �@�E�����c�P�̂R�R���ߖڂ��狭������������ �@�E�����c�Q�̂Q�J�b�R�́A�����ς�R���q�B�悭�w�������ăt���C���O���Ȃ��悤�� �@�E�����c�R�Alebhaft����̂W�������̓����͐�i�ނ悤�� �@�E�����c�R�A�Q�߂̂P�J�b�R�̂W��������meno�i�����e���|�𗎂Ƃ��āj�Ă��˂��� �@�E�����c�S�A�Q��ڂ̃����c�̎n�܂�͂P��ڂ���������� �@�E�����c�S�A�Q�J�b�R�ŃX�C�b�`�I���A�e���|���グ�Ă����� �@�E�����c�T��Eingang�͂��Ƃ����͂�������� �@�E�����c�T�̂P�P���ߖڂ̂S�������͈���Ă��˂��� �@�E�b�������h�h�̂P�R�V���ߖڂ����accel�I �@�����āA����̔��Ȃ܂��A�u�����_�E�v��ʂ��ďI���܂����`�B �@�݂Ȃ���A��������A�����l�ł����B�V���t�H�j�[���m���X�g�b�v�Œʂ������A���ꂼ��Ɏ��n�̑�������������Ǝv���܂��B����̗��K�܂łɊe���ł���ɖ����������āA�������t���ł���悤�Ɋ撣��܂��傤�I �@ |
| �Q�O�O�U�N�U���P�V���i�y�j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�����_�E�A�����ȑ�S�y�͑O�� �@�������̂��鉹���I �@���낻����K����l�߁I�@���������ѐ搶���炱��ł����Ƃ������炢�ו��ɂ킽���Ďw�E������܂����I �@�^�N�g���E�����w�E�͉��L�̒ʂ�B�����𗎂Ƃ����l�́A�������菑������ł����ĂˁI�i�����w�E���Q�x�A�R�x�Ƃ���Ȃ��悤�ɁI�I�j �@ �@�y�����_�E�z �@�E�`���̃t���[�g�i�ォ��o�Ă���N�����l�b�g���j�̂P�U�������͋ϓ��Ȓ�����ۂ��āB�i����}���ł��܂���I�j �@�E�`����́A�Q���ߒP�ʂŃe���|���h��܂��B�i�R�U���ߖڐ�ցA�R�V���ߖڂ͂��rit�Ƃ�����Ɂj �@�E�W�O���ߖڂ���̃z�����Apoco piu mosso�̃e���|�����������͂�ŁA�I�P�S�̂���������悤�� �@�E�W�O���ߖڂ���̊NJy��͖������̂��鉹�ŁI�i�u���X�̃X�s�[�h���グ��I�I�j �@�E�P�Q�Q���ߖڂ���́A��������邱�Ƃŋ������̂��鉹�y�����悤�� �@�E�P�T�R���ߖڂ���̃t���[�g�́A��ɉ��̗����オ�����������͂�����ƁB�i�����ɂ����ӁB�j �@�E�P�V�V���ߖڂ���̖؊ǂ́A�����ł����̗����オ��͂͂������ �@�E�P�W�V���ߖڂ���́A���y��A�t���[�g�A�N�����l�b�g�̓o�����X�ɋC�����A���ꂼ��̓����������o��悤�ɁB �@�E�P�W�V���ߖڂ���̃��@�C�I�����͂S���ߒP�ʂ̃t���[�Y�������� �@�E�z�����́A�P�W�X���ߖڂ�P�X�R���ߖڂȂǂS�{�����ďo��Ƃ���́A�o�������҂����葵����B �@�E�Q�P�R���ߖڂ���̋��ǂ̓����͂������ł��A�͂�����ƌ������� �@�E�Q�R�T���ߖڂ���̃t���[�g�A�N�����l�b�g�̓A�N�Z���g�̈ʒu�𐳊m�ɁB �@�E�g�̂P���ߑO�͂�����̃f�N���V�F���h �@�E���x���������ǁA�R�Q�V���ߖڂ́Asubito ���I�I�I �@�E�R�R�R���ߖڂ���̓e���|�A�b�v�I�@�|�A���̃X�s�[�h�������āA�������̂��鉹�y���B �@�E�S�O�V���ߖڈȍ~�A�NJy��ƌ��y��ł̓f�N���V�F���h�̂���������Ⴂ�܂��B���ɂ��Ċǂ��傫���Ȃ����肵�Ȃ��悤�ɁB �@�E�Ō�̂Q�̉��́A�c�̐����҂����葵����悤�Ɉӎ����W������ �@�y�����ȑ�S�y�́z �@�E�Q�O���ߖڂ̃e�B���p�j�̓\���X�e�B�b�N�ɁB �@�E�`����̃`�F���̃����f�B�[�͂����Ɖ����ɂ͂߂ĂˁI �@�E�a�̌㔼���烔�@�C�I��������A�}���Ȃ��ŁI �@�E�b����W�������i���ɃA�E�t�^�N�g�́j�̓X�^�J�[�g�ŁI �@�E�c�̂Q���ߑO�A�P�U�������̘A���ŋ}���Ȃ��B �@�E�c����̌��y��A�撣��Ȃ��I�I�@�ɗ͏��������ŁA�t���[�g�̃\����j�Q���Ȃ��悤�ɁB �@�E�X�P���ߖڂP�J�b�R�̂Q���ڂŃN���V�F���h �@�E�d������b����Ɠ��l�ɂW�������͒Z���B �@�E�P�Q�X���ߖڃA�E�t�^�N�g����̃I�[�{�G�ƃN�����l�b�g�͂U���߂P�t���[�Y�Ɋ����� �@�E�g����t���[�g�ƃI�[�{�G�͂S�������̃X���[�̈ڍs�ɋC��z���� �@�E�g����̃t�@�S�b�g�ƃN�����l�b�g�͈�̓����ɂȂ�悤�� �@�E�g����̃z�������p�[�g�ň�̓����ɂȂ�悤�ɂ�������A�W�v���[���� �@�E�l�A�g�����{�[������A�o�Ԃł��I�I �@ �@�Ɠy�j���͂����܂Ł`�B�����͗����B �@�E �@ |
| �Q�O�O�U�N�U���P�O���i�y�j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�V���ƒn���A�h�i�E�A�����ȑ�P�y�� �@�@���Ƃ��ʼn��y�̃����n�����͂�����ƁI �@�{���̒��ӎ����͉��L�̒ʂ�`�B �@�y�V���ƒn���z �@�E�P�P���ߖڂ́A���̉����炐�I�@���y�̕��͋C���K���b�ƕς���B �@�E�P�S���ߖڂR���ڂ���͂��A�����ŁB�P�U���ߖڂ̂R���ڂ܂ł��̉��ʂ�ۂB �@�E�u���D�P�͂P�U���ߖڂR���ڂ͂W���x���ɒ��� �@�E�P�U���ߖڂR���ڃE������́A���ł��A�y�������ŁB �@�E�R�O���ߖڂ̃f�N���b�V�F���h��Y��Ȃ��B�i�R�P���ߖڂŋ}�ɂ��ɂȂ�Ȃ��悤�ɁB�j �@�E�S�V���ߖڂ���̔��t�p�[�g�̓`�F���̃\���ɍ��킹�鎖�Ɖ��ʂ͍T���߂� �@�E�V�W���ߖڂ́A���Ȃ蒷���t�F���}�[�^���܂��B�i�`�F���ƃn�[�v�̕��U�a�����ۗ������āA�Ȃ�ׂ����������ŐL���B�j �@�E�V�X���ߖڂ���̓K���b�ƕ��͋C��ς���B�W�R���ߖڂ���̂P�U���R�A����W�������͓������͂�����ƁB �@�E�X�S���ߖڂ́A�������炢�ɗ��Ƃ��Ă���N���b�V�F���h �@�E�X�W���ߖڂ���̊NJy��̓����A�W�������̓����Əo��������҂����葵����B �@�E�P�O�S���ߖڂ���̂S�������͂P�O�U���ߖڂɌ������Ĉ�C�ɐi�ށI �@�E�P�S�V���ߖڂ���́A���Ȃ�������e���|�Ń����f�B�b�N�ɁB �@�E�P�U�P���ߖڌ㔼�͂`�������������̃e���|�i�P���߂͂�����Ă銴���ɂȂ�B�j �@�E�P�U�Q���ߖڂ̌��y��́A���ł�������͂�����ƁB�i�����ɂ���C���Ƃ�ꂸ�A�ނ���ڌ��̕��ɒ��ӂ��āA�����o���悤�ɁB�����g���[�i�[���j �@�E�P�X�O�A�P�X�P���ߖڂƂP�X�S�A�P�X�T���ߖڂ͑Ŋy��ȊO�͂����ɗ��Ƃ��B�i�Ŋy�킾�����傫�����������ŁB�j �@�E�Q�O�O���ߖڂ���̂P�U�������͂Ȃ�ׂ����ɂ���B����accel���� �@�E�Q�O�S���ߖڂ�a tempo �@�E�Q�Q�V�A�Q�Q�W���ߖڏ���accel.���āA�Q�Q�X���ߖڂ�a tempo �@�E�I��T���߂́A���̂܂܂̃e���|�ł����܂��B�i�^����������肵�Ȃ��B�j �@ �@�y���������h�i�E�z �@�E�P�S���ߖڂ���̃`�F���̃����f�B�[�́A���̑O�̃z�����̃����f�B�[�̊������p���ŁB �@�E�Q�R���ߖڂ�Tempo di Valse�́A��������������悤�Ȋ����ŁA����������������cresc. �@�@�s�m���D�P�����c�t �@�@�E�R�S���ߖڃA�E�t�^�N�g����́A���Ƃ��̃_�C�i�~�N�X�����炵�� �@�@�s�m���D�Q�����c�t �@�@�E�Q�J�b�R�͊��S�ȂR�U��i��������w�������āA�t���C���O���Ȃ��悤�Ɂj �@�@�s�m���D�R�����c�t �@�@�E�Q���ߖڂ���̃A�N�Z���g���͂�����i���h�q�������݂����ɁH�I�j �@�@�ELebhaft����̃e���|�̗h���̂ɒ@������� �@�@�s�m���D�S�����c�t �@�@�E�T���ߖڂ͂Q��ڂ̕����������e���|�B�i�R�U�肷��̂ŁA�w�����悭����j �@�@�E�Q�J�b�R���班��accel �@�@�s�m���D�T�����c�t �@�@�E�T���ߖځA�K�����ɗ��Ƃ� �@�@�s�b������ �U�t �@�@�E�P�O�W���ߖځA�P�U��� �@�@�E�P�R�T���ߖځA���R�U�� �@�@�E�P�R�U���ߖځA���S�ɂR�U�� �@�y�����ȁ@��P�y�́z �@�E�P�T�X�A�P�U�O���ߖڂ̂��A�P�U�P�A�P�U�Q���ߖڂ����̈Ⴂ���͂�������� �@�E�P�U�V���ߖڂ̂R���ڂ���̂e���C�b���͋ɗ͑傫�� �@�E�Q�O�V���ߖڂ���̂s���̂S�������́A�s���Z�� �@�E�R�O�T���ߖڂ̂S���ڂ̊NJy��̓X�^�J�[�g�� �@�E�R�O�V���ߖڂ���̊NJy��̂S�������͏����Z�߂ɂ��ďd�����Ȃ�Ȃ��悤�� �@ �@���S�̓I�ɁE�E�E �@�@�����������Ƃ����Ɛ������I �@�����g���[�i�[���� �@�@���낻��y���ɂ�������̂���߂āA�����Ǝ���ŗ���Ă��鉹�y��c�����Ȃ���e���悤�ɂ��܂��傤�B �@�@�����o�������ł͉��y�ɂ͂Ȃ�܂����I �@ �@���ѐ搶����̊e�Ȃɑ��钍�ӎ�������̏o�������i�H�j�����B���ꂩ��́A�����w�E��tutti���~�܂����肵�Ȃ��悤�ɁA�e���ł������蕜�K���Ă����܂��傤�I �@�y�T�b�J�[�A���[���h�J�b�v�n�܂�H�I�z �@���ѐ搶�́A�����̃T�b�J�[�D���炵���A���ꂩ�疈���S�̓h�C�c�ɔ�Ԃ������E�E�E(^_^;) �@�c���̒��ɂ��T�b�J�[�t���[�N�͑����Atutti���Ȃ̂Ɏv�킸�b������オ��A���Ȃ����K���Ԃ��`�I�ƃn���n�����郁���o�[������ق�B�@����́A�����s���̃����o�[�����������Ȃ��B(>_<) |
| �Q�O�O�U�N�U���R���i�y�j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�����_�E�A�����ȑ�P�y�� �@�@�c��P�����Ł`���I �@���ƂȂ��A�v���Ԃ���Ċ����́u�����_�E�v�ł��B���ѐ搶�́A�����ɔ����āA���K���ׂ��|�C���g���O�O�b�ƍi�荞��ł��炵���̂ɁA�̐S�̃p�[�g���܂������Ă��Ȃ��āA�����[���璲�q�������Ă��܂����悤�������B�ł��E�E�E�e���d�����X�̓s���łǂ����Ă��P�W�����ɊԂɍ���Ȃ��l������̂ŁA�����ق��I �@���Ă��āA�C����蒼���A�����͉��̂����u�����_�E�v�̏I�肩��A���ӓ_���q�ׂȂ���tutti�B �@�e�y��ւ̎w�E���ڂ���ƁA���L���c��ȗʂɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�Ƃ肠�����A�S�̂Ɋւ��邱�Ƃ������ڂ��Ă����܂��B���ꂼ��̃p�[�g�ւ̎w���̓p�[�g���Ŏ��m�O�ꂵ�Ăˁ� �@�y�����_�E�i�I�肩��E�E�E�j�z �@�E�S�Q�Q���ߖڂ����肩��rit. �@�E�S�Q�R���ߖځA�Q�U�肩����U�U��� �@�E�S�Q�S���ߖځA���S�ɂU�U��i�R�U��~�Q�j �@�E�S�P�O�ȍ~�͊y��ɂ����dim.�̕t�������Ⴄ�̂ŁA�y���ɒ����ɂ����邱�� �@�E�R�R�R���ߖڂ�Piu moto����e���|�����Ȃ�A�b�v����̂ŁA�f������������ �@�E�R�R�R���ߖڈȍ~�̃A�N�Z���g�A�������͂�������� �@�E�R�Q�V���ߖڂ�subito p������I�I �@�E�d�̂Q���ߑO����Q�U�� �@���S�̓I�ɁA���̗����オ�肪�B���Ŏア�B�����Ƃ�������͂�����I�I �@�y�����ȑ�P�y�́z �@�E�`���̃����f�B�[�́A�S�y�퉹�̐�ڂ����킹��B�i���x�݂����l�́A�����p�[�g�̐l�ɕK���m�F���邱�ƁB�j �@�E�`����W�������|�P�U���x���|�P�U�������Ȃǃ��Y���Œx��Ȃ��B�P�U�������͂Ȃ�ׂ����ɂ���B �@�E�R�U���ߖڂ���キ�Ȃ�߂��Ȃ��I �@�E�S�V�A�S�X���ߖڂ̓��ɊNJy��̂P�C�R���ڂ��҂����葵����B �@�E�P�S�T���ߖڂ���̌��y��́A�e���̃\�����ۗ�������悤�ɁB�i���ʂ��Z�[�u�j �@�E�f�Ɍ������āAcresc.���������� �@�E�P�T�X���ߖڂ���P�U�P���߂܂Œi�K��ǂ��đ傫�� �@�E�g��������y��͍T���߂ɂ��A�e�����Ȃ��悤�ɁB�܂��A��������ǂ��l�߂��肵�Ȃ��悤�ɁH�I �@�E�i�̂e���̃A�E�t�^�N�g����e���|�����炽�߂Ď��܂��B��э��܂Ȃ��悤�ɁB �@ �@�Ƃ���Ȋ����ł����B �@���T�̌����Ȃ͂��̑���������܂��B �@ �@�{�Ԃ܂ŁA���悢��P�����E�E�E�S�z����Ă������A�u�����_�E�v�Ȃnj`�������Ă�������ǁA�����͑��ς�炸�낤�����A���ꂼ�ꂪ�܂��������e���i�����j���Ƃɐ���t�ŃA���T���u���ʂł��܂��܂��B�S���Ƃ͌���Ȃ�����ǁA������x�͈Õ��ŗՂނ��炢�̈ӋC���݂Ń����V�N�ł��I |
| �Q�O�O�U�N�T���Q�V���i�y�j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�����ȁE��Q�y�͂ق� �@�@�S�[���܂ł͂܂��܂������Ȃ��E�E�E�B �@�����́A�O�����t�Ō��͏��ѐ搶���w�����Ă���邱�ƂɂȂ��Ă����̂ɁA�������o�[�̏W�܂肪����ŁA���Ǎŏ�����tutti����邱�ƂɁE�E�E�B�搶�́A���H�������Ȃ���̎w�����ƍl���Ă����炵���A���@�C�I���������Q���Ă����B�������A�ƂĂ��M�d�ȋ@����Ă��܂����悤�ȋC���B�i�����������̂̓^�N�g�����H�j �@tutti�̗l�q�͂Ƃ����ƁE�E�E�O�����t�Ƃ����\�肪�����Ă������߂��A�NJy��̏W�܂���ǂ����F�����Ȃ��A������ƋC�̔����������Ȃ��ɂ������炸�ł����B����ɁA�{�Ԃ܂ł��ƂP�����Ə����Ƃ������̎����ɂȂ��Ă��A�܂������̉������p�[�g������ق�B����܂����˂��B���Ƃ��A�_�C�i�~�N�X�̖��Ȃ�A���̊y��Ƃ̃o�����X������̂ŁAtutti�Ŋm���߂Ȃ�����͓̂��R���Ǝv�����ǁA�����Ɋւ��Ă͂܂��l���̔��e����ˁB���́A�R�O�O�O�~��Ń`���[�i�[�ƃ��g���m�[�������̂����y�ʃR���p�N�g�E�����\�̂��̂��o�Ă��邩��A�����ƈ�l��l���V�r�A�Ɏ����̉����ƌ��������ė��K�������tutti�ɗՂ�ł��炢�����ˁB�����݂����ȕs���a�����炯�̉��t���Ⴀ�A�ƂĂ��ƂĂ����t��Ȃ�āE�E�E�B �@���ѐ搶�����Ȃ藎�_����J���ނ���ċA�r�ɒ������悤�������B�搶�́A�������D�����̂��A���������Ƃ����������Ȃ�����ǁA�R�e���p���Ɏ����Ăǂ��ɓ˂����Ƃ���Ȃ��ƃG���W����������Ȃ��悤�ł͂ˁE�E�E�B�ƁA�^�N�g�̏����͂����܂łɂ��āA�A�A�����̒��ӎ����������Ƃ��m�点�ł��B �@�y��Q�y�́z �@�E�`���̌��y��i���ɒጷ�j�͉����𐳂����Ƃ邱�ƁB �@�E�X�`�P�O���ߖځA���A�������I �@�E�`����̊NJy��A���j�]���̉������������荇�킹�Ă������ƁB �@�E�a�̃A�E�t�^�N�g����̊NJy��̓����A�a�̓��̉��Ɍ�������cresc.�B�����Ɏキ�Ȃ�Ȃ��B �@�E�a�A�Q���ߖڂ���̌��y��͂����B�͋����I�I �@�E�S�Q���ߖڂQ���ڂ���̊NJy��́A�����ŏ������������n�܂���cresc. �@�E�b����̂u���̓����́A�P�̗���Ōy���B�i���Ƃœ�������������NJy������l�Ɂj �@�E�b�A�Q���ߖڂ���̃t���[�g���I�[�{�G�̃����f�B�[�͉��̌�������������������ӎ�����cresc.�I �@�i���ƂŁA�����t���[�Y��e���������l�ɁB�j �@�E�c����̖؊NJy��͌y���y���A�u���\�����ۗ�������悤�ɁB �@�E�U�S���ߖځA���Ȃ�^������B�i�U�T���ߖڂ̉�����яo���Ȃ��悤�Ɂj �@�E�e�̌��y��́A��������I �@�E�X�U���ߖڂ���̂b���̓����͑������o�[�g����B �@�E�P�O�V���ߖڂ���piu mosso �@�E�i�̂Q�A�S���߂߂̖؊ǂ�cresc.�ŁB �@�E�P�S�U���ߖڂ̂P�U�������̓����́A�T�ƂR�ɕ����āB�i�X���[�̂������B�j �@�E�P�T�T���ߖځA�㔼�̂e�����u���̂P�U�������́A�����Ղ�߂ɁB �@���T�́A�����_�E�������ȑ�P�y�͂�������܂��B�݂Ȃ���A�����ɑ��Ă����ƃV�r�A�ɂˁI |
| �Q�O�O�U�N�T���Q�O���i�y�j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�V���ƒn���A�h�i�E�A�����ȂQ�C�P�C�S�y�� �@�@�r���������@�����@�����������H �@���v���Ԃ�`�A�^�N�g�ł��B���́E�E�E�C�w���s�ɍs���Ă����̂ŁA�P���L�����x�݂����Ⴂ�܂����I���߂�Ȃ����B �@���Ă��āA���l�т��ςƂ���ŁA�����������T�̗��K�͗l�����ł��B �@�����́A���Ȃ�̍��o�ȗ��ŁA�ē��ŏ����̎c�镔�����A�l������ƔM�C�Ń���������Ԃ������B �@�܂��́A�V���ƒn���̏����ӂƃe���|�̕ς��ڂ��Ċm�F���ē�����ʂ��B �@�o�����́A�A�E�t��^�N�g����con fuoco�ŁI�@����͂��Ȃ�ӎ����Ēe���Ȃ��ƁA���̗����オ�肪�キ�Acon fuoco�̊������o�Ȃ���B�Ƃɂ����Ȃ�ӂ�\�킸�A�W���J�W���J�e�����I �@���̌�́A���̊Ԙb�����ʂ�A�_�C�i�~�N�X�����炷�邱�ƁB �@�S�V���ߖڂ���̓`�F���̃\�����悭�����Ĕ��t�͍��킹�鎖�B�i����ɐ�ɍs���Ȃ��I�j �@�V�W���ߖڂ̃t�F���}�[�^�͂��Ȃ蒷�����܂��B�o�債�Ă����悤�ɁI�H �@�P�O�V���ߖڂ���́A�u���\�����悭�����č��킹��悤�ɁB �@�P�Q�T���ߖځA�S���ڂ���͊��S�ɂR�U�� �@�P�Q�U���ߖڂ���́A���炩�ȉ~�̓����������Ēe���悤�ɁB �@�P�S�U���ߖځA�S���ڂ���͊��S�ɂR�U�� �@�P�U�P���ߖڂ͓������炷������邱�ƁB���̃e���|�ɑ��₩�Ɉڍs���܂��B �@���y��͂P�U�O�`�P�U�P���ߖڂ̐L���̉����A�P�U�Q���ߖڂ̂P�U����������������߂炦�邱�Ƃ��ӎ����邱�ƁB���ꂪ���܂�����Ȃ��Ǝ��̊NJy��̓����ɂȂ���Ȃ��I �@�P�U�Q���ߖڂ���́A���������������A�����ďd���Ȃ炸�A���ւƗ����悤�ɁB �@���́A�h�i�E�B �@��������܂������ӂ��Ċm�F���Ă���A��ʂ�ʂ��B �@�`���̖؊ǂ́A�܂����͋C���C�}�C�`�B�����ƃC���[�W���������莝���ƂƉ����d���Ȃ肷���Ȃ��悤�ɁB �@�R�O���ߖڂ̂S�������̓X�^�J�[�g�I�@�Z�����āI�I �@�m���D�P�����c�̂R�S���ߖڂ���́A���Ƃ��̑Δ����������i���̊NJy��A�������艹���o���I�j �@�m���D�R�����c�̂R���ߖڂ���̃g�����͉��̏o�������͂�����o���B�i�キ�Ȃ�Ȃ��悤�Ɂj �@�m���D�R�����c�̂Q�J�b�R�ȍ~�́A�W�������̗���𗘗p���ď���accel.�@����̌J��Ԃ��ł��B�e���|�̗h������₭����ŁI �@�m���D�S�����c�A�Q�J�b�R�̂T���߂���piu mosso�B�e���|�グ�A�₩�ȕ��͋C�ŁB �@�m���D�T�����c�Q�J�b�R���A��ΔS��Ȃ��ŁA���i�ށB �@�b�������㔼�̃t���[�g�̃\���́A�w�����݂č��킹�鎖�B �@���ɁA�V���t�H�j�[�̂Q�y�́B �@�ǂ̃t���[�Y���A�����f�B�[���C�����������芴���Ă����Ƃ����Ɖ̂��ӎ��������ƁB �@�a�̊NJy��́A�����̌�A�����ɉ������ڂ܂Ȃ��悤�ɁB �@�S�T���ߖڂ���piu mosso �@�c����́A�u���\�����悭�����āA���킹�鎖�B �@�f�̂S���ߖځA�z�����̓�������piu mosso �@�b����тj�̂P�U�������̉��~���^�͉��炵���y�₩�� �@�I��Q���߂̃N�����l�b�g�ƃt�@�S�b�g�́A��������Ƃ�܂��B �@�Ō�ɁA���̂P�y�́��S�y�̖͂`�������킹�ďI��`�ł����B �@ �@�y�^�N�g�̈���R�����H�z���s��� �@�u�V���ƒn���v�̒��ԕ��Ɓu�h�i�E�v�Ő搶���C�����悭�x���Ă�����A�݂�Ȃ̉��t�͍��i�炵���E�E�E�B �@���āA�{�Ԃ́A���܂���ɁgShall we dance?�h�ƂȂ邩�Ȃ��H |
| �Q�O�O�U�N�S���Q�Q���i�y�j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�V���ƒn���A�����_�E�A�����ȂP�C�S�y�� �@�@�V�l����A���������`���� �@�S���A�t�A�V�������n�܂邱�̋G�߁A�I�P�ɂ��V���������I�@�t���[�g�ƃR���g���o�X�ɑҖ]�̌��w�҂����Ă��ꂽ�B�����āA�ƂĂ����������ɁA���̓��̂����ɓ����I�I�@����l�Ƃ����ꂩ�烈���V�N�`�� �@�挎�́A�u���ɃR���~�X����̂���q����R�l�������A�`�F���ɂ��P�O�N�߂��Ԃ�ɕ��A���ꂽ�������āA�����ԃ����o�[���[�����Ă����B�悩�����B �@�Ƃ��낪�A�����̗��K�́A�����ɂ��A���ǃ����o�[�����Ȃ߂ŁA�������e�B�[���G�C�W���[�g���I���������Ă��x�݂��Atutti�ɂ��Ă͂�����Ɨ҂����Ƃ�����E�E�E�B �@�ł��A�������ɂ��₩�ȏ��ѐ搶�̎w���ŁA�݂�ȁA�ƂĂ��y�������Ɋy������t���Ă����B �@�����̎�Ȓ��ӓ_�́A���L�̒ʂ�B �@�y�V���ƒn���z �@�I�[�v�j���O�́A"con fuoco"�i���̂悤�Ɂj�I �@�P�P���ߖڂ́A���̉����炢���Ȃ肐�ŁB �@�P�U���ߖڂ̂��͌y���A��i�ނ悤�� �@�Q�P���ߖڂ���A�A�N�Z���g�͂����� �@�R�O���ߖڂł�������f�N���b�V�F���h���āA���� �@�S�V���ߖڂ���̂k���������́A�`�F���̃\���̃����f�B�[�̗���������Ȃ��町�t��e�����Ɓi�e���|���h��܂���`�j �@�V�W���ߖڂ̃t�F���}�[�^�͂��Ȃ蒷������̂ŁA�v���� �@�P�O�V���ߖ�Allegretto�̑O�̂W�������Q�̃A�E�t�^�N�g�͂u���\���݂̂Ȃ̂ŁA��яo���Ȃ��悤�� �@�P�O�V���ߖڂ�����u���\���̓����ɒ��ӂ��͂���āA�e���|�̗h��ɑf������������ �@�P�Q�U���ߖڂ���̃����f�B�[�͌y�������悤�ɁB�����̂Ƃ���͈��̉�����������͋��� �@�P�S�U���ߖځi�`�������������̂P���ߑO�j�͎w�����悭���č��킹�邱�ƁB�㔼�̂Q���i�T�A�U���ځj�͂��Ȃ胋�o�[�g���܂� �@�P�U�P���ߖڂ̓��̂S�������͒Z�߁i�����Ɏ���Allegro�̃e���|�ɓ���܂��j �@�P�X�O���ߖځA�P�X�S���ߖڂ͂����ɂ���i�����ƑΔ䂳���邽�߁j �@�P�X�U���ߖڂ́A���ł͂Ȃ����̑O�̂����̂܂܂ŁA�Q�O�O���ߖڂ����肩��N���b�V�F���h���Ă��� �@�Q�T�V�`�Q�T�W���ߖڂ̂P�J�b�R�i���s�[�g���j�Ȃ� �@ �@�y�����_�E�z �@�`�����炠��P�U�������U�̉��̎p�����X���[�Y�ɂł���悤�ɁB�i��{�̊y��ł���Ă���悤�Ɏ��R�ȗ���ɕ�������悤�ɂ���j �@�P�Q�Q���ߖڂ���̂P�U�������̓����́A�Q�ł܂�ŏ����Ă���Ƃ���͂��������������o���悤�ɉ��t����B�܂��A�A�N�Z���g��������Ƃ��� �@�y�����ȂP�E�S�y�́z �@���ǂ���A����̉ۑ�Ƃ��Ė`���̃`�F�������𒆐S�ɍ��킹�E�E�E�Ŏ��Ԑ�I �@�s�������I�x�������E�t�B���I�H�t �@�����́A���\����ɂ��Ă̎w�E���������̂����ǁA���̍ہA���ѐ搶������Ȃ��b���B �@����́A�x�������E�t�B���ł̂��ƁB����w���҂��A�u�����Ƃ��i�t�H���e�j�`�I�v�Ǝw�����o���ƁA���̒ʂ肆�ɂȂ�B����ɁA�u�����Ƃ����Ƃ��i�t�H���e�j�������I�v�Ɨv�����Ă�����ɂ�����Ɗm���ɂ������������̉����o��B���ꂪ���ƂT�炢�J��Ԃ���Ă��A������Ɖ����Ă���邻���Ȃ̂��B����́A���ɑ��Ă������ŁA�x�������E�t�B���̃_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ����̂́A������Ȃ��Ƃ������A�Ƃɂ����z����₷��L��������炵���B���������E�ō���̃I�P�I�Ƃ������������������̂��b�ł����B�t�[�b�B �@���āA����tutti�́A�A�x���������薾�����T���P�R���B�����_�E�����邻���Ł[���B�݂Ȃ���A���������V�N�B�@ |
| �Q�O�O�U�N�S���P�T���i�y�j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@���������h�i�E���h���H���U�[�N�P�C�S�y�� �@�@�e���T�C�w���ҁH�I �@�����́A�u���̏W�܂肪�C�}�C�`�E�E�E�R���E�~�X����͂��x�݁H�I�@���`�A����������tutti�Ȃ̂ɁA���v���H�@�ƐS�z��������ǁA�P�����̃����o�[�͂Ȃ��Ȃ��������Ă������A�Q������Sawako�}�}�������̂ŁA�ق��B �Ȃ�Ƃ��Atutti�ɂȂ�����`�B�i�Ȃ�Ē�x���Ȃ��Ƃ������Ă��Ă͂�����I�j �@���āA������tutti�́A�h�i�E����B���ߔԍ���U��Ȃ�����K�����̂ŁA���x�݂����l�́A���L���Q�ƂɋL�����Ă����ĂˁB �@Tempo di Valse�E�E�E�Q�R���ߖ� �@�m���D�P�����c�̍ŏ��̃��s�[�g�E�E�E�R�S���ߖ� �@�m���D�R�����c�ŏ��̂Q�J�b�R�E�E�E�P�V���ߖ� �@�m���D�T�����c�̍ŏ��̃��s�[�g�E�E�E�P�Q���ߖ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�J�b�R�E�E�E�Q�W���ߖ� �@�b�������U�@�ŏ��̃_�u���o�[�E�E�E�P�X���ߖ� �@�@�@�@�@�@�@���̃_�u���o�[�iF dur�ɓ]�������Ƃ���j�E�E�E�T�P���ߖ� �@�@�@�@�@�@�@���̃_�u���o�[�i�c dur�ɓ]�������Ƃ���j�E�E�E�V�U���ߖ� �@�@�@�@�@�@�@�f�D�o�D�̏��߁E�E�E�P�O�V���ߖ� �@�����āA���ӎ����́A �@�E�`���̖؊ǂ̂W�������͗]�C�ŏ_�炩���B �@�ETempo di Valse�͂Ƃɂ����y���͂���Ő�i�ނ悤�� �@�y�m���D�P�����c�z �@�E�Q���ߖڂ͂����Ƀe���|�ŁB�i�Q���ڂ�����l�͂��₭�e���|������Łj �@�E�Q�T���ߖڂR���ڂ̂W�������͒Z�����āA���̂W���x���̊Ԃ��������芴���� �@�E�R�R���ߖڂ���̂��A���̋��������������A�Δ���I �@�y�m���D�Q�����c�z �@�E�R���ߖڂ̃A�N�Z���g����ۓI�ɁA���������킹�� �@�E�Q�J�b�R�͂R�U��Ȃ̂ŁA�悭�w�����݂āA�R���ڂ���яo���Ȃ��悤�� �@�y�m���D�R�����c�z �@�E�Q�J�b�R�̓e���|�����o�[�g����̂ŁA�w�������č��킹��B�i��яo�����ӁI�j �@�E�k����haft�̂Ƃ���́A�W�������A���̐����𗘗p���ď���accel.�@�Q�O���ߖڂ̓e���| �@�@�i�ȍ~�����悤�Ɂj �@�y�m���D�S�����c�z �@�E�T���ߖڂ͂R�U�� �@�E�P�J�b�R�͕K�����ɗ��Ƃ� �@�E�P�J�b�R�̂S���ߖڂ�rit. �@�E�Q�J�b�R���班������accel. �@�y�m���D�T�����c�z �@�EEingang�̂��Ƃ��������Ƃ��� �@�E�P�P���ߖځA�����c�̎n�܂�͂������R�U��B�i�w�������č��킹��j �@�E�Q�S���ߖڂ����肩�班������rit.���ĂQ�V���ߖڂ̂S�������͂������ �@�E�Q�W���ߖڂ���͏���accel. �@�E�R�Q���ߖڂ���₩�ȕ��͋C���o���� �@�y�b�������U�z �@�E�S�R���ߖڂ͂��I �@�E�U�T���ߖڂ���accel.���y�� �@�E�P�O�W���ߖڂ���̃t���[�g�͌y�₩�� �����c�́A�e���|�����Ȃ�h��邵�A�܂��A���͋C��肪�ƂĂ���Ȃ̂ŁA�Õ����邮�炢�̋C�����ŁA�Ƃɂ����y���ɂ�������ɂȂ�Ȃ����ƁB�����Ǝw�������Ăˁ`�B �@���ɁA�h���H���U�[�N�̂P�y�͂���B �@�E�`���̃`�F���ƃz�����́A���������킹�āI �@�E�c����̋���i���Ɍ��̂����j���������� �@�E�f�̋��NJy��́A�t�_�Q�������ƂS���x���ɒ��� �@�E�P�T�X���ߖڂ���́Acresc.�ł��B�キ�Ȃ�Ȃ��ŁI�I �@�E�g�̓t���[�g������i�V�g�̉̂�`�I�H�j�Ȃ̂ŁA���͍T���߂ɁA�ł��キ�Ȃ肷���Ȃ� �@�E�P�W�Q���ߖڂ���̂P���� �u���A�������킹�ā`�I �@�y�S�y�́z �@�E�`���̃`�F���͖�����̂ŁA�����E���Y�����s�b�^�������悤�ɁA�l���K����������I �@�Ƃ܂��A����Ȋ����ł����B ���āA�悤�₭���ѐ搶�ƃI�P�̃y�[�X�������Ă����悤�ȋC������B���Ƃ́A�݂�Ȃ������Ƃ����ƐϋɓI�ɉ��y�����t����悤�ɂȂ�Ƃ������ǁE�E�E�B�O����搶�Ɍ����Ă���悤�ɁA�C���[�W�������ĂˁB �@�y�e���T�C���~�V�ˁA���V�Ёz �@���ѐ搶�ɂ́A���̂Ƃ���A������ƍ������W���N�X�����܂Ƃ��Ă���炵���B����܂Ŗ{�ԂƂ����ƁA�n�k�i�L���ɐV�����V���n�k�j��䕗�A��J�ȂǁA�V�ЂɌ�������m�������Ȃ荂���̂��Ƃ��B���āA�V���̎s���̖{�Ԃ͂����Ȃ��ƂɁH�@�����S�z�����ǁA�ł��A�l��́A���N���߂ɁA���̗����A�u�[�߁v�������I�����̂��B���v�E���v�`�I |
| �Q�O�O�U�N�S���W���i�y�j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�h���H���U�[�N�W�ԂR�y�́��P�y�� �@�@�C���[�W�����ɁH�I �@�����A�R�T�ԂԂ��tutti�����`�I�@��T�́A���E�Ǖ�����Ă�������Z�N���B���y��́A�ґ�ɂ��i�I�j���ѐ搶�ƈ��g���[�i�[�̃_�u���u�t�w�̎�����w�����A���Ȃ�̐��ʂ����҂����Ƃ���B �@�܂��́A��T�̉ۑ肾�����R�y�́B�����˂��`�A���̖`���̃����f�B�[�B�^�N�g�́A���̂R�y�͂̉��Ƃ������Ȃ����D��тт��������ƂĂ��D���I�@�����ŁA���ѐ搶�A�܂������ȊO�̌��y���e������B�����A���̂��̔��t�p�[�g�����ł�������ˁ`�B���ɁA�Q���� �u���̂Q���ڂɓ���s�b�c�B�J�[�g�����Ƃ��f�G�B �@�����āA�N�����l�b�g�ƃt���[�g�̕��U�a���I�ȂR�A���̓����ƃI�[�{�G�A�t�@�S�b�g�̉��̈��p���A���̏o�����������āA�o�g�������܂��n��悤�ɂȂ�A�����Ƒf�G�ɂȂ�ˁB�撣���ā`�I �@���̑��A��Ȓ��ӓ_�Ƃ��āA �@�E�����i�t�H���c�@���h�j�ƃA�N�Z���g�̉��͂͂����肭������ƁB �@�Ecresc.�ł��ɒB������A���̂܂܂̋����ŕۂ��āB�}�Ɏキ�Ȃ�Ȃ��B �@�E�e���A���̏o�����ɂ����Ƃ����Ɛ_�o���g���āA���̐l�ƃs�b�^��������B�i�s�A�m�Řa����e���݂����Ɂj �@�E�����āA����ς�g�����h�I �@����ɁA�����́A�g�A�S�[�M�O�h�Ƃ������t�����x���o�Ă��܂����B�u�e���|��Y���ɔ����ȕω������ĉ��t�ʖL���ɂ���v�Ƃ������Ƃ炵���B�ȒP�Ɍ����ƁA�g�h��h�B�@���ꂪ���邩�炱���A���g�̐l�Ԃ����t���鉹�y�ɂ͖�������̂��E�E�E�B�������A�T�O�l����ʼn��t����I�[�P�X�g���ł��̗h��𑵂���̂͂Ȃ��Ȃ�����̋Z�B�����疈�T���T���K���āA�u�w��������I�@�R���E�}�X������I�v�ƂȂ���ǂˁB �@����ƁA������A�������ѐ搶���狳��������ƁB�w�����̏o�����ɋ�̓I�ȃC���[�W�����x�Ƃ������ƁB �@���Ƃ��A�y����ł͒P�Ȃ�W�������ł��A���̉����{�[���ɗႦ����ǂ�ȃ{�[�����H�@�e�j�X�̃{�[���H�@����Ƃ��A�o���[�̔����{�[���H�@�������A�����Ȃ�ĂȂ��B�\�l�\�F�̃{�[���ō\��Ȃ��B�厖�Ȃ̂́A���ꂪ�ǂ̂��炢�̍d���ʼn��F�ŁE�E�E�ȂǂȂǂ�������C���[�W���āA��������ɂ��悤�Ƃ���C�����������ƁB���ꂾ���ŁA�o�Ă��鉹�F���S�R����Ă���B�i�m���ɁA�o�X�P�b�g�{�[�����C���[�W����O�ƌ�ł́A�s���̑חt�����̉��͖��炩�ɈႢ���I�j �@���̘b���Ă��āA�ӂƎv���o�����̂��A�ŋ߃u���[�N���Ă���u�̂��߃J���^�[�r���v�Ƃ����R�~�b�N�B��l���̂̂��ߏ�́A�܂��ɉ��y�ɐF�ʂ��Ƃ����܂��܂ȃC���[�W�������ĉ��t���Ă���I�i���ѐ搶���A������w�̂��߃t�@���x�H �@����͂��Ă����A���{�ł́A�Ƃ����u�N���V�b�N�������v�Ǝv��ꂪ���������̂��A���̃R�~�b�N�̔g�y���ʂŎ�N�w�̃N���V�b�N�t�@���������Ă���炵���B���t�����ł̃q���g�����\�B��Ă���̂ŁA�܂��̐l�͂��Ј�ǂ���I�@�N���V�b�N���y�ɑ���T�O����ς��邩���`�B �@���T�A�݂�Ȃ̉��F���ǂ��ω����Ă��邩�y���݂��B �@ |
| �Q�O�O�U�N�R���P�W���i�y�j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�V���ƒn���������_�E �@�@�\�����ā`�I �@�����͎�s�������炭����ł��������ŁA�a�Ɋ������܂ꂽ���ѐ搶�͎Ԃ̒��ł₫�����`�B�����ɂ������ʼn����ł����B �@���āA�����́A�܂��u�V���ƒn���v���Ȃ���B �@���̊y���ɂ́A���K�L�����Ȃ��I�ƌ�����ŁA�X�R�A�̏��ߔԍ���U��Ȃ���A�܂��ꍇ�킹�B �@���x�݂����l�̂��߂ɁA���ߔԍ��͉��L�̒ʂ�ł��̂ŁA������Q�l�Ɋe���Ő����Ă��ĂˁB �@ �@�`���̃A�E�t�^�N�g�͐����Ȃ��B �@�`�������������������i�W���̂U���q�j�E�E�E�R�U���ߖځi���O�̃t�F���}�[�^�Q�͂P���߂Ƃ��Đ����遨�N�����l�b�g�\���j �@�k���������i�S���̂R���q�j�E�E�E�S�V���ߖ� �@�`�������������������@�������������i�S���̂Q���q�j�E�E�E�V�X���ߖ� �@�`�������������������i�W���̂U���q�j�E�E�E�A�E�t�^�N�g�̎����P�O�V���ߖځi���O�̃t�F���}�[�^�R�͂P���߂Ƃ��Đ����遨���@�C�I�����\���j �@�o�����@�����������E�E�E�P�Q�U���ߖ� �@�`�������������E�E�E�P�S�V���ߖ� �@�`�������������i�S���̂Q���q�j�E�E�E�P�U�Q���ߖ� �@�ŏ��̃��s�[�g�E�E�E�P�V�W���ߖ� �@�P�J�b�R�A�Q�J�b�R�Ƃ������� �@�g�����i�f�������j�ɓ]�������Ƃ���E�E�E�Q�O�S���ߖ� �@�j�����i�c�������j�ɓ]�������Ƃ���E�E�E�Q�Q�P���ߖ� �@���̃��s�[�g�E�E�E�Q�S�R���ߖځ����̃��s�[�g�͂��܂���B�����Q�J�b�R�� �@ �@�Ƃ���Ȋ����ł��B �@�ׂ������ӓ_�Ƃ��ẮA���ԕ��̃��@�C�I�����\���́A�\���̓������悭�����č��킹�܂��傤�B�I�y���قǂ̓e���|���h��Ȃ�����A�����C��������킹����͂��B �@�P�S�V���ߖڂ̂`�������������ɓ���O�̏��߂́A�w�����悭���č��킹�邱�ƁB�㔼�̂R���͊��S�ɂR�U��ɂȂ�܂��B �@�P�U�Q���߂̂`�������������ɓ���P���ߑO�̉��́A�Z�߂ɐ��Ă����`�������������ɓ���܂��B�i�x���͂قƂ�ǂȂ��j�@ �@���ƁA�����������ǂ݂��I�������A��������_�C�i�~�N�X�����܂��傤�B �@�x�e��́A�u�����_�E�v���ǁE���ɕ�����ė��K�B �@�`���̖؊ǂ̓����́A�܂��܂��e���|�������ꂳ��Ă��Ȃ��Ƃ������A��̗���ɂȂ��Ă��Ȃ�����A �����Ƃ����ƃp�[�g�������č��킹�Ă����܂��傤�B�ŏI�I�ɂ́A��l�̐l�����[���Ɛ����Ă���悤�Ȋ����ɕ�������悤�ɁI�i���Г������̔т�H���ċC���������킹�ĉ������H�I�E�E�E���ѐ搶�k�j �@���y��A���ɂQ�������@�C�I�����ƃ��B�I���́A�y���������ėJ�T�ɂȂ邩������Ȃ����ǁA�����ł��y�ɂȂ�悤�ɂƏ��ѐ搶������`�����Ă���܂����B���肪����A���肪����`�� �@���A���낻������炫�n�߂����A���ꂩ��{������Ċ撣��܂��傤�I |
| �Q�O�O�U�N�R���P�P���i�y�j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@���������h�i�E�������_�E �@�@�����c�̋Ɉӂ́A���̌��t�H�I �@��������܂��A�V���̉��t��Ɍ����āA���ѐ搶��tutti�ĊJ�I �@�܂��́A�u���������h�i�E�v�̐i�s���m�F�B�i���x�݂����l�͎Q�l�ɂ��ĂˁI�j �@�@��m���D�P�����c�E�E�E�Q�J�b�R�Ȃ��i�c�D�r�D���Ȃ��j �@�@��m���D�Q�����c�E�E�E�P�C�Q�J�b�R����@ �@�@��m���D�R�����c�E�E�E�ŏ��̂P�C�Q�J�b�R����@�㔼�̂Q�J�b�R�Ȃ��i�c�D�r�D���Ȃ��j �@�@��m���D�S�����c�E�E�E�P�C�Q�J�b�R����@�c�D�r�͂Ȃ� �@�@��m���D�T�����c�E�E�E�ŏ��̂P�C�Q�J�b�R����@�I��̂P�J�b�R�͂Ȃ��ł����Ȃ�e�������֓���A�b�������U�� �@�������A�y��ɂ���ă��s�[�g�̕\�L�̎d�����Ⴄ�Ƃ��������̂ŁA�����p�[�g�̐l�ɂ�����x�悭�m�F���ĂˁB�i����́A�X�R�A�����ď����Ă܂��`�B�j �@�i�s����ʂ����������A�m�F�̂��߁A�����獇�킹�J�n�B�����킹�Ƃ͂����A�搶��rit.��accel.�̕�������������U���Ă��āA�����]�T�̂��郁���o�[�i�h�i�E�o���ҁH�j�͎w���ɍ��킹�Ă������A�قƂ�ǂ̃����o�[�͊y����������������̂ŁA������ƃo���o���Ƃ�������ǁA�܂��A���Ƃ������܂��܂Ői�B �@�����āA�搶���u�݂Ȃ���A�ߋ��ɃV���g���E�X�̃����c�͂�������Ƃ���܂����H�v�Ƃ̎���B �����ł͂Ȃ����A�y�F����͂x�搶���E�B�[�����w�o�����������������A�V���g���E�X���̂̃����c�E�|���J�͌��\����Ă���B����ŁA�u�ȑO���̃h�i�E�̂ق��Ɂg�E�B�[���C���h�g�썑�̃o���h�����܂����B�v�Ɩ؊ǃZ�N����������B����Ɛ搶�́A�u���̎��A�����c�ɂ��ĉ����b�́H�v�@�c���u�E�E�E�H�@���ɉ����E�E�E�v�@ �@�搶�u���ꂶ��A������o���Ă����āB�E�B���i�E�����c�͂R���q�Ƃ������P���q�Ȃ��ǁA��{�I�ɗ���Ă�̂͂R���q�B���ɁA�Q���ڂɏ����ӎ��������Ƃ����B�����ł悭�����Ă�̂́A�h�C�c��́g����������h���gIch liebe dich�h�i�C�b�q�E���[�x�E�f�B�b�q�j�ƌ������t�B�gliebe�h�ɏ����͓_�����銴���łˁB���̌��t�������Ȃ��烏���c�̂R���q��������悤�ɂ��Ă݂ĂˁB�g�h love you�h�ł��܂��������ǂˁB�v �@�ւ��`�A�Ȃ�قǁ`�B�m���ɁA���̈��̌��t�́A�P�E�Q�E�R���Ċ������ł�`�B�ʔ��`���I �@�ƌ�����ŁA�݂Ȃ���A�p���������炸�ɃE�B���i�E�����c����鎞�́A�܂����̌��t���Ԃ₫�܂��傤�`�� �@�����āA������A�e���|�����Ȃ�h��邯��ǂ��A�Ⴆ��rit.�����炻�̌�ǂ����ŕK��a tempo���Ă܂��B accel.�ɂ��Ă����l�B�ǂ����ŕK��a tempo���Ă܂��̂ŁA����������ւ�����������ˁB�@���搶�H���A���̃e���|�̗h��ɂ��āA��������̂́A�Q�E�R���ڂ�S������i�������ł��Ƃ�����j�p�[�g�炵���B�Ƃ������Ƃ́A�z�����A2nd���@�C�I�����A���B�I���ɂȂ�̂��ȁH�@���̂R�p�[�g�̕��͓���a tempo����������ӎ����Ă݂�Ȃ����������ăl�I�@�����Đ搶�̖_���d�������Ȃ��悤�ɁI �@�h�i�E�Ɋւ��Ă͂�����搶����A�u�����ƃC���[�W�������Ēe���܂��傤�v�ƌ����܂����B�Ⴆ�A�傫�ȉԂ��ς��ƊJ�������Ǝv���Ə����ȉ��炵���Ԃ������Ă�����Ƃ��ˁB�m���ɁA���̋Ȃ́g�ԁh�̃C���[�W����ԃs�b�^�����邩�ȁB�܁A���ꂼ�ꉹ���o����������Ȃ��āA�������v�������ׂȂ��炻������ɂ������ʼn��t����悤�ɂ��Ă݂悤�I�@�����ƍ��܂łƊm���ɉ����ς���Ă���͂��B �@���A����ƁA�P�������@�C�I�����́A���ѐ搶����t���W�I���g��������������Ă����B���x�݂����l�͂������胁���o�[����`�����Ă�����ĂˁB �@�Ō�ɁA�Q��قǓ�ȂƖڂ����u�����_�E�v�����킹�܂����B����ς����`�B�ł��A�撣��Ή��Ƃ��Ȃ肻�����B���ѐ搶���u���͂܂��ł��Ȃ��Ƃ�����肾�낤���ǁA�K���ł���悤�ɂȂ邩��A���t�Ȃǂ����Ȃ���ꏏ�Ɋ撣���Ă����܂��傤�B���v�A���v�B�v�Ƃ݂�Ȃ̕s���𐁂������悤�ɗ�܂��ĉ��������B�@�݂�ȁA�搶�̉������C�����ɉ����āA���ꂩ��撣�낤�ˁI�@�����āA�����_�E��̗������������\���ł���悤�ɂȂ낤�I �@���K�̏I��Ɉ��搶����u�����_�E�͐삾���ǁA����Đl���ɗႦ���邱�Ƃ�������ˁH�@��Ɉ��Ƃ͌����ĂȂ��āA�����Ƃ��������������̗���̂Ƃ������������A�L�������苷��������Ƃ��B������A�݂Ȃ���������y�������ɂ����Ȃ��āA�����̐l����U��Ԃ��Ă��������A���ꂩ��̐l���Ɏv����y����ł���������A�Ƃɂ��������������炩�́g�z���h�����ɂ̂��ĉ��t����悤�ɂ��܂��傤�B�v�Ƃ̂��b���������B���`��A�d�����t�ł��B�g�z�����̂���h�܂ł����ɂ́A�܂��͂����ƒe����悤�ɂȂ�Ȃ��ƁE�E�E�B����ɂ́A���K����̂݁I�I �������A���T���T�A�u���K�E���K�I�v��A�����Ă܂����A����ς肻�ꂵ���Ȃ�����˂��B�@���ɂ͋x�݂��K�v�����ǁA��鎞�͂�������撣��܂��傤�`�B �@���T�́A�u�����_�E�v���u�V���ƒn���v��tutti�Ł`���B �@ |
| �Q�O�O�U�N�R���T���i���j�@ �@�@�ߕ����w�Z�@�~�j�R���T�[�g�{�Ԃł��I �@���āA�����Ƃ����Ԃɖ{�Ԃ̓�������Ă����B �@�ߕ����w�Z�́A�����̗��K�ꂩ��S�O���ȏォ����B�W���͂P�O���Ȃ̂ŁA�݂�Ȃ��ꂼ��Ɏ��Ԃ����v����Č��n��ڎw���B�ŋ߂́A���x�̂����J�[�i�r�����y���Ă邵�A���ɖ��q�ɂȂ�悤�Ȑl�͂��Ȃ������B�i�킩��₷���ꏊ���������ˁB�j�@�Ƃ�����ŁA�����x������l�͂������̂́A�S�����Ƃ��W���B������l�A�܂��́A�e�`�[�����Ƃɗ��K�B�P�P���Q�O���ɗ��Ȏ��ɏW�����A���̃Q�l�v���A�����āu����ہv�̍��t�B �@�����́A�]�T�̎��Ԃŗ��K�I���B������ƍ����Ȃ��ٓ����킢�킢�Ƃ��������A�P�R���A���ł���̈�قցB�\�z�ʂ�A������Ɗ����B�ł��A���V�C���悩�����̂ŁA�\�z���Ă������₦���݂͂����Ȃ��B �@���t�̑O�ɂ�������I�P�̏Љ�Ȃǂ�����A�P�R���P�O�����t�J�n�B �@�܂��́A�NJy��S���ɂ��u�I�u���f�B�E�I�u���_�v�B�y���ȋȂł��݂�OK�H �@�����āA�g�����{�[����d�t�B���[�c�@���g�̃\�i�^�B�X���C�h�����̂������X�s�[�h�ŏ����݂ɓ����̂��A�q�������͂ف[���Ɗ��S���Č��Ă���悤�������B �@���́A�؊njd�t�iFl2,Ob1,Cl1,Fg1�Ƃ����Ґ��j�Łu�����̗x��v�i�����̌��j�@�q�������̔����́A�A�A���Ȃ��s���Ȃ��Ƃ����������H �@���́A���njd�t�iTp1,Hr2,Tb2�Ƃ����Ґ��j�Ńt�����X���w�̃t���[���W���b�N�B�ŏ��́A���������Ƃ���t���[�Y�ɋ������䂩�ꂽ�悤���������ǁA������ƋȂ����߂������̂ŁA�W���͂�����Ȃ��Ă��������B �@�����ŁA�q���������悭�����Ă���Ȃ̓o��B �@�N�����l�b�g�O�d�t�Łu�W���s�^�[�v�u�����Ƃ��āv�@�u�W���s�^�[�v�͓r�����烊�Y�~�J���Ȋ����ɂȂ�A�����W���悩�����݂����ŁA���������̂Ȃ��Ȃ��Ă����q�������ɂ����h���ɂȂ��Ă����B �@���ɁA�z�����J���e�b�g�Łu�A�C�[�_�v�u���e�̎ˎ�v�@�����Ƃ��Q����̒Z���ȂŐ����H �@�NJy��A���T���u���̃g���͖؊ǂX���ɂ��u�f�B�Y�j�[���h���[�v�@�q�������̒m���Ă���Ȃ��ƑI���̂́A������ƒ��������̂ŁA�����ɂȂ��Č㔼�������J�b�g�B�܁A���̔��f���������������ȁB �@�����āA���悢�挷�y��̓o��B�NJy��́A���Ɩڂɂ���@����邩������Ȃ����ǁA���y��͂��Ԃʼn����̂Ȃ�ď��߂Ă̎q����Ȃ낤�ȁB �@�܂��́A���{�s�b�R���Ōy���ȃS�Z�b�N�́u�^���u�[�����v�@�s�b�R���̍��������̈�قɋ����ƁA��N���炵���őO��̒j�̎q���u���킟�`�A�������`�B�v�ƌ����Ď����ǂ��ł����B�i�j �@���̌�A��N�A�C�㏬�A�A���T���u���E�t�F�X�^�ƂQ�t�������Ƃ̂���u�A�C�l�E�N���C�l���i�n�g�E���W�[�N�v�P�y�́B����́A�R���~�X���d���̂��ߕs�Q���Ƃ����āA���̃A���T���u���͑��v�Ȃ̂��ƐS�z���Ă������ǁA�Ȃ�̂Ȃ�݂̂�Ȃ������肵�������o���Ă���B���̂Ƃ���ł�����Ɖ��̏o�������s���ȂƂ���͂���������ǁA�c�̐����悭�����Ă��āA��N�̂Q��̉��t���������Ƃ܂Ƃ܂��Ă��邵�A�����������������B�q���������A������l���������X���Ă���悤�������B �@�����āA�c�錷�̂Q�Ȃ́A�q�����������т́u�������x�ł��v�u�ƂȂ�̃g�g���v�ł����B�ǂ���̋Ȃ��̂����Â���ł���q���������āA���Ɂu�g�g���v�́A�܂��܂��q�������Ɉ����ꑱ���Ă����i�Ȃ̂��Ȃ��Ƃ��݂��݊������肵�āE�E�E�B �@�Q���P�T���A�Ō�ɃI�P���t�ł��ǂ������Ɂu����ہv���̂��Ă�����ďI���B�@�̂��̂��Ă���q�������̐����������Ă����Ƃ�������A�����B����́A�ȊԂɊy��Љ�������Ȃ���i�߂Ă���������ǁA���������q���������Q���ł���R�[�i�[�����������������̂�������Ȃ��ƁA�y�������ɉ̂��̂��Ă���q�������̗l�q���݂Ďv���܂����B �@�܂��A���낢�날�������ǁA�~�j�E�R���T�[�g�͖����I���B�@���T����A�܂��V���̉��t��Ɍ�����tutti�ĊJ�B���ꂩ��́A���t��̋ȖڂɑS�͏W���Ŋ撣��܂��傤�I �@�y�N�C�Y�̓����z �@�O��A�Ƃ́E�E�E�V�E�B�[���y�h�̃A���m���g�E�V�F�[���x���N�A�A���o���E�x���N�A�A���g���E�E�F�[�x�����̎O�l�̂��Ƃł����B���������l�`�H �@ |
| �Q�O�O�U�N�R���S���i�y�j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�ߕ����~�j�R���T�[�g���K���Q�l�v�� �@�@�Q�l�v���`�� �@�����A�����́A���悢��ߕ����~�j�R���T�[�g�̖{�Ԃł��B �@�Ƃ�����ŁA�����̗��K�́A�܂����ꂼ��̃`�[���ɕ�����ăA���T���u���̗��K�A���̌�Q�O��������ƑO����Q�l�E�v���̗\��B���āA�e�`�[���̏o�����₢���ɁH �@�\��ʂ�Q�O�������O�ɁA�S���w�K���ɏW���B�Q�l�E�v���J�n�ƂȂ������ǁA������Ə����Ɏ�Ԏ��A�Q�O���߂��ɂ悤�₭�J�n�B�v���O�������ɉ��t��i�߂Ă��������̂́A���s�ψ�����̎��Ԃ̓ǂ݂��Â��������Ƃ������āA���nj��y��`�[���͂P�Ȃ������t�ł����A���Ԑ�B���̃Q�l�v���͗����Ɏ����z���ƂȂ����̂ł����B������� �@�ł��A�S�̓I�ɒZ�����K���Ԃ̊��ɂ͂܂Ƃ܂��Ă����悤�Ɏv���B �@�����A�����͂ǂ��Ȃ邩�H |
| �Q�O�O�U�N�Q���Q�T���i�y�j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�h���H���U�[�N�F�����ȑ�W�ԑS�y�� �@�@�y�F�I�P�E�J���^�[�r���I�H �@�����́A���ѐ搶�̂Q��ڂ�tutti�B �@��T�Ɉ��������A�������V���t�H�j�[�̗��K�B�܂��́A�P�y�͂���������B�n�[���j�[�̊m�F�≹�̃o�����X�Ȃnj��\�ׂ����Ƃ���܂Œ��ӂ�����܂����B�Q�y�͂ł́A�؊ǂ̂��ꂼ��̃t���[�Y�̎����͋C�������ƖL���ɕ\�����ė~�����ƌ����Ă��܂����B�Ⴆ�A�t���[�Y��F�ɗႦ�Ċ�����ȂǁE�E�E�ˁB���`��A����Ȃ��B�ł��A���Е��t�Ńg���C���Ă݂悤�I�@�R�y�͂́A�����g�J���^�[�r���h�I�I�@���̈ꌾ��������܂���I�@���A�ł��A���ԕ���Vn�\���������Ȃ��悤�ɁA���̃p�[�g�͉����T���߂ɂˁB�@�S�y�͂́A�g�����y�b�g�̃t�@���t�@�[�������������ƁI�@�����āA���̌�����т��тƁB�@ �@�����Ƃ���Ȋ����ł����B �@�ŁA����ς荡�x�̉ۑ�́A�̐S�i�H�j�Ɖ����B�搶�H���A�W���j�A�I�P�ł͂ǂ������܂������Ȃ����A�y���u���Đ��ɏo���ĉ̂��Ă��炤�̂��Ƃ��B��������ƁA���ɒe�������͂��Ȃ肢�������ɂ��ɂȂ�̂������B �@���������A��N����搶��tutti�ł��A���܂������Ȃ��Ƃ���͉̂����肵����ˁH�@���lj��y�́A�y��ł͂Ȃ��A�����̒��ɂ���Ƃ������Ƃ���ˁB�@������A�����̒��ł�����Ɖ̂��ĂȂ��ƁA�y��ŕ\���ł���Ȃ��B���i�A�Ȃ��Ȃ������o���Ȃ����ɂ���l���A�y����X�R�A��Ў�ɂ��Љ̂����Ɓi�S�̒��łł���������j������Ă݂悤�B�����Ƃ������ʂ�������Ǝv����B����ƁA�����E�E�E�ǂ������ȃI�P�Ƃ����łȂ��I�P�̍��͂����ɕ����Ƃ��낪�����悤���B�����������Ă���A�悢���������邵�A�_�C�i�~�N�X�����ʓI�ɂȂ�B�ł��A�����������ĂȂ��ƁA����������l��l���撣���Ă����o���Ă��A�P�{�P���Q�ɂȂ�ǂ��납�A���݂��̉���ł����������悤�Ȃ��Ƃɂ����Ȃ肩�˂Ȃ��B�ǂ�������K���Ԃ̏��Ȃ��A�}�E�I�P�ɂ́A�N���A����̂���ςȉۑ肾���ǁA�撣���ď������ł��N���A���Ă������I ���Ƃ́A�Ƃ���ǂ���ŁAVn.�Ƀ����|�C���g�A�h�o�C�X����������A����ς�y��̒e����w���҂͂����Ȃ��Ǝv�����肵�܂����B �@�����tutti�͂Q�T�Ԍ�B���x�́A�O�v���̋Ȓ��S����B�����āA���T�͂��悢��ߕ����w�Z�~�j�E�R���T�[�g�{�Ԃł��I�@�݂�ȁA�t�@�C�g�`�B �@�y���ѐ搶�̓��m������I�H�z �@�݂Ȃ���A��ȉƎO��B�ɂ��Ă͂����m���Ǝv���܂����A�ł͎O��A�Ƃ͒N�̂��Ƃł��傤���H �@�E�E�E�����́A���X��̂��̓��L�ŁI �@�i���Ȃ݂ɁA�O��B�́A�o�b�n�A�x�[�g�[���F���A�u���[���X�ł���`�B���y�ŏK������ˁH�j |
| �Q�O�O�U�N�Q���P�W���i�y�j�@�P�W�F�R�O�`�Q�O�F�S�T�@�h���H���U�[�N�F�����ȑ�W�ԑS�y�� �@�@�m�d�v�V�[�Y�������I�H �@�y�������ꂵ�������i�H�j�u�[�߁v�����������ɏI��A��������͐V�����w���̐搶�ƂƂ��ɁA�V���̃I�P�P�ƂɌ����āAtutti�J�n�B �@�u�[�߁v���I����Ă��A�ق��Ƃ���q�}���Ȃ��A�R���T���̒ߕ����w�Z�ł̎����y�R���T�[�g�i�A���T���u�����S�̃~�j�R���T�[�g�j���I���܂ł́A�Q�̌����̗��K���i�s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ƃ��n�[�h�ȃX�P�W���[���ł���B��T�܂ł̂R�T�Ԃ́A�Ђ�����~�j�R���T�[�g�p�̃A���T���u���̗��K�B�����āA�����Ɨ��T�͂V���̃��C���ł���h���H���U�[�N�̃V���t�H�j�[��tutti�B���łɁA�ڂ�����Ă��郁���o�[�����邩���B�ł��A�R���T���ȍ~�́A�V���̉��t��ɏW���ł������A�������������撣���āI�@�ߕ����̎q�������������t���y���݂ɂ��Ă��邾�낤���E�E�E�B �@���āA�b�����ɖ߂��āA������tutti�̗l�q�����`�����܁[���B �@�����l����w�����Ă���鏬�ѐ搶�́A���N�̗[�ߌ����̎��A���w�����Ƃ߂Ă���ꂽ�̂ŁA�قƂ�ǂ̃����o�[�͊猩�m��ł���B�Q��قǔ�{�搶�̑����tutti�����Ă������������ˁB�[�߂̎��ɂ����������ǁA���ѐ搶�̓W���j�A�I�P���w�����Ă��������邹�����A�ƂĂ��_�a�ʼn��₩�ȕ��͋C�B�݂�Ȃ������̏�tutti�����L�ѐL�тƉ��t���Ă���悤���B���A�A�A�搶�̓��@�C�I������e����邾�������āA�v���v�����Y�o�Y�o�˂�����ł���I�@�`���̃`�F���͂ƂĂ��d�v�Ƃ������ƂŁA�u������Ɠ�l���e���Ă݂āv�Ɛ搶�B���܂ŌQ��Ēe�����ƂɊ���Ă��������o�[�́A�h�L���B�e���Ă�l�A�e���ĂȂ��l�������ɁI �@����ł��A��l���ł͂Ȃ���������A�܂���������Ă���Ă��������ȁH�@����ɁA����ȕ��ɂ��炯�o���ꂽ��A���ꂱ���K�������ė��K���Ă���ł���H�@�{���͂ˁA����Ȃ��Ƃ���Ȃ��Ă���l��l�������ƒe���ĂȂ����Ⴂ���Ȃ����ǂˁB�i�NJy��Ȃ́A�قƂ�ǂ����\����Ԃł��炯�o����Ă邩��A�݂�Ȍ��\����������K���Ă��Ă��ˁ`�B�j �@����ȋ�ɁA�قǂ悢�ْ��������Ɏg�������Ȃ���A��tutti�͐i��ł������B�O���͂P�y�͂����Ȃ�ׂ������K���A�㔼�́A�Q�`�S�y�͂����[���ƈ�ʂ荇�킹�Ă������B����ŁA�����������̋Ȃ̕��͋C�͂킩��������A����܂łɌl���������������Ă��悤�ˁB �@���āA���ѐ搶����A���L�R�̓_����ɒ��Ӂ����ӂ��ė��K����悤����������܂����B �@�P�D�t���[�Y���������肤�������ƁB�i�\��L���ɁB�j �@�Q�D�����������Ƃ����Ɛ��m�ɁI�i���̂��������ɂȂ��Ă�E�E�E�j �@�R�D���Y���𐳊m�ɁB�����x�߂̃e���|�ł�������A�܂����m�ȃ��Y������������c�����邱�ƁB �@�@�@�i�����łȂ��ƁA�c�̐�������Ȃ��ăS�`���S�`���̉��y�ɂȂ����Ⴄ��B�j ���A����ƁA�P�y�͂̕t�_�W�������{�P�U�������̃��Y���̂P�U�������́A�Ȃ�ׂ����ɂ��Ēe�����ƁI�@����͂P�y�͂�ʂ��ĕK������ĉ������I�I�@�i�݂�ȁA�����Ɗy���ɏ������H�j �����́A�v�X��tutti�Ƃ������Ƃ������āA�݂�ȂƂĂ��y�������������B���ꂩ��A�����_�E�Ƃ���Ȃ��T���Ă��邯�ǁA�搶���K�b�J�������Ȃ��悤�A���ꂼ�ꂵ������l�������Ă����܂��傤�I �@�y�^�N�g�̖����Ȋy���݁z �@�����́A�P�N�ȏ�Ԃ�ɏ��ѐ搶�ɂ������Ƃ������ƂŁA���͂ƂĂ��y���݂ɂ��Ă��邱�Ƃ��������B �@����́E�E�E�ӂӁE�E�E���ѐ搶���ǂ�ȃw�A�X�^�C���œo�ꂷ�邩�Ƃ������ƁB �@�[�߂ōŏ��ɂ���������́A����菭�����������O�w�A�������B�������猾�����ǁA������ƃI�J�}���ۂ���ۂ������Ă����B���ꂪ�A�[�߂̃Q�l�v���̎��́A�o�b�T���B�j���炵�������ς�Ƃ����V���[�g�w�A�ɕς���Ă����B�^�N�g�I�ɂ̓V���[�g�w�A�̕��������������Ǝv�����B�i��{�搶����������������Ă����B�j �E�E�E�ŁA�����v�X�ɂ��ڌ����̏��ѐ搶�́E�E�E�������肳���ς�̃V���[�g�w�A�ł����`�B �ł́A�܂����T�`�� |
�@�@![]() �i�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�j �@�@�@�@
�i�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�j �@�@�@�@![]() �ߋ��̓��L�������@�@�@
�ߋ��̓��L�������@�@�@![]() �ŐV�̓��L������
�ŐV�̓��L������