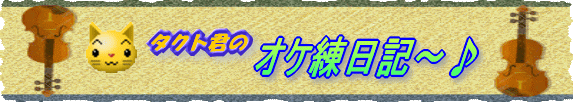
・このページでは、市原市楽友協会オーケストラの練習時における悲喜こもごもを楽しく明るく正直に?お伝えしたいと思います。
 ご意見・ご感想はこちらまで
ご意見・ご感想はこちらまで 
 (トップページに戻る)
(トップページに戻る)  過去の日記を見る
過去の日記を見る  最新の日記を見る
最新の日記を見る
それでは、さっそく・・・。
2007年7月8日(日)  第23回市民コンサート本番です! 第23回市民コンサート本番です!ついに、この日がやってきた〜。今回も、やっぱりハラハラの本番。 午前中は、ブラームス中心にダメ出しをする予定だったんだけど、タンホイザーもアルルもやっぱりいくつか心配なところがあって、わりと細かく合わせました。逆に、ブラームスの方があっさり練習だったような・・・。そんなこんなで、12時前に最後の練習は終わってしまいました。最後に、先生から本番を迎えるにあたって、「2つの大事なこと」について話がありました。 1.自分が演奏しているフレーズ、音楽を感じること 2.ただ音を出さずに、必ず考えて音を出すこと そして、本番・・・「タンホイザー」序曲から。吉田先生がとても気にかけていたクラのトモミちゃんのソロは出だし、ちょっと危うかったけど、最後まで1人でしっかり吹ききったのでした。やったね!トモミちゃん!! それに、弦楽器陣(特に高弦)もよく頑張っていた。妖艶な雰囲気、少し出てたかな。(^o^) 続いて、アルト・サックスさん、ハープさんが加わって「アルル」。「前奏曲」・・・うん?どこからか鼻歌のようなものが? って、吉田先生、オケに合わせて歌ってたよ〜。ひゃ〜。面白い?! と景気よく始まり、サックスさんの美しい音色が会場に心地よく響いて「前奏曲」が終り、問題の「メヌエット」。Vnさん、走らないでね〜と祈るような気持ちで見守っていたけど、昨日と午前の練習の甲斐あって無事通過。「カリヨン」「パストラーレ」と続き、Flさんド緊張の「メヌエット」。先週の冷房の部屋で練習した時、すごく苦しそうだったから、大丈夫かなぁとタクトもドキドキ。最後の音、吉田先生はもうちょっと長く伸ばして欲しかったみたいだけど、とりあえず合格点。よく頑張りました。しめくくりの「ファランドール」では、みんな解放されたように音が踊り狂っていました?! 休憩後、メインのブラームス1番。実は、今まで一度も楽章順に通したことがなかったりする。(先生はTbに気を遣っていたようで、いつも4楽章からだった。) ちょっと心配な面はあるけど、各々の楽章はちゃんと通るようになってきたので、たぶん大丈夫。とこれまた、祈るような気持ちでステージを見つめていたんだけど、ありゃ? 木管トップ陣、ちょっと不調? 緊張の連鎖が見えるかのように、ポロポロっとミスが。頼む、頑張ってくれ〜! 今回は弦楽器主体のtuttiがほとんどだったから、管楽器メンバーには気の毒というか、まだこなれていない部分が多々あったようで・・・それらの不安がやっぱり出ちゃったんだろうなぁ。 でも、まあ、大きな破綻もなく、最後まで無事にたどり着けました。ホッ。みんな、お疲れ様。 アンコールは、ビゼーのカルメン第1組曲から終曲。いや〜、先生もみんなもはじけてるはじけてる♪ という訳で、今回も無事に演奏会が終わりました。 【また化けた・・・!】 打ち上げの席で、客演指揮の先生が必ずおっしゃる言葉がある。 「本番どうなるか心配だったけど、予想以上のよい出来だった。」 そう、アマ・オケって本番で突然化けたりするから恐ろしいというか面白い。 特に、このオケはそのギャップが大きいようである。 とはいうものの、いつも思うけど、そんな秘めた力(?)があるのなら、もっと前の時期から目の色変えて練習しようよ〜。そしたら、もっともっとお客さんも増えるかも。 何はともあれ、みなさん、お疲れ様でした。 |
| 2007年7月7日(土) 18:30〜21:40 ゲネ・プロ&練習 ゲネ・プロというより、最後の悪あがき? さて、いよいよ明日が本番ということで、今日は演奏会場にてゲネ・プロ。 団員は、17時30分に現地集合、舞台セッティング。最近の会館は、とてもサービスがよくなって、照明はすでにセッティングされていて、山台を組むのもテキパキ。40分とかからず、セッティング終了。ホールの職員さん、ありがとう! と言う訳で、予定より少し早く18時30分にゲネプロ開始〜!と思いきや、吉田先生は、「弦楽器が窮屈そう」と配置の修正を始めて、、、結局tuttiが始まったのは、インペクさん作成のタイムテーブル通り、18時40分でした。(^_^;) 普通、ゲネ・プロというと、本番同様にさーっと通し練習をすることなのだけど、吉田流は全然違って、いつもの練習と全く変わらず、細切れに練習した後、その曲を通すといった感じでした。 しかも、会館は22時まで使用可能だったので、21時40分までみっちり・・・いつもの土曜日より1時間近くも長い練習となり、メンバーは相当疲れているようだった。明日、大丈夫かなぁ。 ま、一晩寝ればね。 でも、今日指示されたことは、明日の本番が終わるまで絶対忘れちゃダメだよ! 【オケ練日記成果?】 今日、アルル1組の「メヌエット」の練習で、吉田先生が「頭の弦楽器のフレーズは4分音符を短く!」と直して下さった。オケ練日記を見てくれたのかな? ようやく「メヌエット」らしくなったんだけど、音符が短くなった分、なんで急ぐの? みんな、走る走る。そんなにaccelしちゃったら、中間部が〜! ということで、明日の朝必ずダメ出し練習するとのこと。 |
| 2007年7月1日(日) 10:00〜15:45 全曲 極寒かサウナか・・・究極の選択? 昨日に引き続き、今日も市原青少年会館の集会室で練習。使用料が安いから、あまり文句は言えないけど、ここの冷房には毎年泣かされる。とにかく効き過ぎるのである。ずっとつけていると冷蔵庫内のように冷え冷え。夏の装いで来たメンバーはぶるぶると震えながら風邪の恐怖と闘い、管楽器奏者は、仮死状態となった楽器を蘇生させるべくいつもより余計に息を吹き込み・・・と大変な苦労を強いられる。かといって、事務所にお願いしてとめてもらう(この部屋の空調のオン・オフはボイラー室にあり、勝手にいじれない)と、今度はサウナのような暑さとの闘いになるのであった。ま、練習に集中してれば、暑いの寒いのなんて言ってられないよね。 でも、市民としては、冷房費もきちんと払っていることだし、何らかの対処をしてもらえないものかと思う。 おっと、そんな話はさておき、今日の練習。 ハープのMさんとサックスのHさんが加わって、まずはアルルの合わせ。 テンポの確認、これまでの指示の再確認などしながら、ほぼ予定通り終了。 休憩後、タンホイザー。マエストロが気になる部分をつまみ練習してから通し。フレーズの持つニュアンスや雰囲気について細かい指示が出る。 そして、午後は、ブラームスを4→1→2→3の順で合わせ。ここでもマエストロの気になる部分をつまみ練習、歌い方やフレーズの受け渡し方、どこのパートを聴くべきかなど、半分以上は今まで言われたようなことを注意されました。それと、音符の長さを正確に、走ったりはしょったりしないようにと。こういうのは基本中の基本のような気がするんだけどね。(^_^;) まあ、そんなこんなで強化練習も終わってしまい、あとは、ゲネプロと当日午前の練習を残すのみ。どこまで仕上げられるのか・・・タクトにもわっかりませ〜ん。 昨日の日記にもあるけど、もっともっと指揮を見ましょう!!! |
| 2007年6月30日(土) 18:30〜20:45 アルル&タンホイザー&ブラームス4楽章 Look at me! いよいよ本番まで残り1週間。今日の練習は、アルルから。さっと流してから、要所要所をチェック。どれも、前に言われたことがほとんど。何となく、練習のたびに“ふりだし”に戻っているような・・・。 そして、事件(!)はブラームスの4楽章を合わせている時に発生!! タッ、タッ、タッと思いっ切りよく音が切れたところで、tuttiストップ。マエストロがタクトを止めていることにみんながようやく気付いたからだ。「今、1拍目で棒を振るのをやめたのに、誰も気付かず、次の小節の頭まで行ってしまいましたね・・・。実は、みんながどのくらい棒をみているか、試したんだけど、見事ハマりましたね。」 マエストロは、苦笑い。う〜ん、これじゃあ、マエストロが微妙なテンポの揺れを指示しても、機敏に反応なんかできる訳がないね。以前からも言われ続けているけど、楽譜にかじりついてないで、もっと指揮をちゃんと見ましょう! さて、明日は、ハープさん、サックスさんが加わっての強化練習。しっかり頑張ろう! 【Violinさんにお願い!】 タクトは、アルルの組曲の中では、第1組曲のメヌエットが一番好きです。冒頭の弦楽器のメロディーから胸がキュンとなります。・・・でも、まだ楽友オケの音では一度もキュンとならない。 一番の理由は、Violinの3・4・5小節目の1拍目のスタカートが揃っていないこと。響きのある短い音が理想的だけど、ともかく中途半端に長く弾くのだけは勘弁してほしい。せっかくのメヌエットの持ち味が台無しに・・・。 と言う訳で、両方のViolin奏者さん、よろしくね♪ |
| 2007年6月23日(土) 18:30〜20:45 ブラームス&アルル&タンホイザー 名演奏者は名俳優?! 今日は、ブラームスから合わせ。要所要所で、吉田先生からていねいかつ細かな指摘、指導が入る。どの曲も最初の頃よりは、だいぶ形になりつつある。・・・けど、まだまだ努力が必要だね。 さて、今日は、先生からこんな話がありました。 「タンホイザー序曲のこのあたりは、悪い女神が元の世界に戻ろうとするタンホイザーを自分の色気で誘惑して引き止めようとしているんだから、クラリネットのソロもヴァイオリンも、もっと・・・ね。みなさんは、そういう人じゃないんだろうけど、そういう人になったつもりで弾いて。(笑)」 実は、これと似た話をつい最近耳にした。演奏者は、ある意味俳優のようなもので、曲想に合わせて性格(正しく言うと音色?)を変えなくちゃいけないって。演奏には、まずその人本来の性格が色濃く反映されるから、しっかりとした意志と強い意識を持たないと、それらしい音楽にならないそう・・・。とはいうものの、うちのオケの女性陣は、ピュアな人が多いから、ヴェーヌス(タンホイザーを誘惑する女神)のような妖艶さを表現するのは、とっても大変だろうなぁ。 しかし! ここは一つ、自分の殻を破って(!)頑張ってほしいものである。 ということで、今回はおしまい。 【微笑ましい親子の2コマ♪】 その1 今回は、インペクOhnoさんのお嬢さんが二人(ヴィオラ&トランペット)も賛助出演してくれる! 前回の一日練のお昼休み、Ohnoファミリーが仲良く3人連れ立って歩いている姿に何だかホッ として、思わず微笑んでしまうタクトでした。 その2 さらに、今回、なんとマエストロ吉田のご子息(某M音大在学中)がクラリネットの助っ人として ご出演!! で、やはり前回の練習、終わるやいなや、マエストロは身支度をささっと整え、ご子息のところへ。 「なんだ、まだ楽器を片付けてないのか。終わったら、さっさと片付けて。帰るのが遅くなるだろ。」 と、ひと言。息子さんの方はというと、特に言い訳するでもなく、淡々と楽器を片付けていた。 何となく、ほのぼのとした気分になって、ププッと吹き出しそうになるのを必死にこらえたりして。 確かに、あの時間、市原から都心に帰るにはかなりの渋滞なんだろうなぁ。 しかも、亀のように歩みののろいオケを指導した後の体には、渋滞はさぞかしこたえるだろうし。 お父さん、お疲れ様デス。 でもね、木管楽器はお片づけが大変なんですよ〜。ベストコンディションを保つために、ケースに しまう前にしっかり湿気を取っておかないと! それに、、、クラリネットは、A管、B管って二本もあ るし・・・なんて、息子さんのかわりにちょっと言い訳?! |
| 2007年6月17日(日) 10:00〜15:45 全曲 何を聞くべきか? それが全ての第一歩! 今日も、昨夜に引き続き、集会室にて練習。でも、上からドンドンダンダン攻撃はなく、練習はしやすそう。 隣の運動場では、少年野球がリーグ戦をやっていて、お子様達の声が絶え間なくしていた。いや〜、みんな朝から元気いっぱいだ。僕達も負けずに頑張らなきゃ。 と言う訳で、アルルからスタート。むむ、またもや同じ指摘、、、16分音符の入りでフライングしないように。 その後も、やはりほとんどが弦楽器に対する指摘。でも、何だかね、どれも、前に言われたんじゃ?みたいなことばかり・・・。ちっとも進歩していない? う〜ん。 そして、ついに午後、ブラームスの練習中に、先生から決定的なひと言が! 「3月からここの練習に来ていてずっと思っているのは、お互いを聞いていないなぁということ。いや、聞いていないというより、聞くべき音がわかっていない気がする。だから、出るべき音がちゃんと聞こえてこないし、自分の音にばっかり必死になってしまう。まずは、基本となるリズムをどの楽器がやっているのか、自分はその部分でどんな役割をしているのか、表に出るべきなのか、控えめにするのか、そういうことを理解して弾くことを考えてほしい。」 ・・・確かに、みんなの演奏を聞いていると、とても一つの音楽をやっているようには聞こえない。弦と管のずれどころか、同じヴァイオリンパート内でもバラバラの感じ。それは、たぶんそれぞれが自分のテンポ感で演奏しているからではないかと。つまり、先生がおっしゃるように他を聞いているようで肝心なところを聞いてないのだと思う。 こんな状態では、ブラームスの一番は完全にお手上げ。何人かは、録音を録って聞いているようだけど、できることなら、全員に今の自分達の演奏を聞いてみてもらいたい。とてもとても人前で聞かせられる演奏ではないと痛感すると思う。 そこで、タクトからもお願い。これから本番までの3週間、一日30分でいいから、オケのために時間を作って下さい。そして、音出しできなくても、音源を聞きながら演奏するつもりで自分のパート譜をしっかり見て下さい。 「演奏会の曲なら、移動の車の中でいつも聞いているよ〜」と言う人もいるだろうけど、ただ聞いているだけじゃ、聞き流している部分が結構多いんだよ。効率よく成果を上げるには、やはり楽譜を見ることが大切。これを繰り返すことで、今までただひたすら自分の音ばかり追っていたのが、だんだんと他の音も耳に入るようになるし、音楽全体の流れが確実につかめるようになると思う。時々はスコアを見ながらというのが、より効果的なんだけど・・・とにかく、まずは自分のパート譜からスタートしてみよう。 そして、弦・管ともに、集まれる人だけでも早めに集まって、パート練、セクション練をやりましょう! 残り3週間、最善の努力をしましょう〜。 |
| 2007年6月16日(土) 18:30〜20:45 ブラームス&アルル&タンホイザー おお!上からダッタン人の来襲!? さて、今日は1階の集会室で広々のびのび練習ができるなぁと思っていたら・・・上からドンドンダンダンとものすごい音が聞こえてきた。 うん? これは・・・ボロディン作曲の「ダッタン人の踊り」ではないか! そう、すぐ上の部屋で、市原フィルさんが練習していたのでした。いや〜、ものすごい迫力。(といっても、聞こえてくるのは、ほとんど打楽器&金管なんだけどね。) こちらも負けじと・・・なんてことはなくて、こちらはややおとなしめのブラームス2楽章からスタート。いつものように、先生がチェックしてきた箇所をつまみ練習。なので、曲が止まるたびに、上からダッタン人がワーッと襲ってくる感じでちょっと練習に集中しにくかった・・・。しかも、ダッタン人の後は、チャイ様の「イタリア奇想曲」!! なんと派手なっ! でも、素敵〜♪ と思わず、上の部屋へ迷い込んでしまいそうに・・・。 こちらの練習はというと、相変わらず8割方、弦練習みたいなtuttiの状況で、つくづく弦楽器のオケにおける重要さ、基礎の大事さを思い知らされるのだった。 今日は、要所要所を合わせただけで、あとは明日の一日練に持ち越しとなりました。 おしまい。 |
| 2007年6月2日(土) 18:30〜20:45 アルル&タンホイザー&ブラームス3楽章 ピッチ(音程)がなあ・・・。 今日は、2ndとヴィオラ、打楽器にエキストラさんが参加して下さって、音楽室ではかなり窮屈な感じ。でも、1stはコン・ミスさんがお休みで、何となく心細さが・・・。 で、1ヶ月ぶりとなる「アルル」。はにゃ〜、すっかり振り出しに戻ってしまっている感じ。音程もリズムも今一つ合わないし、それぞれが自分のパートを弾く(吹く)ことに精一杯で、全然アンサンブルができてないっ! 明らかに、個人練不足である。でも、吉田先生は怒ることも慌てることもなく淡々と、以前にも注意されたことを繰り返し繰り返しおっしゃっていた。タクトは、何だかとーっても申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。 と言う訳で、今日指摘されたことをピンポイントで書くと・・・ 【前奏曲】 ・アウフタクトの16分音符は充分待って入る。 ・fからpに落とすところはしっかりと ・後半のメロディー(弦、トロンボーン)は、伴奏の3連符の中にきちっとはまるように。 【メヌエット】・目の前に三角形があるつもりで、常に3拍子を感じて弾くこと。 【カリヨン】 ・出だしのホルンは、先へ進む感じは必要だけど、先走り過ぎないように。 ・中間部、弦は管楽器のメロディーにつられて書いてないところでクレシェンドしない。 【パストラール】・一つ一つの音を響きを大切に充分に保って、ソステヌートの雰囲気を出す。 ・ホルンは4拍目の頭までしっかり音を残す。 【ファランドール】・Pからはテンポをまくし立てていくので、指揮をみて合わせるように! 【タンホイザー】・強弱、クレシェンド、デクレシェンドについて、もう一度今までの指摘をよく見直す。 ・それぞれのメロディーが、物語のどのシーン、またどんなことを描写しているのか、把握して弾くように。 とまあ、こんなところかな・・・。 でも、、、みんなには、やっぱりもっと音程に関してシビアな耳を持ってほしいとタクトは思いました。強弱とか表情とかは、音程が合ってこそのものだと思うんだよね。今のようなアバウトなピッチだと、音の響きが全然なくて、とっても雑で稚拙な演奏に聞こえるばかり。きつい言い方かもしれないけど、一人一人がしっかり自覚しないと! そして、もっともっと個人練習をして下さい!! 今日はここまで! |
| 2007年5月12日(土)〜26日 弦、猛特訓の合宿、、、&有望新人さん続々加入! とってもお久しぶりの日記になってしまった。楽しみにして下さっている方(そうたくさんはいないと思いますが)、ゴメンなさい! 今週からしっかり再開です♪ まずは、合宿の様子から。 出席メンバーの状況などもあって、先生はまず弦の強化に力点をおいたようで、練習時間の4分の3くらいは弦練となりました。パート、セクションの段階でしっかり合っていなければ、合奏しても曲にならないというのが先生の基本方針らしく、練習箇所を絞って入念に、しかも妥協することなく、練習は進められ、終わる頃には弦メンバーはかなりぐったりなのでした。その間、管のメンバーはというと・・・決して羽を伸ばして遊んでなどおらず、練習部屋が豊富にあったので、トモミちゃんは山ちゃんにタンホイザーの特訓を受け、その他のメンバーは、ブラームスのセクション合わせ。夕方からヴィオラのOちゃんのお友達、ファゴット吹きのKさんが加わり、木管のセク練はかなり充実していました。 合宿と言えば、やっぱり楽しみなのは、夜の大宴会! 大いに盛り上がったけど、、、翌日はまた吉田先生の猛特訓が、弦メンバーを待っていたのだった!! さて、合宿の成果やいかにとばかり、先週・今週の練習はtutti。合宿では、あまり通し練習をしなかったけど、そろそろ曲を通す段階にきたらしく、ある程度流して、どうしても気になるところは止めて指示という練習になりました。先生のおっしゃることは、常に一貫していて、いつも基本となるリズムに耳 |